- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
診察室に訪れる子どもや青年の中に,程度の差はあるにせよ,トラウマの存在に気づくことが増えたように思う。不登校や希死念慮,自傷行為などを主訴に自ら,あるいは家族に連れられて受診をしてくる子どもや青年の中に(時にはその家族の中にも)トラウマが潜んでいるケースに出会う機会が増えた。これまでトラウマというと,私たちがイメージするのはPTSD(心的外傷後ストレス障害)であった。しかし,実際の臨床で多く出会うのは,はっきりとPTSDとまでは診断はできない,閾値下にあるトラウマである。生存の危機とまではいかない,もう少し程度の軽い出来事でも状況によってはトラウマとなり得るし,トラウマ反応を生み出すことがしばしばある。例えばいじめなどの苦しかった体験から,こころに傷を負い,トラウマ反応を起こしている場合である。
不安・抑うつ,強迫,幻覚妄想,食行動異常や依存症などのさまざまな表現型で精神科を受診し,経過の中でトラウマの存在に気づくという場合がある。従来の精神疾患の背景にトラウマが潜んでいることに気づかず,なかなか治療が奏功しない,あるいは慢性化,難治化してしまうということも少なくない。では,トラウマに気づくことで何が変わるのか。どのような時にトラウマに気づき,気づいた時にはどうしたらよいのか。そして,トラウマが癒える(治癒する)というのはどのような時なのか。
本稿では三つの症例を交えながら,トラウマという視点から思春期臨床における治癒とはどのようなものなのか,筆者がトラウマに対しどのようにアプローチしているかを記したい。なお,症例の記載においては,プライバシー保護の観点から個人を特定できないように配慮し,大幅に改変してある。
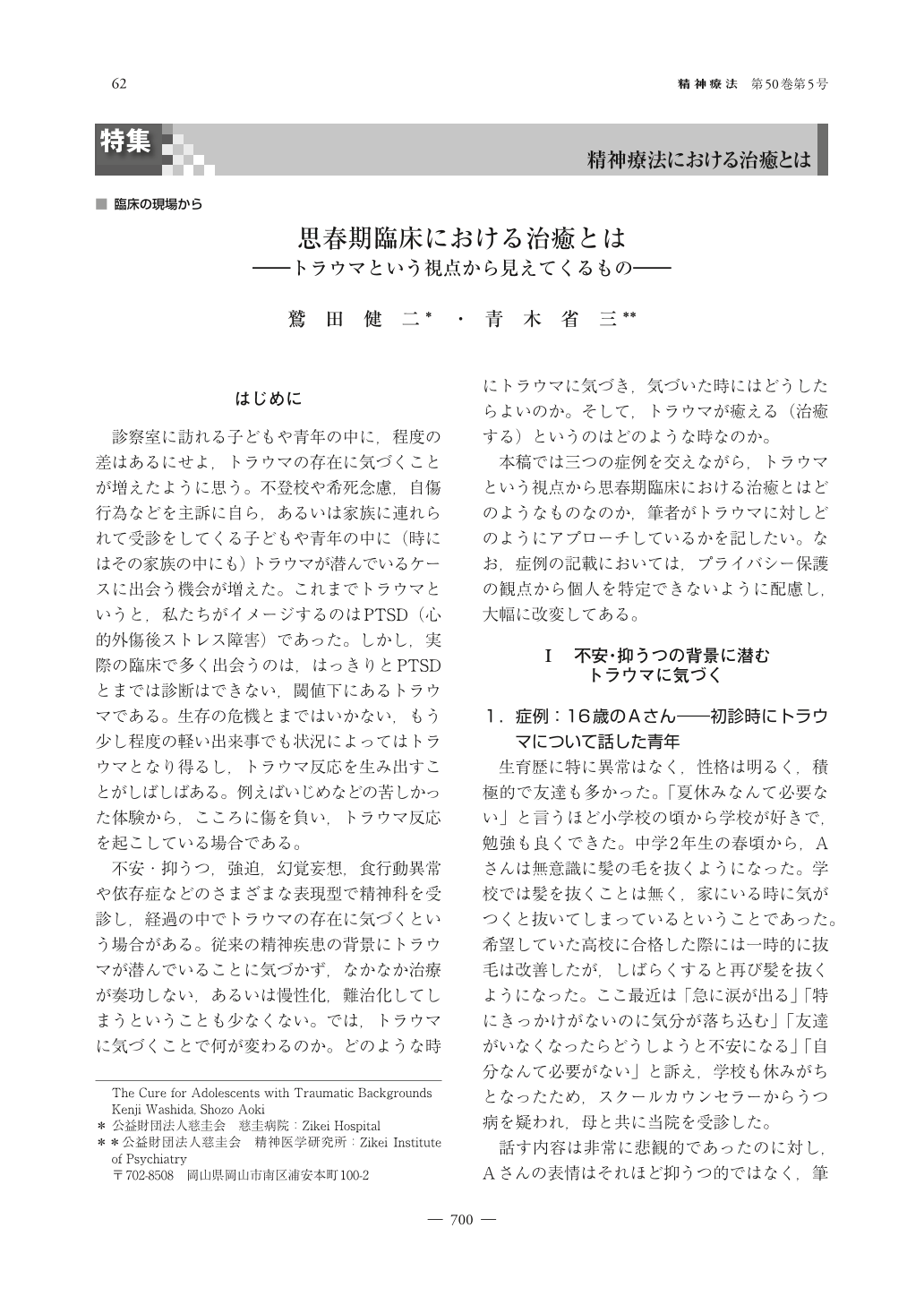
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


