- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
ここで児童臨床における精神療法を論じるにあたり,別項目に思春期臨床が存在することから乳幼児期から中学生年代までの子どもの精神科医療や心理相談機関での活動を児童臨床と呼んでおきたい。そのうえで,児童臨床と思春期臨床の重複を避けるため,本論では幼児期と学童期を対象とした精神療法について論じることとした。その年代の終末期にあたる高学年の小学生は青年期の入門段階(Blos(1962)のいう“preadolescence”)にあたり,すでに幼児とも小学校4年生あたりまでの学童とも異なる心性が優勢になっていく年代であるが,ここでは児童臨床の最終盤に位置づけておきたい。そのうえで本論は幼児期から青年期入門段階を含んだ学童期までの年代の精神療法とは何かを論じ,その一環として子どもの精神療法における「治癒」について考えてみたい。
そう書きだしながら筆者は子どもの精神療法における治癒を論じることにいささか迷いを禁じ得ない。思い当たるその理由の一つが,子どもの心の問題や疾患が治癒することとはどのような治療ゴールに到達することかという問いへの答えがはっきりと像を結ばないことにある。身体疾患にならって「治癒とはその問題や疾患の出現以前の心身の状態に復すること」と単純に考えてよいのかどうか。そもそも身体疾患自体がそれに罹患し回復した後の身体状態と発症前のそれとが同じかというと,そんなことはないだろう。多くの疾患では良くも悪くも罹患し回復した後にも罹患により変化した身体状態を引き続き持ち続け,それを含んだ新たな身体の機能システムとして生きていくのではないだろうか。
それは精神疾患の場合でも同様で,大半の疾患の罹患によって人はその疾患を抱えた心理状態を自己そのものとして経験することで,罹患前とは多少とも異なる心性を抱えて生きていくことになるだろう。治癒像とはそうしたものであり,それは人にとって良くも悪くも新しい自己なのだと筆者には思えてならない。「いわんや子どもにおいてをや」である。
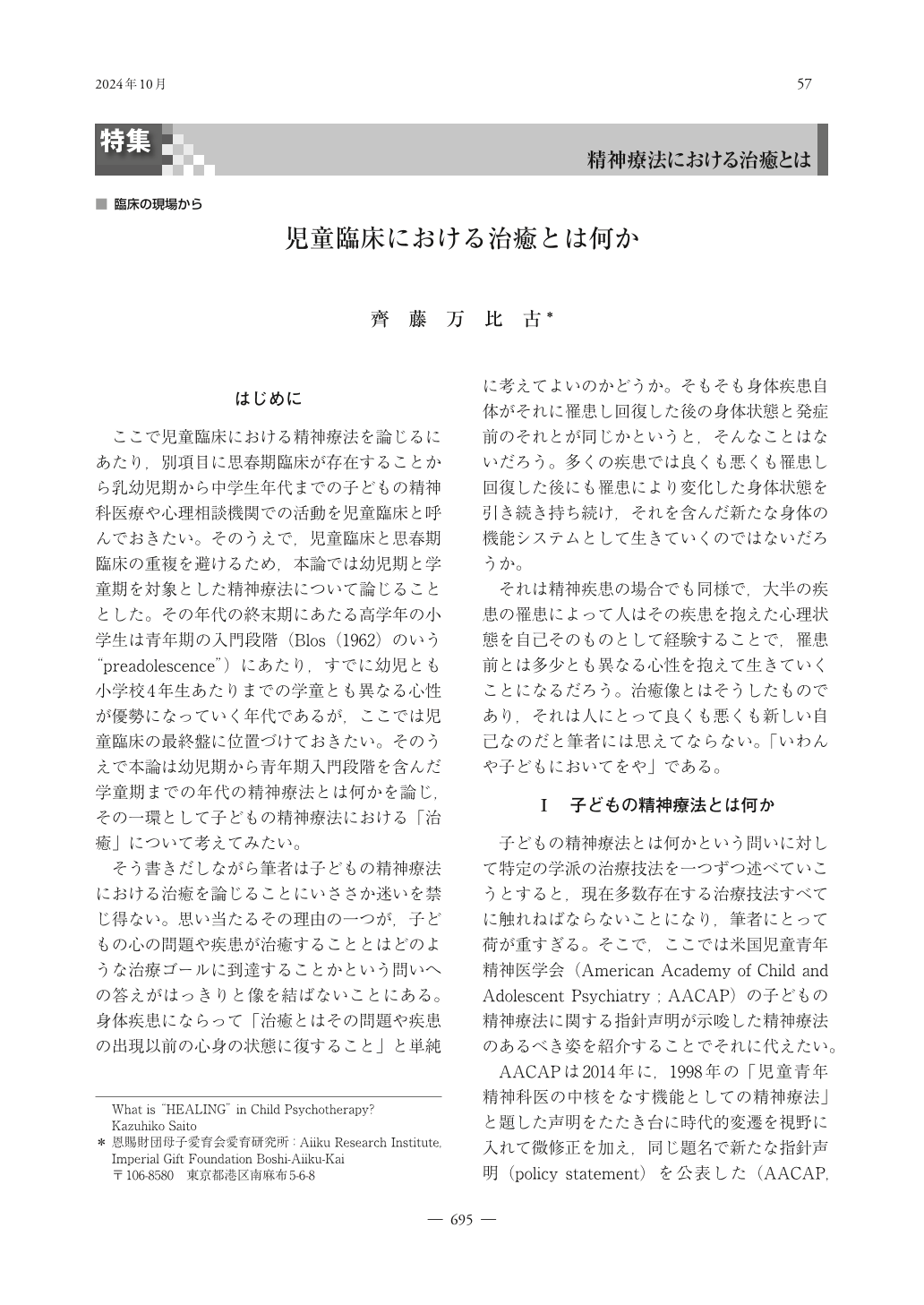
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


