- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
本特集の編者である北西憲二先生から質問をいただいた。「社会福祉領域のソーシャルワークでは治癒はどのように考えられているのか」と。「治癒」についてはこれまで慎重に考えたことがないように思う。その理由として,100年以上もの長い歴史を持つソーシャルワークや社会福祉領域での相談援助は,「セラピー」を行うのではなく,あくまで「トリートメント(処遇)」を実施するものと教わってきた。その意味では,ソーシャルワークの実践は治癒という用語からはるかに遠いものであると言えるかもしれない。
治癒とは,病が癒えること,病が治ること,治療することから生まれる一つの状態であると捉えると,明らかに医学領域や精神・心理に関連する看護,保健領域で使用される用語であるといえる。
ソーシャルワークの実践では,治癒はないと言い切れるかもしれないが,治癒の「癒し」の部分を切り離して,癒しについて考えたい。それなら,相談・支援実践上に関連する事象として存在するかもしれないと思う。
例えば,援助者がクライエントに癒しをもたらすような支援・援助をしているかもしれない。その実践現場の歴史的展開プロセスにおいては,クライエントとの関わりを通して援助者が「癒される」ことはなかったのだろうか。援助者やクライエントの双方の人間関係形成のプロセスが存在するのであれば,そこには互いに癒しあうという事象は生じるであろうと考えられる。援助・支援の実践では,治癒を目標としてはいないとしても結果的に双方に癒しをもたらしていることはあり得ることである。
本稿では,社会福祉施設をはじめとする多領域にわたり展開されているソーシャルワーク支援について精査し,その歴史的変遷のプロセスにおいて治療がどのように捉えられ,どの専門領域で討論されてきているのか,または議論されてきたのか,援助・支援実践の目標や効果を詳細に紐解き,治療や癒しの探究を試みたい。特に,専門領域別ソーシャルワーク,人の6側面の理解とソーシャルワーク,方法論的モデルやアプローチの適用に焦点を当て,癒しの実体を探究していきたい。
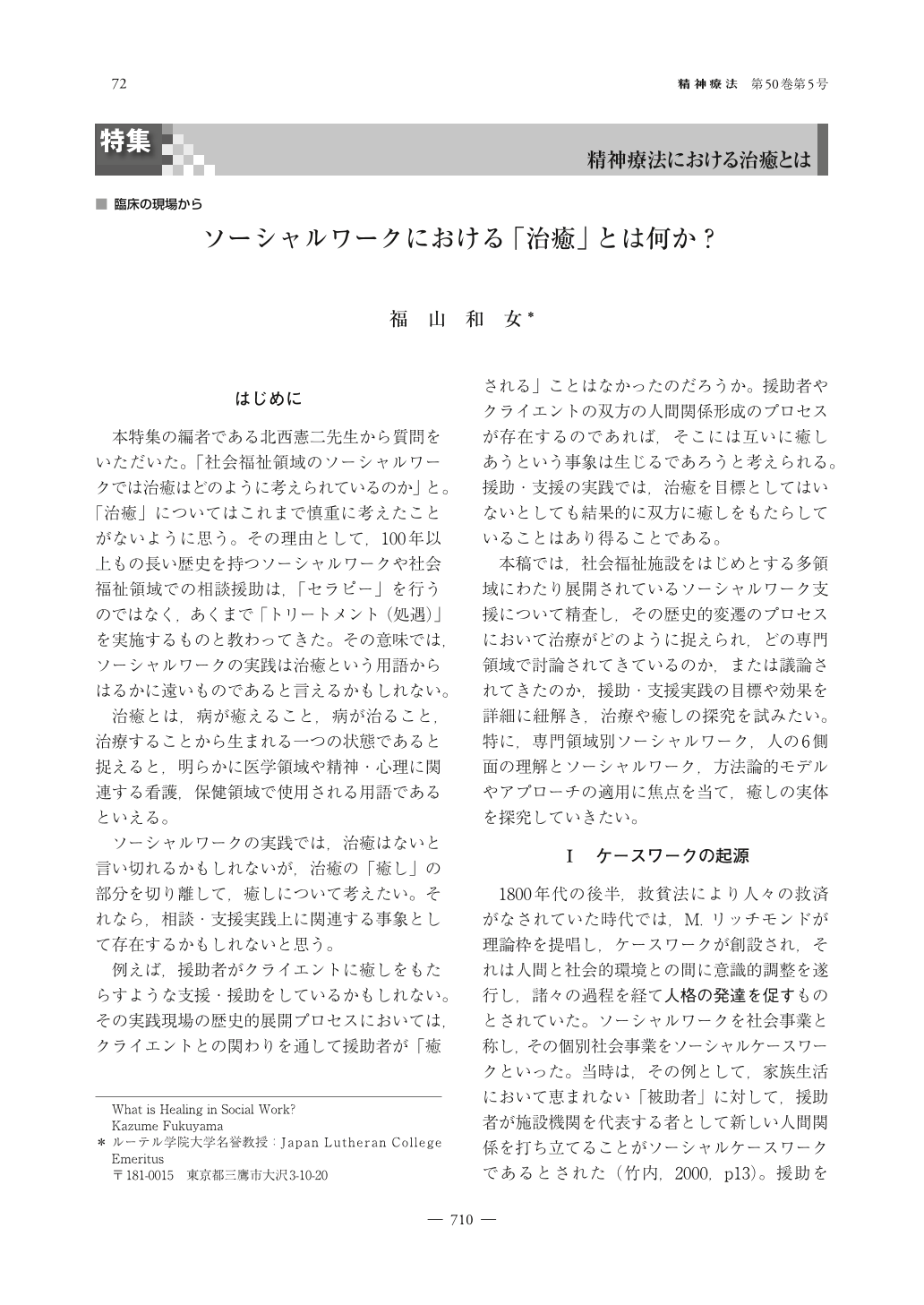
Copyright© 2024 Kongo Shuppan All rights reserved.


