- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 見立てとは?
心理支援のための面接は,ただのおしゃべりではなく,クライエントの福祉を高めることを目的とした働きかけである。そのために,見立てやフォーミュレーションが大事になってくる。
ここでは見立てとフォーミュレーションを交換可能な用語として用いる。それらは,心理支援を行っていくための実用的なクライエント理解,すなわち関わりや介入の方針を導く理解のことである。見立ては「問題は何か(1つとは限らない)」「誰が(何が)変わるべきか」「クライエントが取り組むべき課題は何か」「課題を乗り越えるためにクライエントはどのような体験をする必要があるか」「目標は何か」「そのための効果的な関わり方はどのようなものか」といった問いに取り組むものである。
以前,見立てをテーマにした研修会で参加者にアンケートを取ったことがある。そこからは多くの心理職が見立てに苦手意識を持っていることが窺われた。若手の心理職に限らず,一定の臨床経験を積んだ中堅以上の心理職でも,見立てに苦手意識を持っている人がたくさんいるようであった。
なぜ,見立てに苦手意識を持つ心理職が多いのだろうか。これらの心理職は,訓練において見立てについてしっかり学んでこなかったのだろうか。私は,これらの心理職は,自分が今いる現場での実践にはそぐわない見立ての考え方を教わってきて,それでも教わったことを真面目に忠実に守ろうとした結果,見立てに対する苦手意識が生まれているのではないかと疑っている。
ここで私が「現場での実践にそぐわない見立ての考え方」と呼んでいるのは,見立てに関する次のような考え方である。①見立ては初回面接の終わりに立てるものである。②見立ては心理支援の他の要素(受容,共感,承認,傾聴,探索,介入など)からは独立した作業である。③見立てにおいては客観的で科学的に正しいことが最も重要である。④見立ては心理職が単独でする作業である。
もし読者が見立てをこのような仕方で捉えているのなら,見立てを苦手だと感じるようになっても当然だろうと思う。本稿においては,以下,こうした見立ての考え方がいかに多くの心理職の現場の実践にそぐわないかを見ていく。そして,より現場の実践にふさわしく,それを豊かにするような見立ての概念化を示したい。
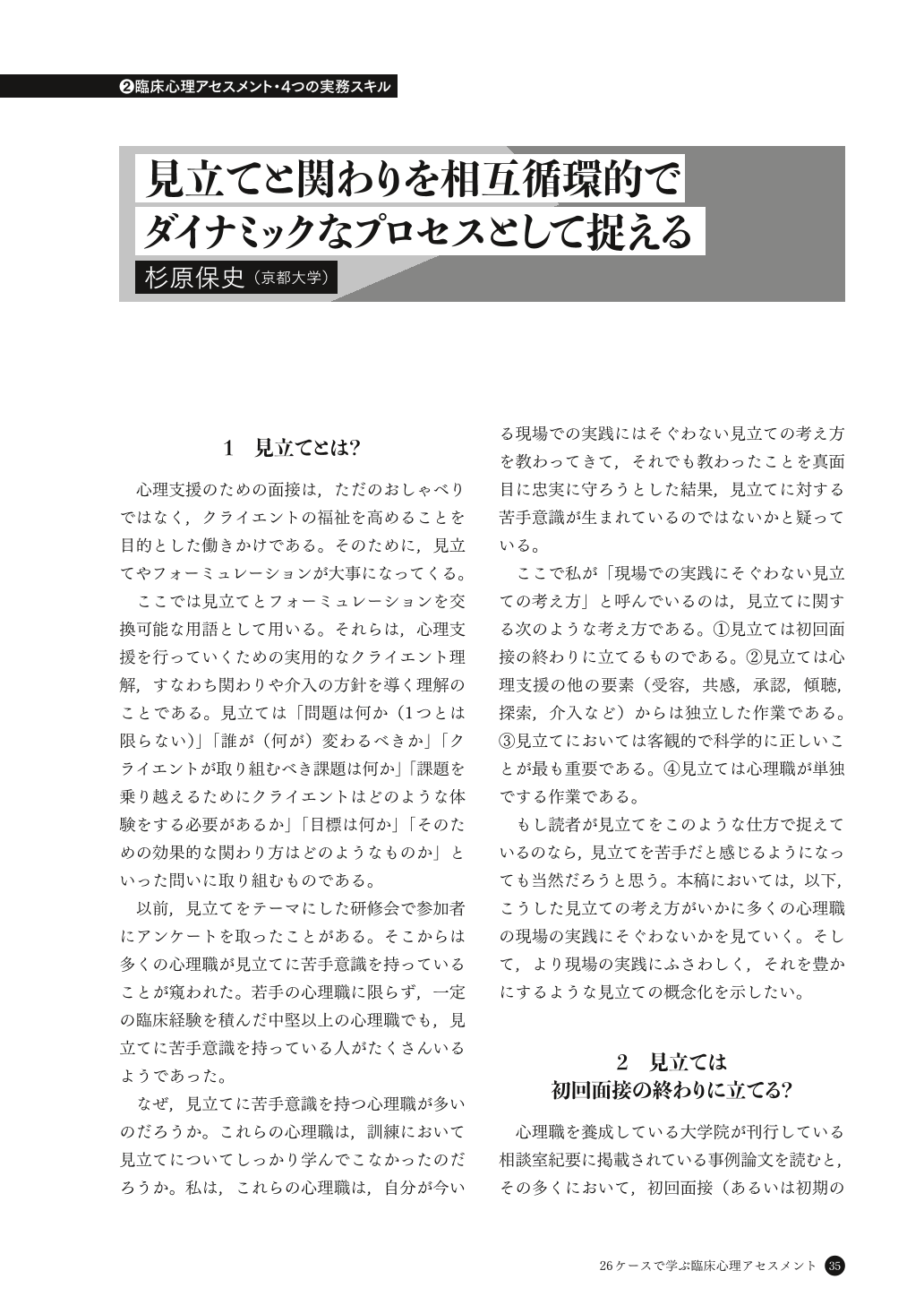
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


