特集 26ケースで学ぶ臨床心理アセスメント――インテークとフィードバックをつなぐ〈スキル7〉
観察――行動アセスメント
黒田 美保
1
1田園調布学園大学
pp.18-22
発行日 2025年8月30日
Published Date 2025/8/30
DOI https://doi.org/10.69291/cp25070018
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1 はじめに
臨床心理アセスメントにおいて,「観察」は,面接や心理検査と並ぶ主要な情報収集手段である。観察は,クライエントが示す非言語的な情報,たとえば視線,姿勢,運動,表情,反応のタイミングといった行動を通じて,その人の内的状態や心理的特性を把握するために不可欠である。これらの行動は,言語による応答とは異なり,意識的に操作されにくいため,より素の状態を反映するデータとしての信頼性が高いといえる。
特に子どもや発達障害のあるクライエントのアセスメントにおいては,言語的応答のみでは十分な情報が得られない場面が多く,行動観察が果たす役割は極めて大きい。言葉で気持ちや考えを伝えることが難しい子どもたちにとって,行動は重要な「メッセージ」のひとつであり,それを正確に読み取るためには,観察スキルが求められる。
本稿では,行動観察を大きく「インフォーマルな観察」と「フォーマルな観察」に分けて述べる。前者は学校や幼稚園,保育園,家庭といった日常生活のなかでの自然な観察や機能分析といった臨床的な手法,後者は標準化された手続きによる行動観察に基づく心理検査,特に自閉症観察尺度第2版(Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition : ADOS-2)を取り上げる(Lord et al., 2012)。また,知能検査など構造化された心理検査においても,検査中に示されるクライエントの反応様式や対人行動の観察が,得点結果の解釈や支援計画の立案に直結する重要な情報源となる。それについても言及し,観察を通して構築される行動アセスメントの全体像を多角的に捉えていきたい。
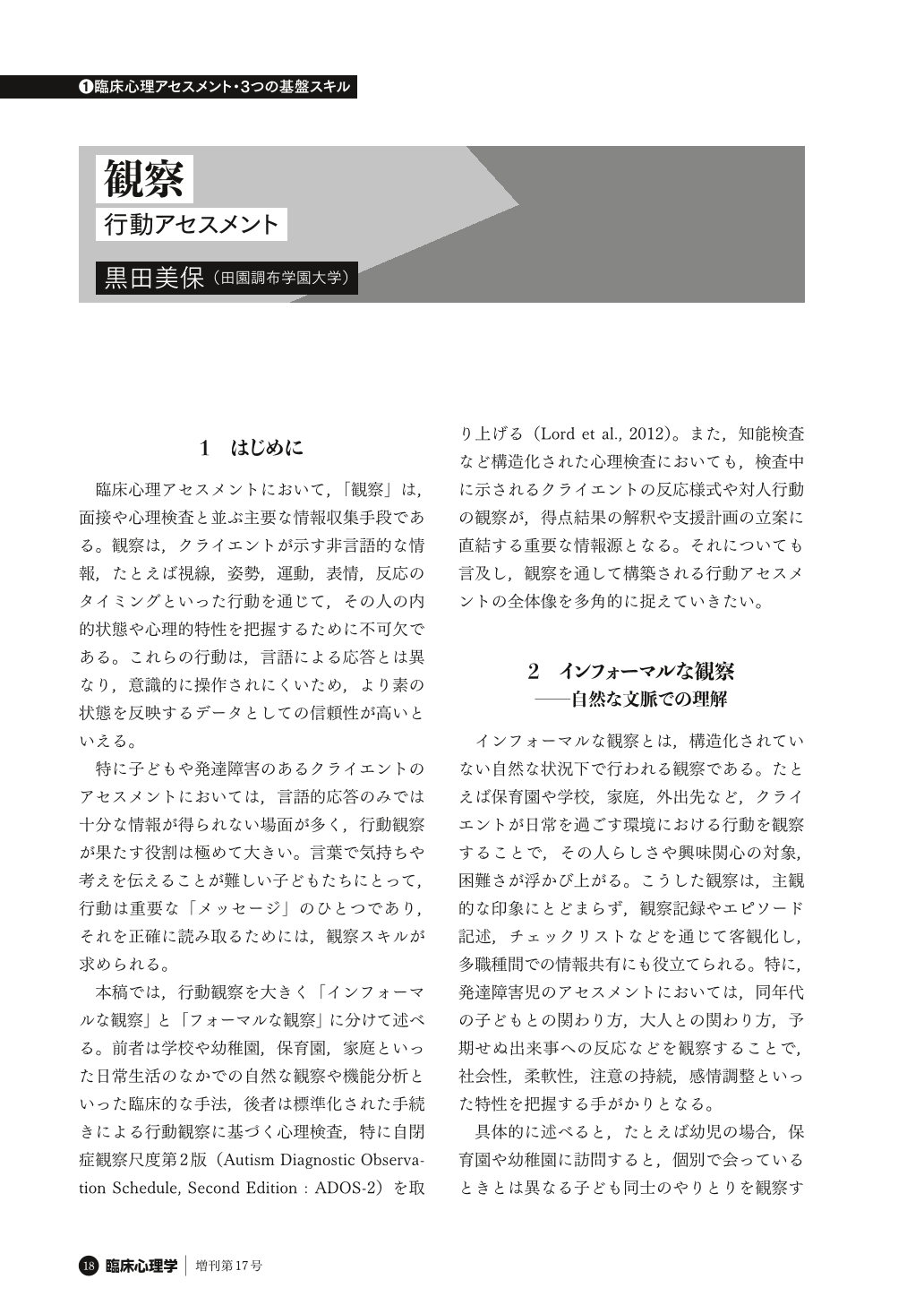
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


