- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I はじめに
社会の中に「お店」を出して何らかの経済行為を行おうとする場合,まずそこでは何を売っているのかを明確にする必要がある。それは,社会の中でどのような位置取りで,どのような機能を果たそうとするのかということを示すものであり,それを明確化することが「お店」を打ち出す者の責任である。屋号を定め,そのウリを定義する約款を策定し,その収支から,定められた割合の税金を社会に納める。そうしたことを介してお店は社会の中に公認される。「開業」のハード面はこうして成立している。
では,我々はいったい何を売っているのだろうか,そして誰にそれを買ってもらおうとしているのだろうか―これに関連して重要なことは,「心」に関わる社会サービスが,これまでの歴史の中ですでにさまざまに立ち上げられているということである。心身の不調は医療に,健全な発達は教育に,労働上の問題は労務に,といった具合である。ところが「心の問題」は,実は日常生活のあらゆる場面に出現し,こうした縦割りのサービス構造では,どうしても漏れ落ちるところが出てきてしまう。あるいは逆に,複数の関係者が生じて「船頭多くして……」という事態が生じることもある。さらに現代の「心の問題」は,いわば旧来の精神病理学の枠づけを超えて遷延化・多様化しており,精神医療だけでは賄いきれないほどに裾野の広いものになっている。にもかかわらず,いや,だからこそ,精神医療の現場は,最早キメの細かい診療が難しいほどの逼迫状況に瀕している。
こうした境界線の不明瞭な混乱した状況の中で,開業心理士は,いったいどのようなお客様を相手に,どのように自分の仕事を創り出していくのか。本稿では,我が国における「心理の開業」の歴史を踏まえながら,いわゆるsubclinicalな領域を扱うための技能の問題や,その中での医療との連携の問題を考えてみたい。
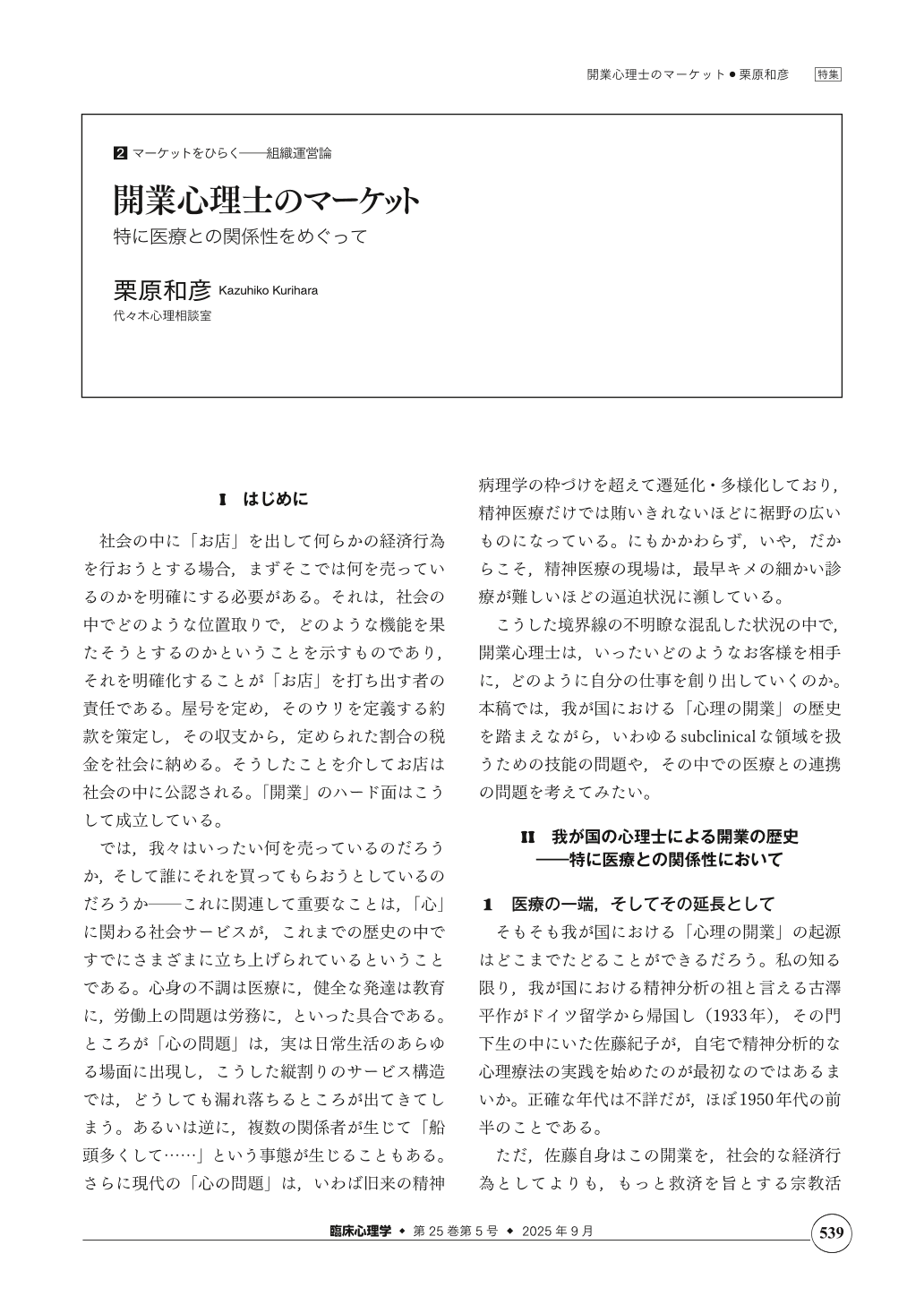
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


