- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
I コア・ストラテジーとTIC
トラウマインフォームドケア(Trauma Informed Care : TIC)が我が国でも浸透,普及しつつあり,喜ばしく思う。その一方で,精神科医療のなかでの認識の広がりや活用はまだ十分とは言えない。本稿では,主に行動制限最小化の観点から,TICがどのように役立つのかについて,近年の研究成果物を交えて紹介する。
筆者がTICに初めて遭遇したのは2010年頃に行動制限最小化に関する研究活動をしていた時のことで,重要な基礎理論のひとつとして米国のある論説に取り上げられていた。当時は現在と同様,わが国で隔離や身体的拘束といった精神科医療における行動制限の最小化が話題となった時期で,研究活動の一環として,米国の看護師のグループが提唱したCore Strategies(コア・ストラテジー)(Huckshorn, 2004)の翻訳機会を得た。その邦訳は4回の短期連載シリーズとして『精神科看護』誌に掲載され,筆者は連載第3回(第2部)の基礎理論に関する部分を担当した(杉山ほか訳,2010)。
コア・ストラテジーは,精神保健領域における隔離身体拘束最小化のための6つの方策で構成された包括的な取り組みで,4つの基礎理論を置く(表1)。トラウマインフォームドケアはその基礎理論の3番目にあたる。ちなみに他の3つは,1つ目が「神話的通念と思い込み」で,隔離と身体的拘束はしっかりとした現場経験に裏付けられた形で行われているという認識は,何ら学術的根拠のない神話であり思い込みである,といった痛烈な指摘に基づく認識変革の要請である。2つ目は「公衆衛生学の考えに基づいた予防モデル」で,行動制限の最小化は経験論でなく,あくまで科学的手法や概念によって対策されるべきという考え方,4つ目は「リカバリーモデル」で,当事者性を特に重視する形でこれを基礎理論に置いている。
TIC以外の3つに関しては,当時であってもそれまでの知識で何とか理解できたが,TICだけはどのようなものかすぐには解らず,そもそもこの3語から成る英語の意味が直訳では全くイメージできなかった。何度か読み返した末に,さらなる関連文献を当たることになったが,やはりすぐには解決しなかった。というのも,当時TICに関する文献はほとんどなく,コア・ストラテジーの著者らが関与する論説を中心に情報はわずかで,日本語の資料に至っては皆無であった。このようにして苦労の末に翻訳したのが先の文献である。当時,用語の解説として,訳注にTICの説明を載せた(表2)。
その後,共著者の石井美緒らは2014に本場米国マサチューセッツ州で行われたコア・ストラテジー研修に参加し,開発者らから直接の教えを受けた。帰国後,『精神看護』誌にて報告し,共同意思決定に基づく事前指示である「セイフティプラン」(佐藤,2014),当事者参加の重要性を示す「コンシューマー」(三宅,2014)とともに,コア・ストラテジーの観点からTICについて紹介している(石井,2014)。その中で,米国では行動制限はもはや治療手段ではなく治療の失敗とみなされるということや,TICとはトラウマを念頭に置いて臨むケアであること,TICを実践する具体的な方法(表3)などについて解説している。
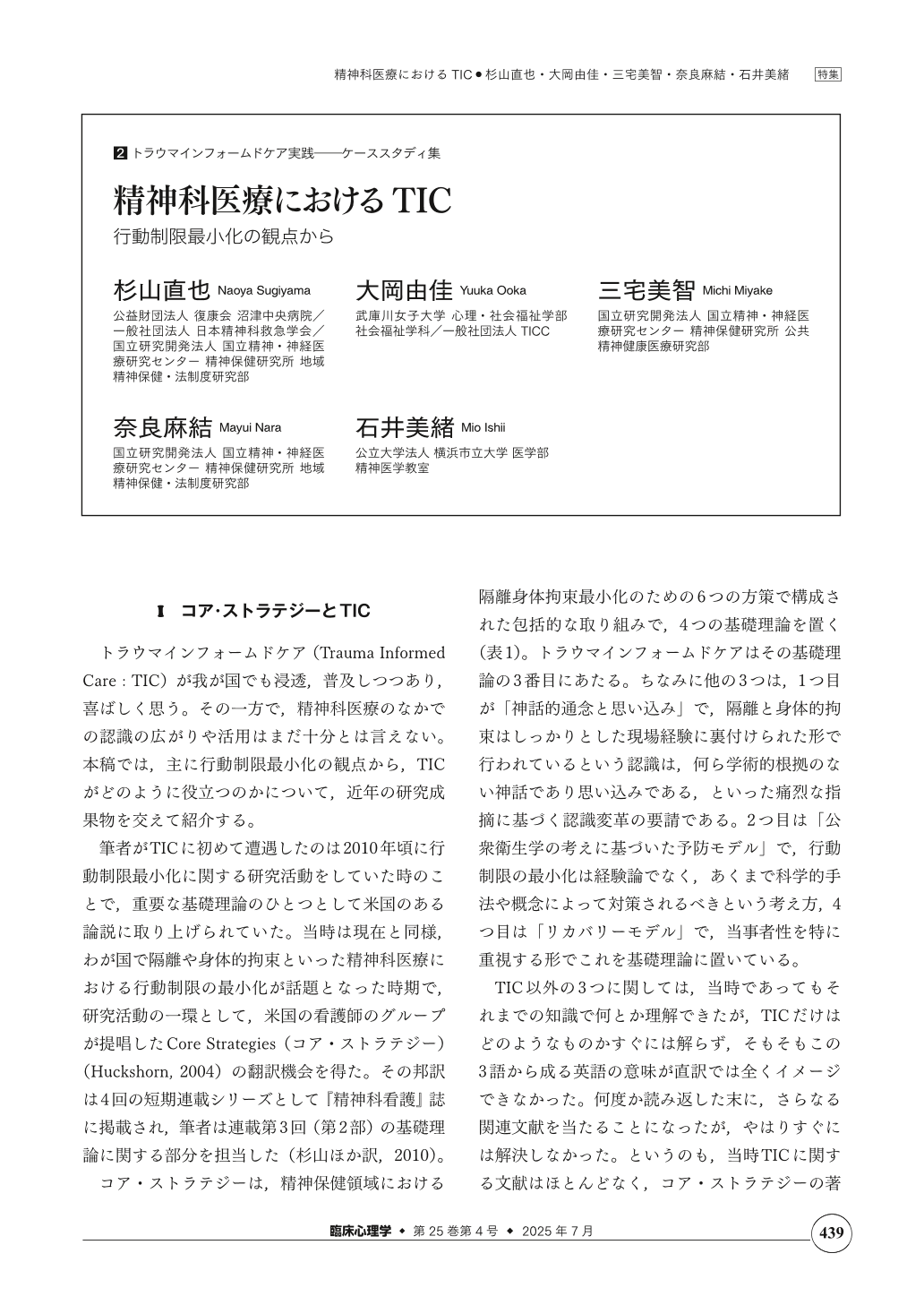
Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.


