Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
内容のポイント Q&A
Q1 生活期の中でSMDを見落とさないためには?
定期的なフォローアップと機能の評価観察が重要である.SMDは生活期で進行・顕在化することがあるため,見落とされやすい.関節可動域や疼痛,皮膚状態の定期的な観察,ADLの変化に加え,Ashworth scaleやSIAS,歩行能力等の評価により変化をとらえることが重要である.また,家族や介護者からの「最近腕が動かしづらくなっている」「足のつっぱりや疼痛を訴えることが多くなった」等の日常の違和感の聞き取りも有用である.
Q2 SMDをきたさないために日常生活で注意することは?
関節可動域を保ち,非対称性姿勢や活動の低下を避けることである.同じ姿勢での長時間保持による関節可動域制限の出現を避け,ストレッチや活動を,日課として意識的に取り入れることが重要である.また,短下肢装具や上肢の補助装置等を使用し,定期的に調整することで適切な関節可動域を保持することも必要である.生活期においても家事やセルフケアの際に麻痺側を意識的に使用しつつ,皮膚トラブルや疼痛出現時には速やかに医療機関の受診を教育することが重要である.
Q3 生活期でSMDを診断した場合どのように対応すべきか?
ADLへの影響等を考慮して薬物療法とリハビリテーション治療を計画する.筋緊張の程度をmodified Ashworth scale等で評価し,SMDによる衣服の着脱や,移乗や移動の介助量等のADLを評価する必要がある.筋緊張に対しては,ボツリヌス療法の適応を見極め,早期の介入による疼痛や共同運動,拘縮等の二次障害を緩和していく.さらに,リハビリテーション治療の必要性も検討し,外来リハビリテーション治療や介護保険等を利用した通所・訪問リハビリテーション治療の開始,必要時のカンファレンスを行う.使用している装具や福祉用具の見直しも必要である.
Q4 SMDを防止するために生活期でどのような連携が必要か?
多職種による継続的な情報共有・地域資源の活用を行う.患者自身での障害の把握は難しく,医療機関を受診すべき症状を患者に教育するだけでは不十分な場合が多い.そのため,地域との連携が重要であり,訪問リハビリテーション等でかかわる理学療法士や作業療法士,ケアマネジャー,義肢装具士,それぞれの疾患の主担当医やリハビリテーション科医との連携をとれる体制の強化が必要である.連携の中心として,装具外来やボツリヌス外来の拡充は必須である.また,「痙縮」としてとらえられることの多い「SMD」の統一化された管理を広めていく必要がある.
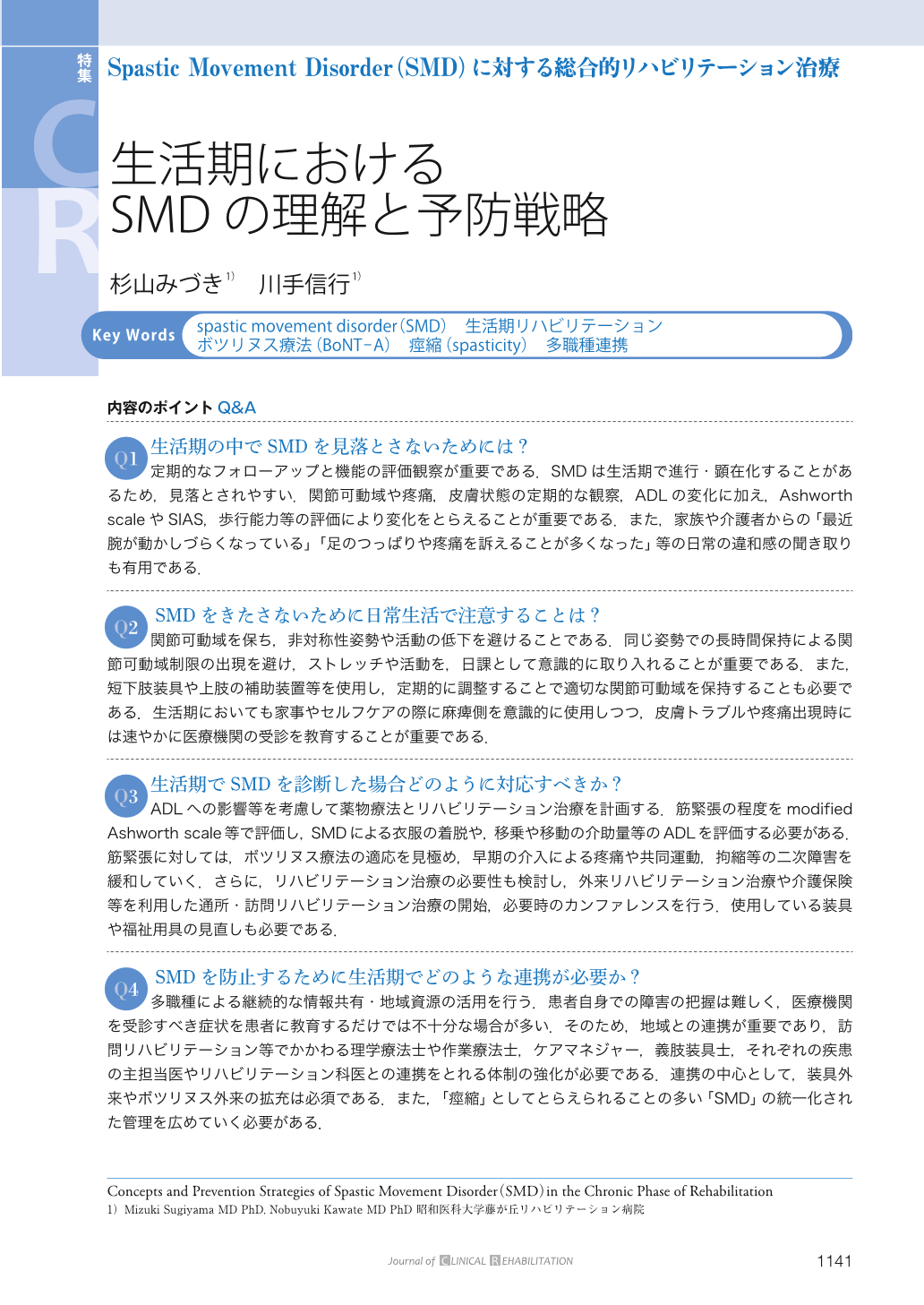
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.


