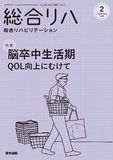Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
脳血管障害により,上下肢麻痺,痙縮,感覚障害,膀胱直腸障害,構音障害,嚥下障害,高次脳機能障害,精神障害などの障害が発生する.不動・廃用症候群の予防,日常生活動作(activities of daily living:ADL)向上や社会復帰を目的として,発症から24〜48時間以内のリハビリテーション治療の計画を立てて,病態に応じて比較的早期から介入することを「脳卒中治療ガイドライン2021」でも推奨している1).つまり,急性期から生活期を想定したリハビリテーション治療の実践が重要なのである.
急性期では不動による合併症予防が中心となり,離床やベッド周囲での基本動作訓練,ADL訓練が行われることが多く,回復期では麻痺の程度の改善に合わせた機能障害の改善,治療用補装具や自助具,治療用機器を用いてさらなる活動性の向上や環境調整を行い,生活期につなげていく.急性期・回復期から生活期にむかって,リハビリテーション治療は依存性の高い訓練内容から徐々に患者の主体性を重視する訓練内容に変化していくことが特徴である.病院内でのリハビリテーション治療は生活期のスタートを切るための治療であり,患者の主体性に基づく環境調整と運動学習理論に基づくアプローチを行う治療である(図1).
脳卒中生活期におけるリハビリテーション治療の目的はADLの自立度向上や機能維持であることが多く,生活の質(quality of life:QOL)向上につながることが多いといわれている2).一方で介護保険利用者の脳卒中患者の割合が増えている状況で,介護度の高い患者のリハビリテーション治療の目的をはっきりさせることも今後の課題である.訪問リハビリテーションでの訓練内容がリラクゼーションや関節可動域訓練といった依存性の高い訓練内容となればなるほど,生活期での主体性は減る可能性は高く,ADL向上,活動性向上を目的とするリハビリテーション治療の実践が困難となる.本稿では,生活期におけるリハビリテーション治療での主体性の重要性にふれつつ,ADLとQOLの関係,脳卒中生活期のQOL評価を解説する.
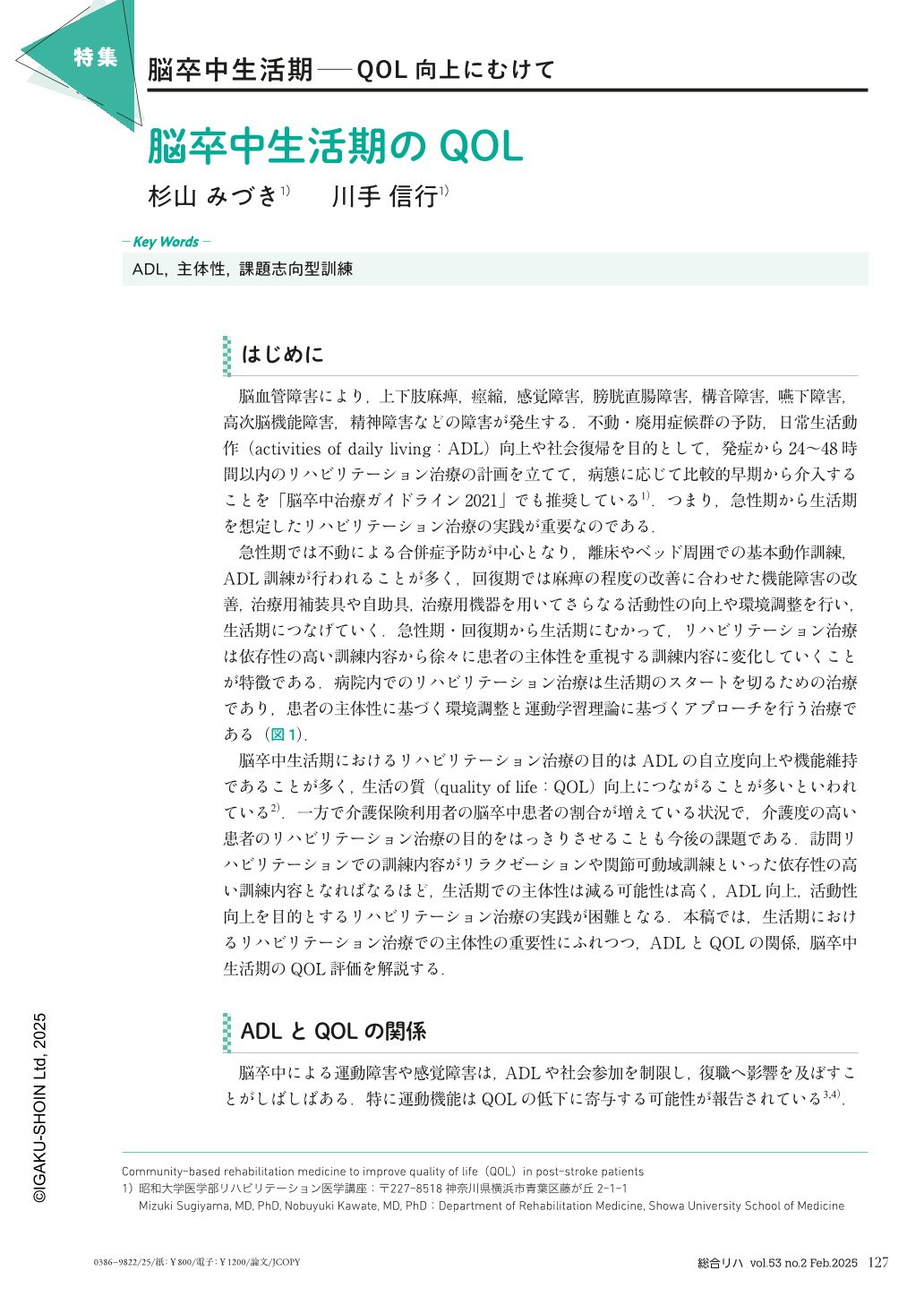
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.