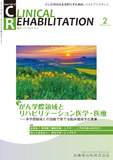- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
化学療法誘発性悪心・嘔吐(chemotherapy-induced nausea and vomiting;CINV)は,患者のQOLを低下させる代表的な有害事象であり,可能な限り予防・緩和することが必要である.CINVの制御が不十分であると,患者がつらいだけではなく,生命予後も悪化させる可能性が示唆されている 1).
抗がん剤の催吐性は薬剤によって異なる.制吐薬を全く使用せずに抗がん剤が投与された場合の投与開始から24時間以内の嘔吐発現頻度をもとに催吐性が分類されており,嘔吐発現頻度が90%を超える抗がん剤が高度催吐性抗がん剤(highly emetogenic chemotherapy;HEC)と定義されている.最も代表的なHECは1970年代に開発されたシスプラチンで,現在でもさまざまながん種のkey drugとして使用されている.制吐薬の開発は1980年頃から始まり, 常にシスプラチンレジメンを対象に開発が進められ,制吐薬が進歩した現在,シスプラチンレジメンによる嘔吐発現頻度は10%以下である.
制吐療法の代表的なガイドラインは,海外ではMASCC/ESMO,NCCN,ASCO,日本では日本癌治療学会により作成されている.オランザピンが標準制吐療法に組み込まれる以前のHECに対する標準制吐療法は,5-HT3受容体拮抗薬,NK1受容体拮抗薬,デキサメタゾンの3剤併用療法であったが,シスプラチンレジメンにおける嘔吐完全抑制(嘔吐なしかつ救済治療なし)割合は,急性期(投与開始〜24時間)が80〜90%前後,遅発期(投与開始24〜120時間)が60〜70%前後で,特に遅発期の改善が課題であった 2).
遅発期の成績を改善する新しい作用機序の制吐薬はまだ開発されておらず,本来は制吐薬ではないがCINVに効果が期待できる薬剤が非定型抗精神病薬のオランザピンで,主に米国のNavariらを筆頭にその効果が検証されてきた.
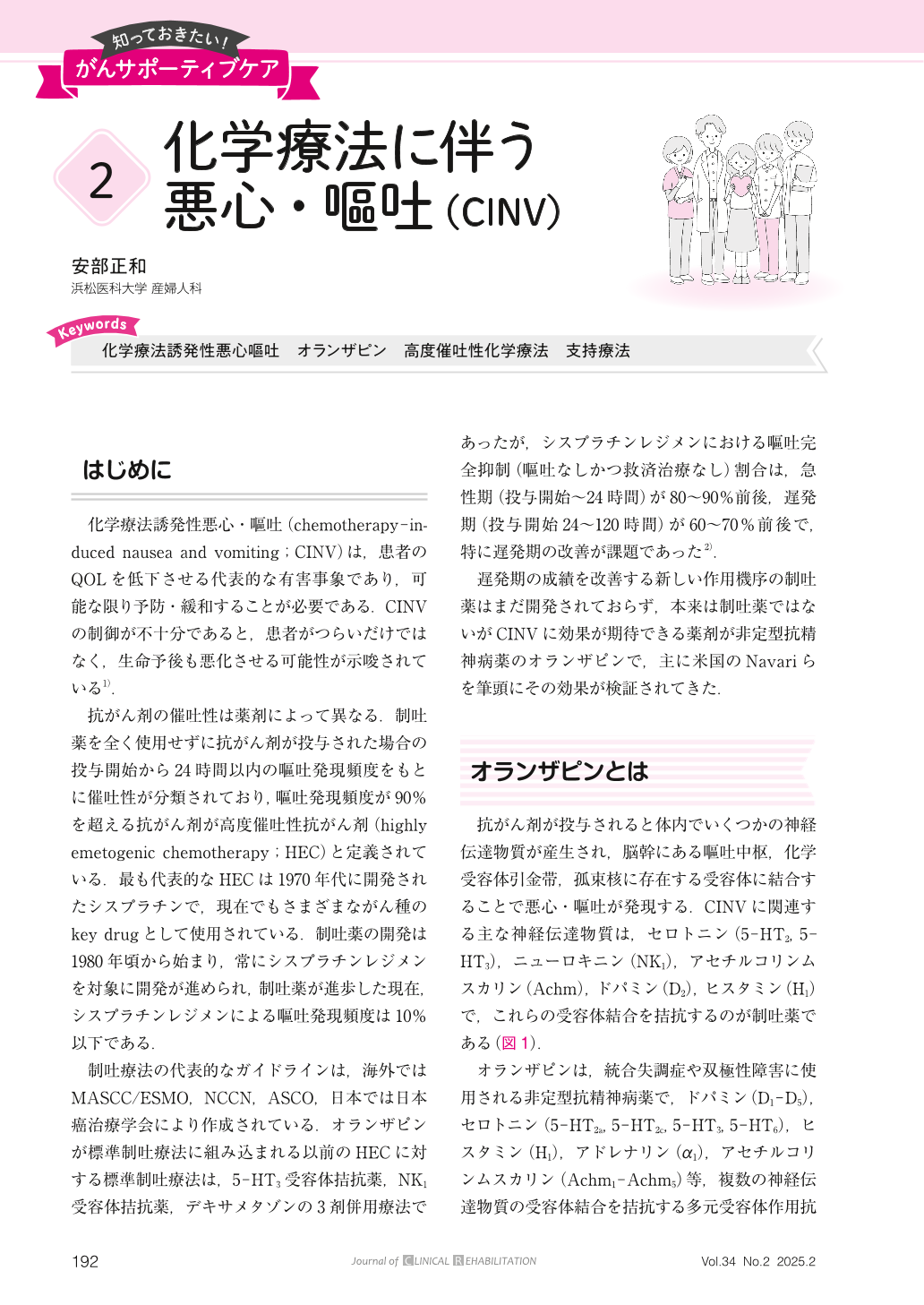
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.