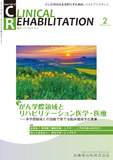リハビリテーション科医師に必要な診察,評価手技
12.摂食嚥下(水飲みテスト, RSST,VF, VEの手技, 評価のポイント)
柴田 斉子
1
,
大高 洋平
1
1藤田医科大学医学部リハビリテーション医学講座
キーワード:
摂食嚥下障害
,
評価
,
スクリーニング
,
嚥下内視鏡検査
,
嚥下造影検査
Keyword:
摂食嚥下障害
,
評価
,
スクリーニング
,
嚥下内視鏡検査
,
嚥下造影検査
pp.169-173
発行日 2025年2月25日
Published Date 2025/2/25
DOI https://doi.org/10.32118/cr034020169
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
高齢化とともに多種の疾患やフレイル等を要因として摂食嚥下障害患者数は増加している.摂食嚥下障害の罹患率は急性期総合病院では30%に達し 1),在院日数を延長させ,死亡リスクを高めるとともに,肺炎等で再入院する可能性も高いといわれている.
摂食嚥下障害は疑いをもたないとそのリスクがある患者を同定することはできない.
摂食嚥下スクリーニング検査は,摂食嚥下障害のリスクがある患者を特定するための第一歩として非常に重要で,定型的なスクリーニング検査の実施により,誤嚥性肺炎の発症率を低減できる 2).スクリーニングの結果,嚥下障害のリスクがあると同定された場合には,さらなる専門職による評価や画像検査の必要性を検討する.
喉頭侵入,誤嚥のサインは,むせ,咳払い,声質変化等であるが,これらを呈さない不顕性誤嚥の患者が20〜30%ほど存在する.ベッドサイドの臨床評価のみで不顕性誤嚥の診断を行うことは難しい.したがって,摂食嚥下障害の評価では,患者の原疾患および既往歴,内服薬の種類を把握し,摂食嚥下障害の病歴(疑わしい症状,罹患期間,経過)と患者の全身状態,血液検査,関連する画像検査の結果と併せて,嚥下スクリーニング検査を総合的に判断し,必要例には画像を用いた嚥下機能評価を実施することが重要である.評価の結果から摂食嚥下障害の重症度を判定し,直接訓練が安全に行える範囲と到達目標を決め,間接訓練を含めた治療プランを立てる.その後,訓練の進捗ごとに再評価と到達目標のアップデートを繰り返し,個々に応じた最高の到達点を目指していく.
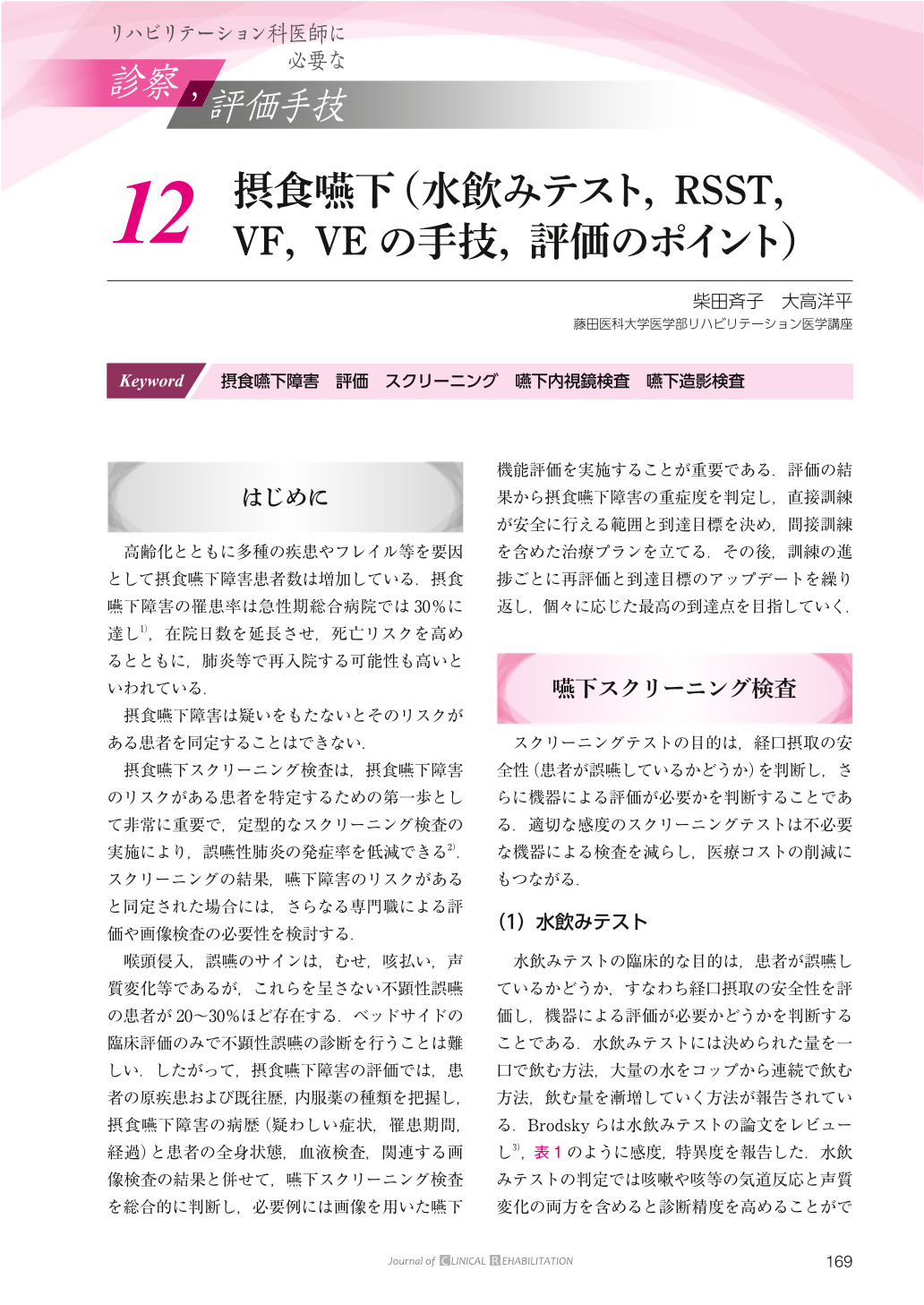
Copyright© 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All rights reserved.