- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
Case 緩和的抜管を希望する終末期COPD患者
患者Aさんは70代の男性である.10年前,労作時呼吸困難のためB市民病院を受診し,慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断され,禁煙の指導と吸入気管支拡張薬の処方を受けていた.COPDに伴う慢性呼吸不全のため,3年前から在宅酸素療法(HOT)が開始された.HOT開始後は,完全に禁煙していた.5カ月前,COPDの増悪で入院し,一時的に非侵襲的換気(NIV)を受けた.自宅に退院後,屋内の歩行でも息切れが生じるようになり,外出時には車いすを使用していた.趣味だった庭いじりもせず,入浴とリハビリテーションのために週2回デイサービスに行く以外は,日中は寝室でテレビを観てすごすようになった.B市民病院の近く(自家用車で10分程度)に在住であること,家族の付き添いで受診に支障がなかったことから,訪問診療は依頼せず,B市民病院への通院を継続していた.適切な栄養管理を受けていたが,1カ月前の外来受診時には身長170cm,体重42kgであった.
入院の3日前に発熱と湿性咳嗽が出現し,さらに呼吸困難が増悪したため,緊急入院した.肺炎の合併による呼吸不全の悪化であった.入院時,CO2ナルコーシスのため意識障害を伴っていた.付き添った妻に確認のうえ,気管挿管し,人工呼吸管理が開始された.PaCO2の改善とともに意識は清明となり,その後は現在まで,鎮静せずに人工呼吸管理が可能な状態である.意思疎通が可能となった後から,本人は筆談やジェスチャーで人工呼吸器中止の希望を繰り返し伝えるようになった.入院10日目までに肺炎は軽快したが,人工呼吸器に依存した状態が続いている.診療科のカンファレンスの検討で,人工呼吸器からの離脱は困難と考えられている.主治医はAさんに,永続的に人工呼吸管理が必要なこと,人工呼吸器を取り外せば数時間から数日以内に亡くなると考えられること,気管切開を行えばより楽に人工呼吸管理を受けられること,人工呼吸器を使用しての自宅療養も可能であることを懇切に説明したが,本人からは気管切開への不同意の意向が示され,あらためて人工呼吸管理の中止の希望が表明された.挿管チューブのほか,末梢輸液,経管栄養のための経鼻移管,モニター類が装着されているが,自己抜去するそぶりは見られず,身体的拘束はされていない.精神科医の診察では,抑うつや希死念慮はないとのことであった.
Aさんは大学を卒業後,地元のB市役所(B市民病院に隣接している)に事務職員として採用され,定年まで勤務していた.20代で市役所の同僚と結婚し,妻も定年まで市役所で働いていた.息子が2人おり,近所に在住である.孫は3人いる.妻によれば家族関係は良好であり,実際,妻も息子も頻回に面会に訪れている.現在は特別療養環境室料(いわゆる差額ベッド代)のかかる個室に入院しており,経済的な問題はなさそうである.
今回の入院後,主治医は病棟看護師とともに,妻および息子2人と3回面談している.そのうち1回は本人のベッドサイドだった.妻によると,Aさんは前回の入院中のNIVがつらかったと述懐しており,NIVも含めて人工呼吸器の装着はしたくないとたびたび話していたとのことであった.前回の退院後,大学の人事によって元の主治医が異動になったこともあり,本人も妻も新しい主治医に人工呼吸器についての意向を言い出すことができなかったのだという.今回の入院時には,本人の呼吸が苦しそうで,また,意識が低下していくのを見て,妻は動揺してしまい,救急外来で担当医に「できることはなんでもしてください」と伝えてしまったと後悔していた.妻も息子2人も,Aさんのことを心配してはいるが,精神状態は安定しているように見え,主治医の説明をよく理解できている.そして,本人が望む通りに,気管チューブを抜去して人工呼吸器を中止してほしいと希望していた.他方,もし本人が気管切開と人工呼吸管理の継続を受け入れるのであれば,家族も協力して自宅での療養を支えるとのことであった.
主治医,病棟看護師,ソーシャルワーカー,担当理学療法士,病棟薬剤師が参加し,Aさんの医療・ケアの方針をめぐりカンファレンスを開催した.本人の意向に従い抜管して人工呼吸器を中止するべきだと考えるスタッフもある一方で,人工呼吸器の中止によってAさんが亡くなった場合の法的懸念を表明するスタッフもおり,合意形成はできなかった.
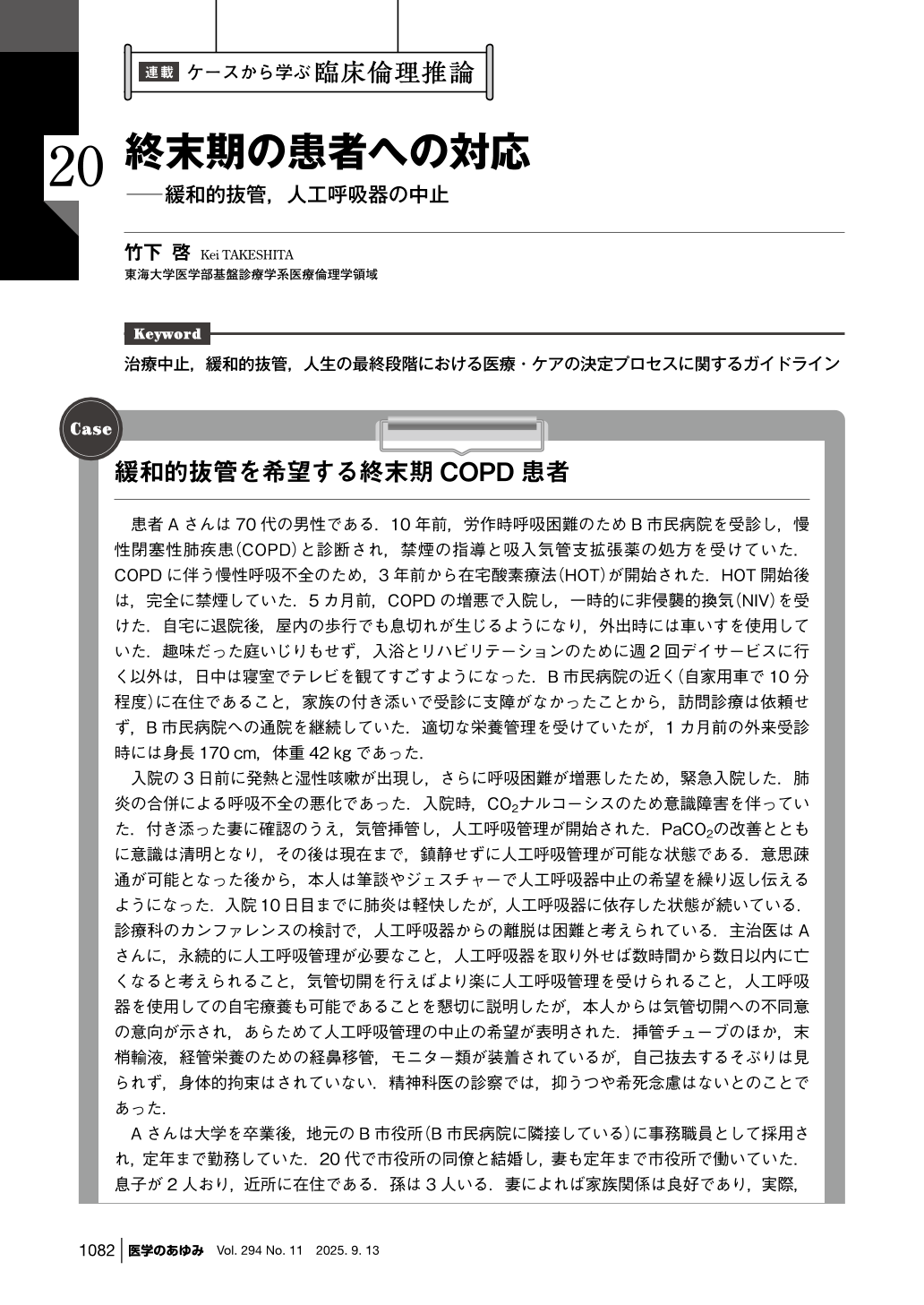
Copyright © 2025 Ishiyaku Pub,Inc. All Rights Reserved.


