- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
世界で本格的ながん治療が始まったのは産業革命期以降,がんが職業病として注目されてからといわれている。19世紀に麻酔の進歩により手術が普及し,やがてX線が発見されて放射線治療も行われるようになった。1940年代,第二次世界大戦中に使用された化学兵器のナイトロジェンマスタードが殺細胞性抗がん薬として発見されたことをきっかけに,抗がん薬の研究が進んだことはよく知られている。一部の白血病や固形腫瘍に効果を発揮する抗がん薬が開発されるようになると,そこから約半世紀の間,小児がん診療にかかわる医療者の関心は,外科手術や放射線,次々に開発される抗がん薬,造血細胞移植などをいかに組み合わせれば治療成績が向上するか(このような統合的な治療を「集学的治療」という)に注がれ,数々の治療研究が行われてきた。その甲斐があって,たとえば遠い昔には輸血をしながらただ見守ることしかできなかった小児急性リンパ性白血病も約90%に寛解が期待できるようになり,そのほかの小児がんも合わせ全体として約80%の子どもたちが病を乗り越えて大人になっていく時代となった1,2)。治療中の急性毒性については比較的早い時期から関心が寄せられていたとされているが,小児がんの長期生存者が増加するに従い,医療者は患者が過去の治療に起因したさまざま困難に遭遇することに気づいた。集学的治療は,恐ろしい病から子どもたちの生命を救う一方で,彼らの心身を密かに傷つけていたのである。これは圧倒的な症例数を有する成人のがん治療後の経過観察においては想像しにくいものであった。なぜならこの問題が成長・発達という小児特有の生物学的特徴に関連づいたものだったからである。ようやく小児がんの子どもたちの「晩期合併症」,つまり“治療を終了したがん経験者に認められる疾患自体の侵襲および治療によると考えられる直接的・間接的な合併症”に関心が寄せられるようになり,これら治療毒性に関する大きな会議が米国国立がん研究所(National Cancer Institute:NCI)の主催によって初めて開かれたのは1975年のことであった。この年,Giulio J D’Angio博士は小児がんの展望に関する論文に“cure is not enough”と記した3)。小児腫瘍学の究極のゴールはがんを克服した子どもたちを健康面だけでなく,心理社会的にも経済的にも守ることであり,近年の小児がんの治療研究には,これまで押し上げてきた治療成績を落とさずに,いかに治療後の長い長い人生を歩む子どもたちのQOL(quality of life)を低下させないことができるか,も重要な達成項目の一つに掲げられるようになった。
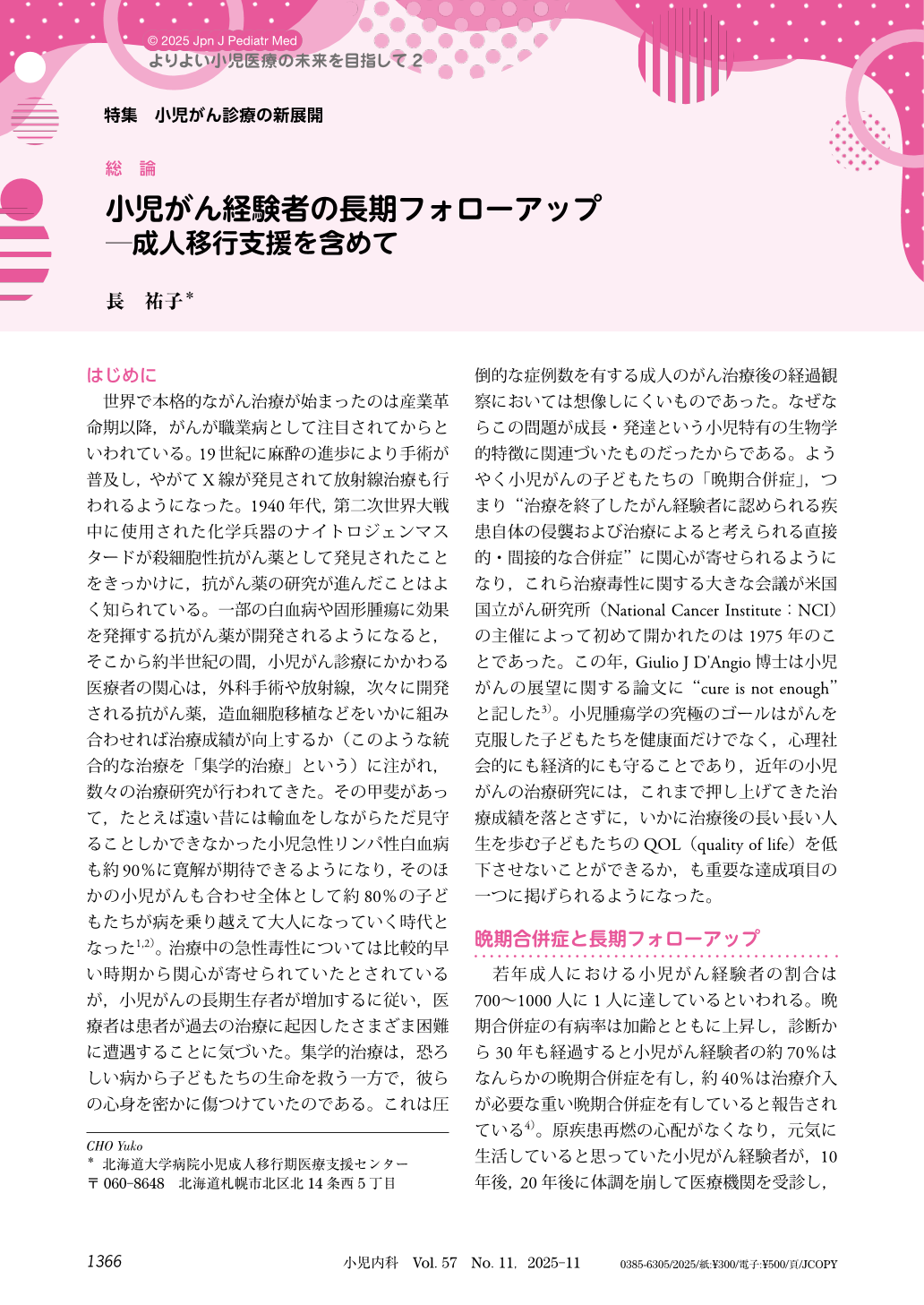
© tokyo-igakusha.co.jp. All right reserved.


