- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
ヒトパピローマウイルス(HPV)検査は子宮頸がん,特に前がん病変の検出感度の高い画期的な検査法であり,子宮頸がん検診に欠かせない診断ツールである。しかしながら胃型腺がんをはじめ,腺がんでの陽性率が低く,浸潤がん全体でも20~30%弱が偽陰性となる点や,検査キット間で検出感度に差があるなど,いくつかの課題も指摘されている。また,最近のフィンランドのランダム化比較試験では「5年ごとのHPV検査」と「5年ごとの細胞診」とで子宮頸がん発生率・死亡率に有意差はみられず,HPV単独検診の優位性が確認されなかった。また,日本は英国や北欧諸国とは異なり,子宮頸がんの罹患率・死亡率の減少がみられておらず,組織型検診体制も未整備である。加えて,受診者登録制度,Call/Recall制度も不十分であり,精度管理体制が整っていない。こうした国情に鑑み,多くの産婦人科医会会員はHPV単独による検診,特に5年ごとの長い検診間隔に大きな懸念を抱いている。
一方で,近年増加傾向が著しい卵巣がん,子宮体がんへの対策も急務であり,これらに対するスクリーニング法として経腟超音波の導入が望まれる。北海道では子宮頸がん検診と併せて経腟超音波検査を同時に実施する体制を整備し,早期卵巣がんの発見に成功している。このような包括的な婦人科がん検診体制の構築が可能となった背景には,現行の2年ごとの子宮頸がん検診体制の存在がある。「5年ごとのHPV単独検診」が主流となれば,このような検診体制の継続・発展は極めて困難となる。日本の女性を守るためには子宮頸がんのみならず,卵巣がん,子宮体がんの早期発見も目指すべきであり,そのためにも現行の2年に1度の受診機会を堅持する必要がある。
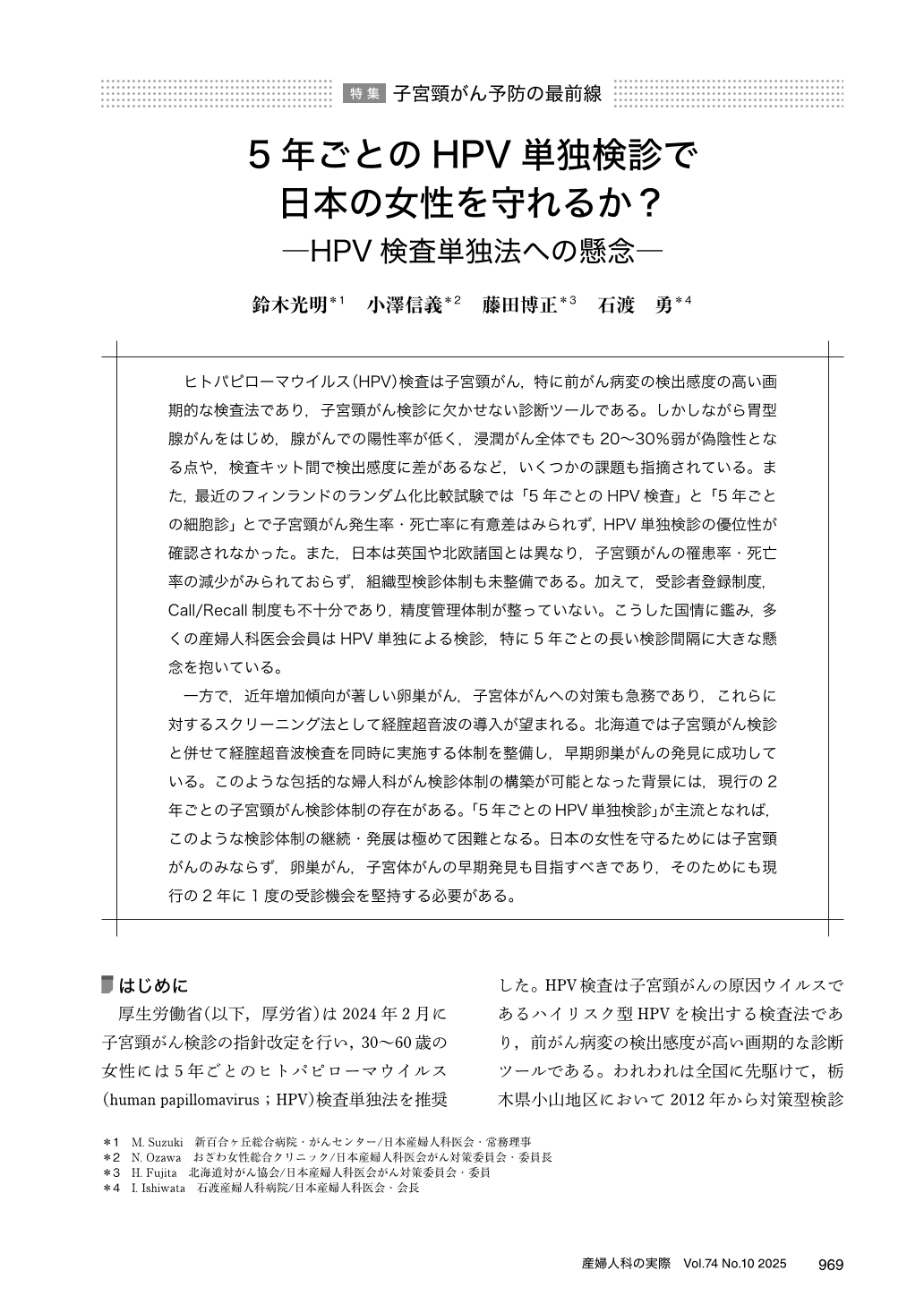
Copyright © 2025, KANEHARA SHUPPAN Co.LTD. All rights reserved.


