- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
近年,がん診療における重要なインフォームドコンセント(informed consent:IC)の場面において看護師や臨床心理士などの同席が全国的に推進されており,当院でもIC同席指針が策定され,積極的に看護師がIC場面に同席し,看護支援を行っている.筆者は「がん看護外来」の活動として,がん告知や治療方針に関するIC場面へ同席を行っており,がん患者や家族の治療や療養に関する意思決定の支援を,日々試行錯誤しながら行っている.
がんの診断初期に,患者や家族はがんという重大な診断への心理的衝撃を受けながらも,治療の意思決定を行うことになる.がん治療は副作用や侵襲を伴い,時に治療は長期にわたる.このため患者や家族は仕事などの社会生活の変更を余儀なくされ,家族の介護や養育を担っている場合には委譲を考えなければならないこともある.この点で,がん治療の意思決定を支援するためには,患者や家族の生活背景を理解することも大切になる.
意思決定について角田1)は「問題解決力や判断力,価値観など実に多くの要因が絡み,様々な思考や行動を必要とするため,かなりの意思力を使う」と述べている.意思決定のために患者や家族は,医師の説明を理解するだけでなく,生活や価値観と照らし合わせてどの選択肢がよりよいかを吟味したり,治療や療養のために生活を変容させたり,意向を医療者へ適切に表明する必要があり,複雑な思考力や行動力,コミュニケーション能力が必要ということがわかる.よって意思決定支援の具体策は,医療的な理解を促進したり,生活や価値観と選択肢のリスクベネフィットを照らし合わせる支援をしたり,療養生活をサポートする資源を紹介したり,ICの場で表明を支援することなどがあげられる.医師は医学的観点から治療のリスクベネフィットに関して患者とコミュニケーションをとる.しかし,患者や家族を生活視点でとらえ,価値観に合わせて共に選択肢を吟味することは,限られた診療の時間のなかでむずかしいのではないだろうか.ここに,看護師が同席し連携して意思決定を支援する必要性と専門性があると考える.
今回,家族の介護を理由に治療の開始を先延ばしにしている患者とかかわるなかで,治療の意思決定にかかわる患者の社会的な背景や複雑な思いを知る機会を得た.この事例を報告し,皆さんと一緒に意思決定支援について改めて考えたい.
なお,事例については個人情報保護の観点から,一部の情報を加工して掲載する.
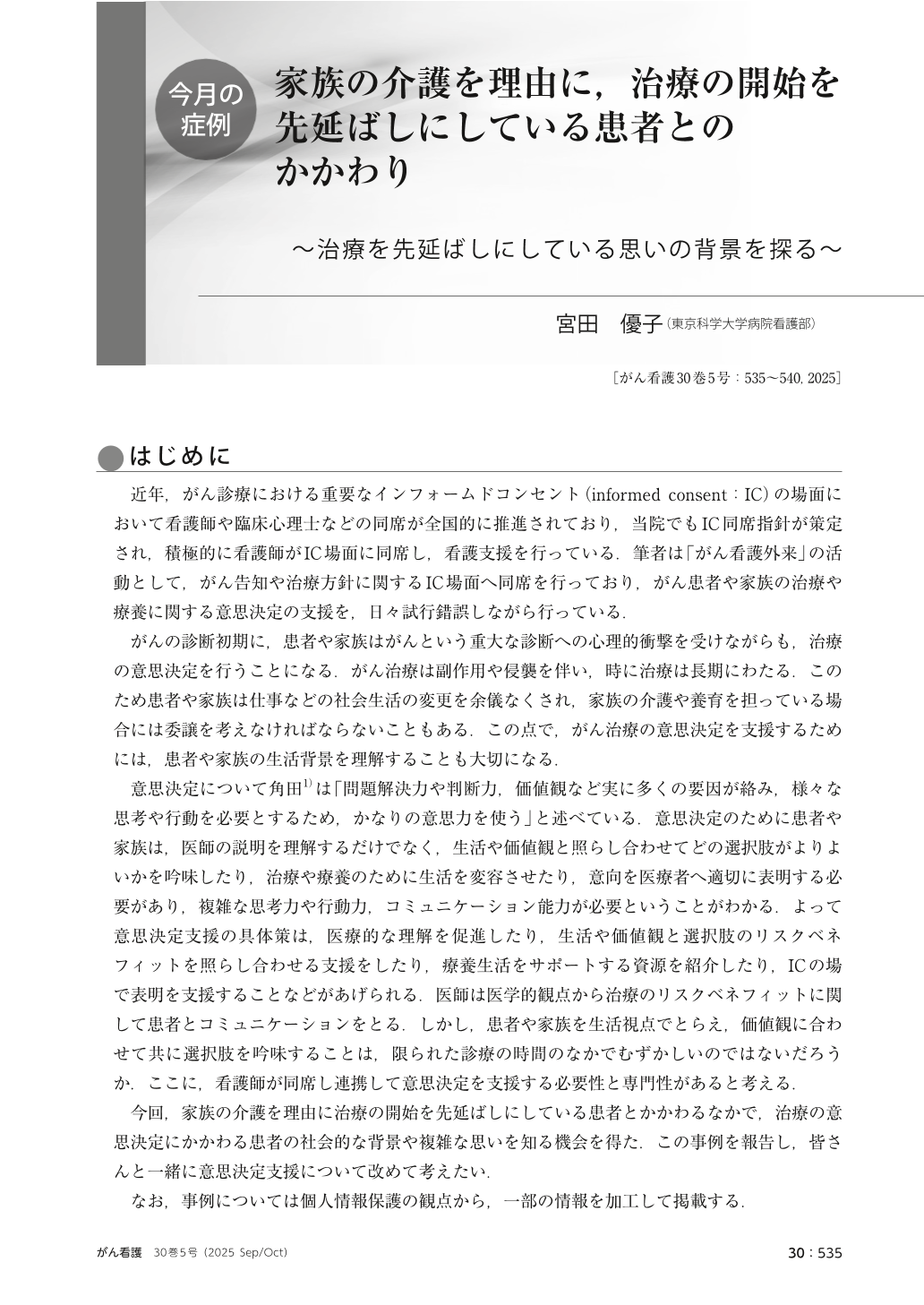
© Nankodo Co., Ltd., 2025


