- 販売していません
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
介護予防を目的とした運動機能向上は,介護保険法と同時に実施されている介護予防事業をさらに,効果的なものにしていくために2006年の改正介護保険法の中でその位置づけがより明確にされたものである.この背景には,要介護高齢者中でも軽度要介護高齢者の急増があり,急激な増加を抑制する効果,またこれまで整備が遅れてきた軽度要介護者に特異的な自立支援をより明確にしたサービスを体系化することが期待されている.
ところで,筆者が介護予防をすすめる動機となったのは,昨今の医療制度改革に対する専門職としての抗いである.介護保険導入にあたって,年金・医療・福祉の社会保障費を従来の5:4:1から5:3:2に変更すべく施策が誘導されている.つまり,医療の枠を4から3へとすべく,医療の対象の限定が行われている.この誘導の影響を最も大きく受けているのは,長期的な療養を必要とするリハビリテーション(以下,リハ)の対象者である.具体的にはエビデンスベースドメディシンという耳あたりの良い言葉で修飾されたDiagnosticrelated group and prospective payment system(DRG/PPS)の導入や,治療の日数制限などがそれである.これらの改正はいかにも理不尽である.
そもそも,エビデンスベースドメディシンとは,医療の対象の限定やマネージドケアのためにあるのではなく,Sackett DL1)が「個々の患者のケアについての意思決定の場で現在ある最良の根拠を良心的に,明らかに理解した上で慎重に用いること」と近年定義したように,専門職が専門職としての当然あるべき姿を指し示したに過ぎない.さらにSackett DLは科学で証明されないものを排除するものではない,医学の持つ芸術的な側面も等しく重要であると,エビデンスベースドメディシンの制約を明確に述べている.
ふりかえって,リハの対象者の性質を考えてみれば,その中心は“障害”であり,そもそも機能的には修復不可能なものを内在している.端的にいえば,治らないという明確なエビデンスがあるということになる.譲って,機能ではなくQOLは修復可能だとしても,QOLを改善する道筋は多くあり,それを現在の科学で証明していくのには,単純な傷の治療と比較すれば数段の難しさが存在していることは容易に想像できる.治らないにもかかわらず,それがリハ医学として成立してきたのは,機能と能力,さらにはQOLは独立したものであるという概念や(これを覆すエビデンスは多いことはもとより承知である),たとえこれが間違っていたとしても,社会が変化することによって障害は,障害でなくなることを社会が理解し,医学の延長線上でこれを実現することを求めたからに他ならない.しかし,これを高齢社会を背景とした社会保障費の増大を押しとどめるために,いとも簡単に放棄してしまうのはいささか寂しすぎる.
とはいえ,高齢者人口が全人口の20%を超え,さらに老年化指数(65歳以上人口/15歳未満人口)が118%2)を超え,後期高齢者の著しい増加が予想される状況下では,現状のサービスを続けることの社会的負担は,何らかの手だてを講ずることなくしては抱えきれないほど増大することも事実である.こうした急速な高齢社会を明るく力のあるものにするために,柴田ら3)は,1)能力の維持の延長,2)高齢者間の相互扶助の推進,3)社会保障費利用の効率化の3つの方略があるとしている.現在のリハ医療のおかれている現状は3)の中で議論されているものであるが,対応はそればかりではく1)や2)へ対するリハ医学の寄与も等しく重要であり,またこの分野におけるコミュニティーベースリハを含むこれまでの蓄積を応用する余地は多く残されている.
死亡率は社会が豊かになることによって,限界寿命に向かって多くの人が生を全うする確率が高くなり,限界寿命に到達すると急激に死が訪れる,いわゆる死亡率の四角化が観察された.同様に健康寿命も延伸できることは十分期待できる.すなわち社会保障費の利用の効率化議論の前提となっている,高齢者が増えると要介護者が増えるというのは必ずしも正しくないことを示す.Vitaら4)は,大学卒業生の長期間にわたる追跡調査によって,健康的な生活習慣を持っているものは,長寿でありかつ不健康寿命が短いという実証データを示している.介護予防などの高齢期の自立した生活を維持するための積極的な取り組みを推進することによって,生活の自立も限界寿命の寸前まで保つことが期待できるのである.ただしPPK(ぴんぴん生きてコロリと死ぬ)に表される健康至上主義的な価値観を肯定するものではない.望ましくは元気に生きるとしても,要介護状態となって生きることも等しく価値があるといえる社会的な余裕を生むための取り組みなのである.
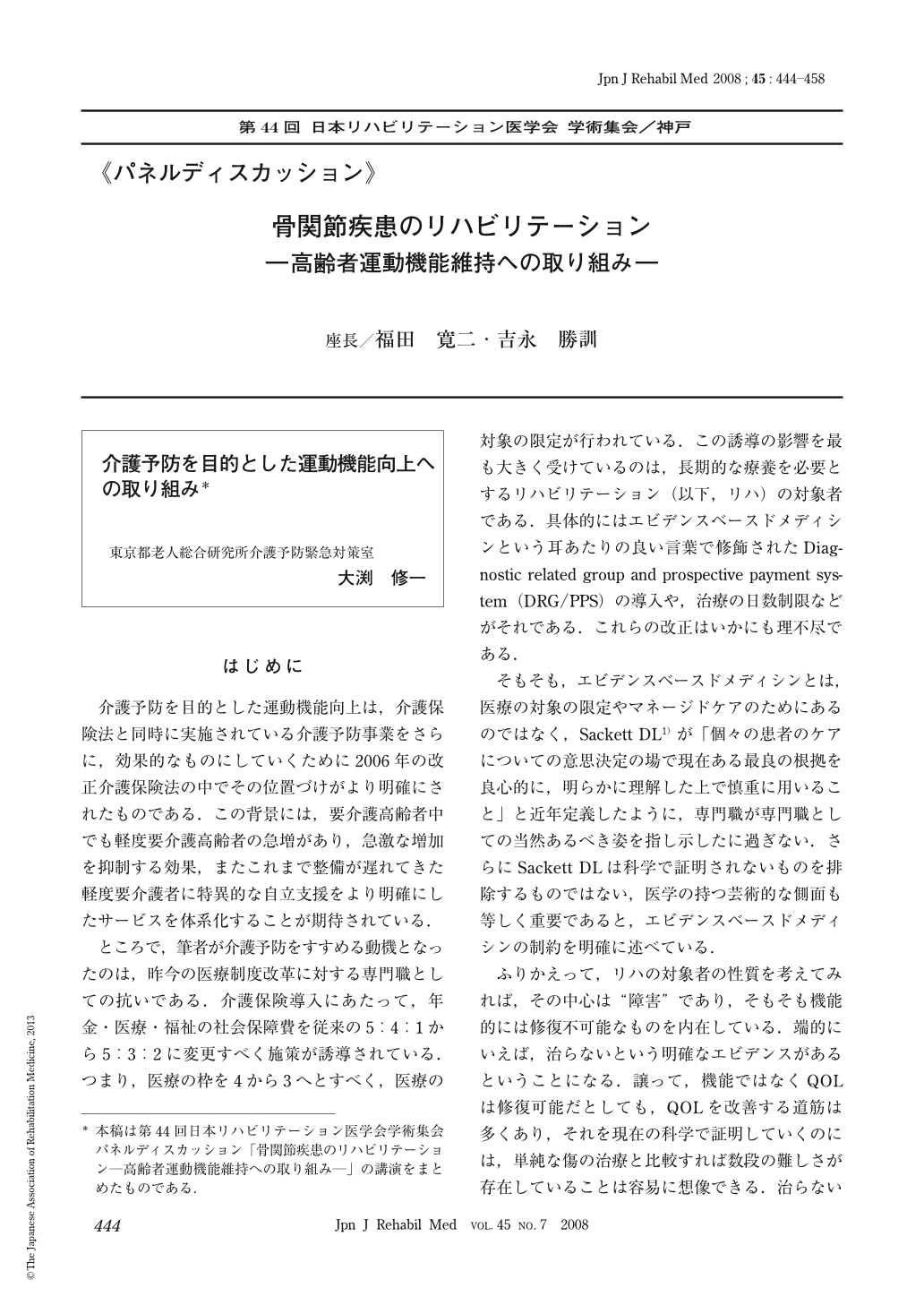
Copyright © 2008, The Japanese Association of Rehabilitation Medicine. All rights reserved.


