- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
1960年代から80年代にかけて,筋生物学が生物学全体をリードしていた時代があった。その動きは,1980年代終わりのH. Weintraub博士らによる筋分化制御因子であるMyoDファミリーの発見とL. Kunkel博士らによる遺伝性筋疾患の代表であるDuchenne型筋ジストロフィー(DMD)の原因遺伝子(DMD/ジストロフィン遺伝子)の発見時に頂点を極めたといえる。前者の背景としては,1982年「筋発生の細胞生物学」の冒頭で岡田節人博士が正しく指摘されたように,試験管内での培養技術および分化のマーカーが最初に確立されたのが筋細胞であったことを挙げることができるだろう。後者の背景としては,80年代後半に分子遺伝子の爆発的な進歩があり,筋ジストロフィーの代表的な病型について,原因遺伝子を追究することがその格好の課題となった。また,この時期を契機として極めて多くのnon-MD/PhDが筋ジストロフィーの研究分野に参入したことも特筆される。
例えば,骨格筋を構成している最も重要な分子であるミオシンについても,ウイルス感染のレセプターであることが明らかにされるなど,最近はnon-muscle cellでの役割が注目されている。それでは筋研究はどのように現代の生物学に貢献できるのだろうか。その一つは幹細胞の研究分野であり,もう一つは筋疾患に関する治療研究分野であろう。前者の例として非筋細胞への強制発現により筋細胞への変換が可能なMyoD遺伝子の発見はiPS細胞研究の先駆けとなっていた例を挙げることができる。後者の例として,DMDを主たる対象として開発が進められてきたアンチセンス核酸(AO)を用いたエクソンスキップ治療がある。最近,AOはDMDの治療のみでなく,脊髄性筋萎縮症(SMA)に対するexon inclusion治療,筋強直性ジストロフィーに対するprotein displacement therapy,さらには筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療にも応用されようとしている。
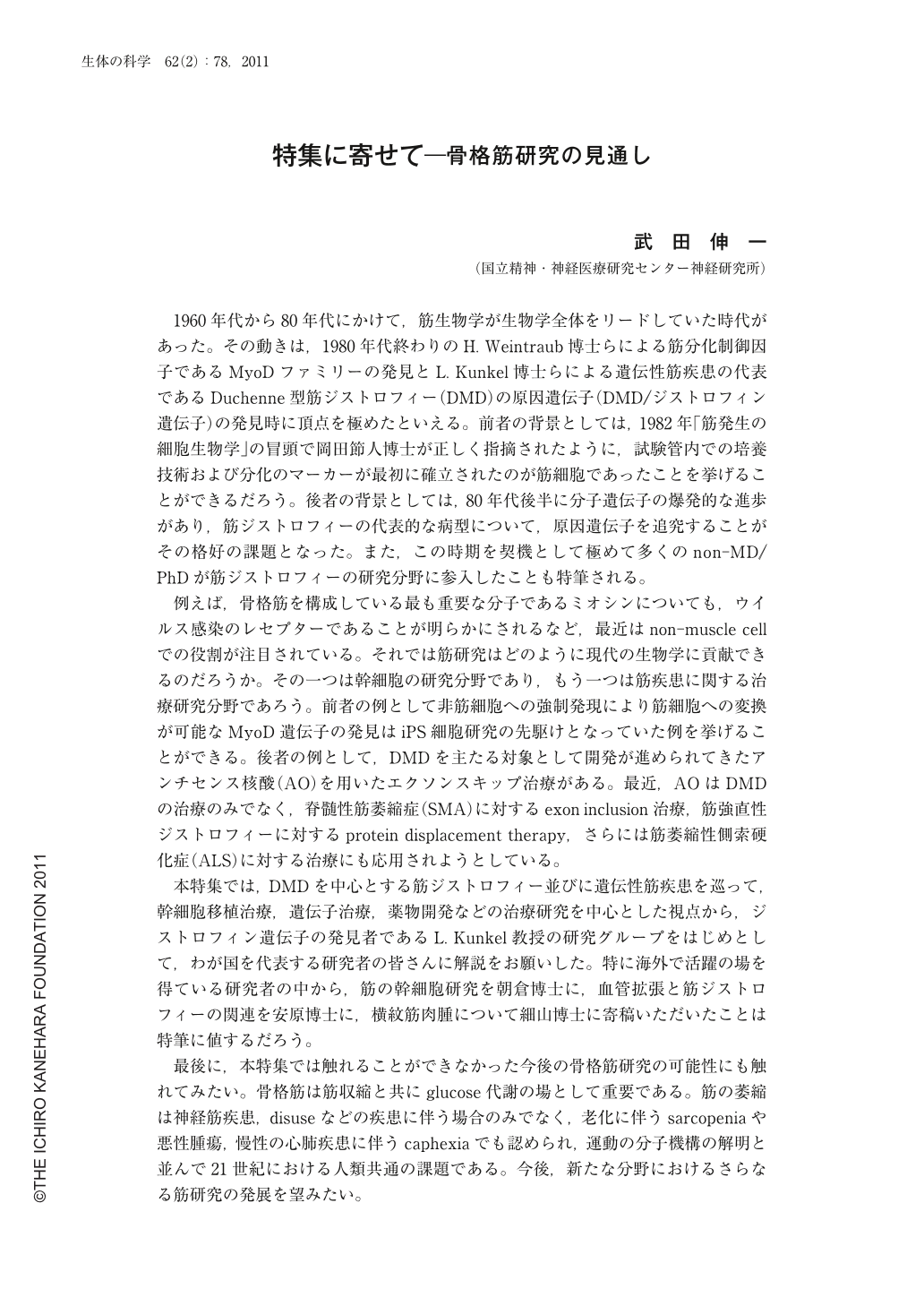
Copyright © 2011, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


