- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
免疫学は「二度無し」(同じ感染症に二度かかることは少ない)の原理を説明するための学問として発展してきたが,その興味の主な対象は,特定の抗原に対する特異的な反応としての免疫,すなわち,適応免疫反応に関するものであった。事実,免疫学とノーベル賞との関わりを見ると,このことがよくわかる。免疫学が学問として広く認められたのは,1901年にEmil von Behringがジフテリアに対する血清療法でノーベル生理学・医学賞を受賞して以来であり,以後,免疫学の分野では幾多のノーベル賞が出ているが,いずれも抗原や抗体(あるいは抗原レセプター)に関するものであり,適応免疫機構に関する研究に関するものが主であった。たとえば,1908年のPaul Ehrlichの側鎖説(免疫細胞の表面には抗原レセプターが存在するという仮説),1930年のKarl Landsteinerの血液型の発見(赤血球に対する凝集素〔=抗体〕の発見),1960年のMacfarlane BurnetとPeter Medawarの免疫寛容の研究(自己,非自己の区別,および自己抗原,自己抗体という概念の提唱),1980年のBaruj Benacerraf,Jean Dausset,George SnellのMHCの研究(免疫細胞の反応性を遺伝的に規定する分子群の発見),1984年のNiels Jerne,Georges Köhler,Cesar Milsteinによるクローン選択説とモノクローナル抗体,1987年の利根川進による抗体の多様性生成機構に関する研究,1996年のRolf ZinkernagelとPeter DohertyによるT細胞のMHC拘束性に関する研究は,いずれも,免疫系がどのようにして抗原特異的に反応を行い,それがどのように制御されるのか,という適応免疫機構に関わるものであった。
しかし,1990年代後半に一連のToll様受容体(Toll-like receptor:TLR)が発見され,引き続いてTLRの作用機序が明らかにされたことから,免疫学の考え方が大きく変わり,これまで非特異的免疫としてしか注目されてこなかった自然免疫の役割が大きくクローズアップされることになった。そして,自然免疫反応が適応免疫反応の始動に大きな役割を果たし,自然免疫と適応免疫の両者が相まって働くことにより初めて有効な免疫反応が始まり,感染防御が可能になることが明らかになったのである。
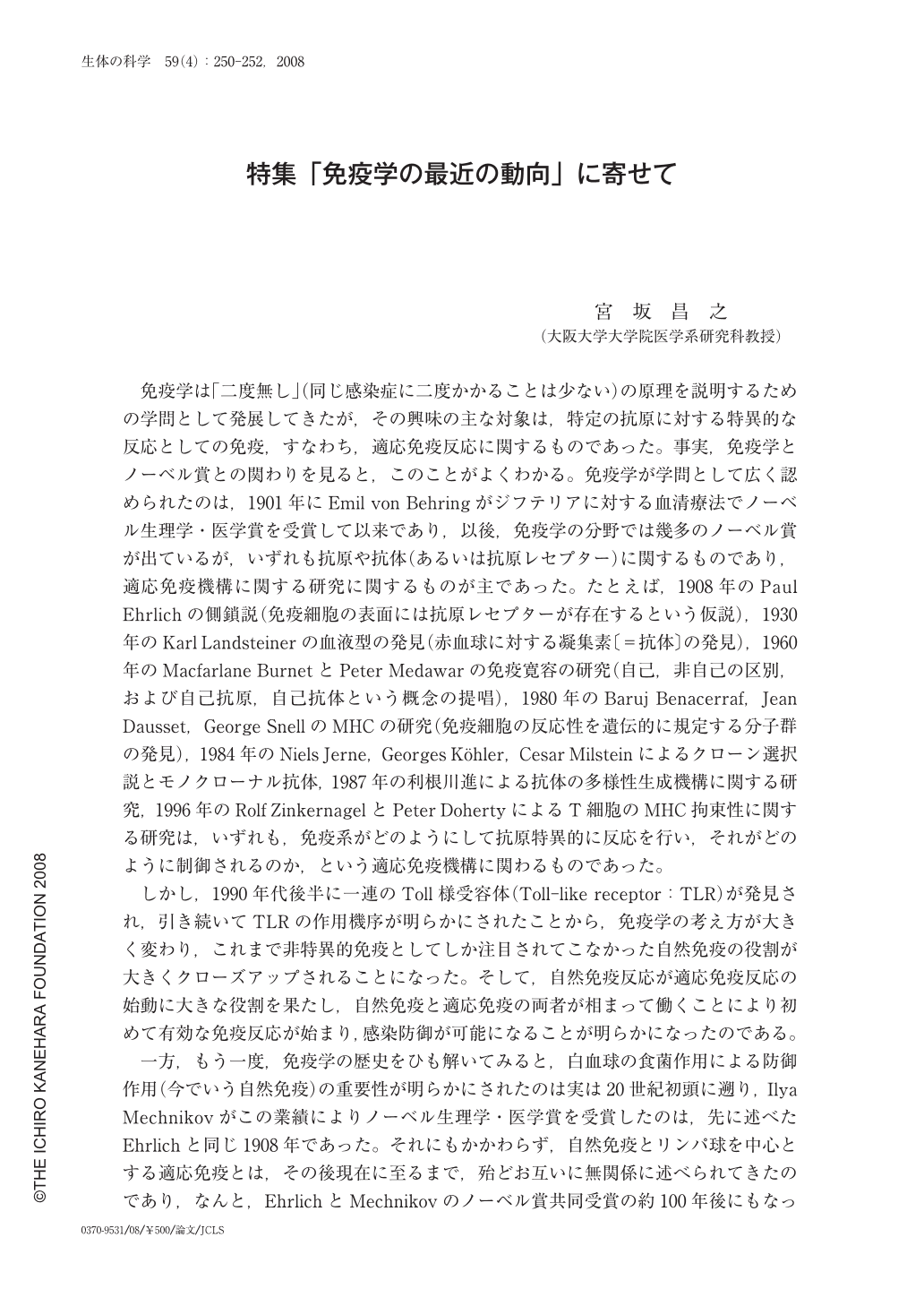
Copyright © 2008, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


