- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
古典的免疫学では,免疫反応を外来よりある生体に入りこんだ"異物"にたいする防衛機転の現われであると理解し,公理のごとくに教えられてきたが,生体が自己の構成成分にたいして免疫反応を起こす,いわゆる自己免疫疾患や血液型のキメラの存在が知られるようになつた1950年の後半ごろから,かかる公理にようやく疑問が起こり,自己識別の機構の解明が免疫学の基本問題として取りあげられるに至り,近代免疫学が大きく動きだしたといえよう。
具体的には,1960年Nobel医学生理学賞を受けたMedawarやBurnetらの理論的あるいは実験的な業績によつて代表される。個体は発生分化のある過程以前から,自己の構成成分(自己抗原)としからざるものを免疫学的に認識する能力があり,この認識は生体の免疫担当細胞(immunolo-gically competent cell)の機能に依存するということである。かかる見地から,古典免疫学の立場からは不可解であつたキメラ,免疫学的寛容,自己免疫疾患などの成立の機構の解明にアプローチする基盤ができたわけである。最近の免疫学は,免疫担当細胞を根幹として,きわめて広範に枝葉がのびつつある過程にあるといえる。基礎的には免疫担当細胞自体の性質の解析,成熟後の免疫学的寛容の誘導法,胸腺の役割,抗原情報をいかにして免疫担当細胞が受けとるのか,allogeneicinhibitionとは何か,臨床的には予想をはるかに上回る腎臓移植の成功例に刺激されて,同種移植免疫反応の解明,制癌剤の副作用を逆用しての免疫反応の抑制,さらには自己免疫疾患の解明,治療,癌の基礎および臨床両面からの免疫学的検索などと,はてしなく分野が拡大している。
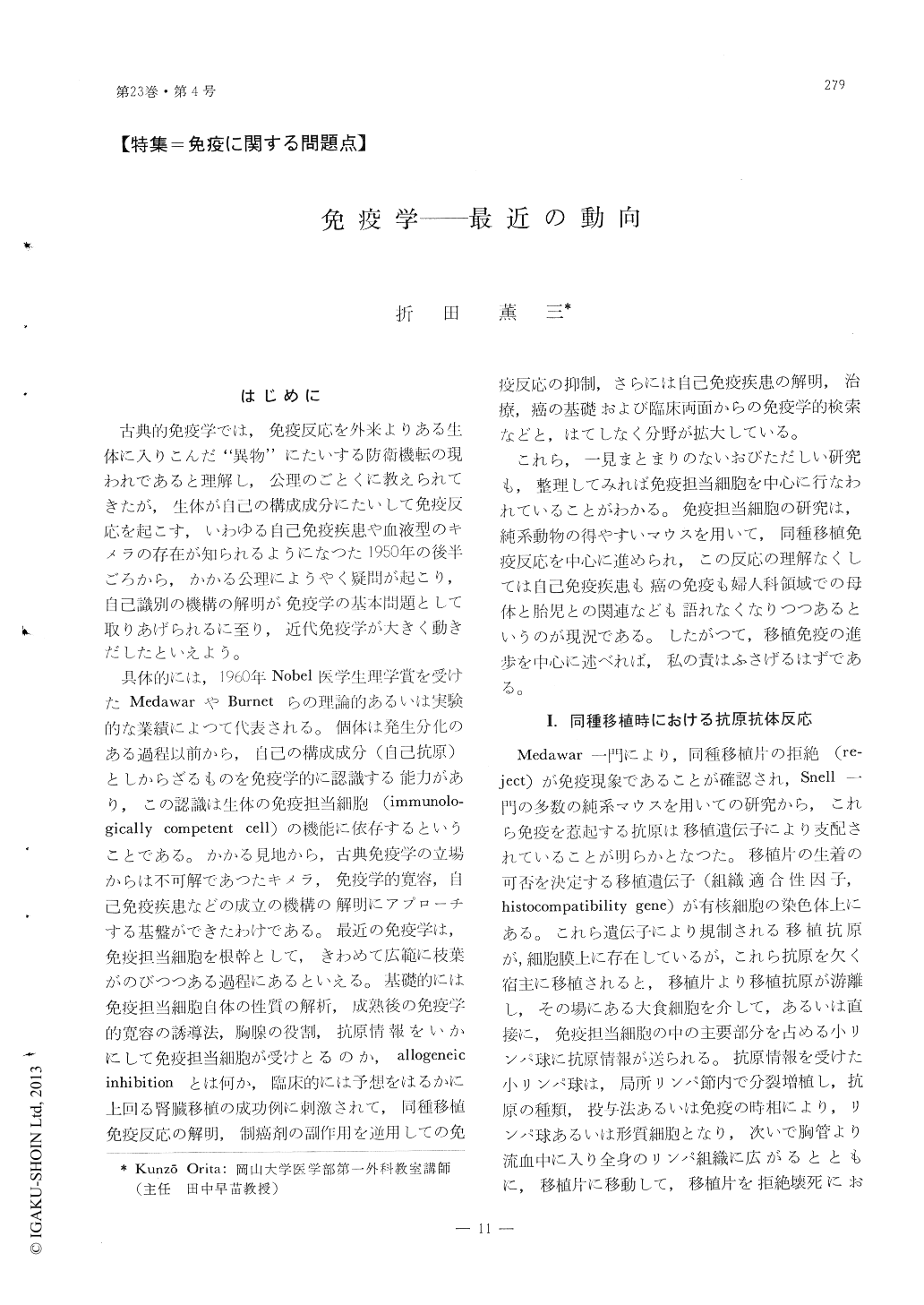
Copyright © 1969, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


