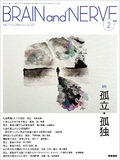- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
脳と心の問題は,古くて新しい問題である。哲学的な議論も含めれば大昔のギリシャ哲学のアリストテレスが「全体は部分の総和以上である(The whole is greater than the sum of its parts.)」と捉えたことからもわかるように,科学の進歩,特に脳科学の進歩により,遺伝子,分子,細胞,ネットワークを分析的に解明してきていても,全体から生まれる心の問題はハードプロブレムである。歴史的には,それらを総合したり,分析したりという2つの動きが常にあり,心の理解に関する理論を展開してきた。
そのような観点から,ウィリアム・ジェイムズ氏(William James; 1842-1910)の『心理学原理』(The Principles of Psychology)を取り上げたい1)(Fig. 1)。当時,脳科学はまだ黎明期以前ではあるが,脳科学への言及も一部含まれている。ジェイムズの,意識を思考の流れ(stream of thought)として捉え,意識の連続性と時間性を流れとして理解する視点は,現代でも通じる考え方である。その点でもう1つの原著としては神経哲学者ゲオルク・ノルトフ氏(Georg Northoff; 1963-)の近著『意識と時間と脳の波—脳はいかに世界とつながるのか』(Neurowaves: Brain, Time, and Consciousness)2,3)を取り上げたい(Fig. 2)。意識と時間の関係にさらに,脳活動の中に計測される多数の波を含めて意識の連続性や時間との関連を論じているのは,当時の問題提起が現代においても依然として課題であり続けている1つのよい例であろう。
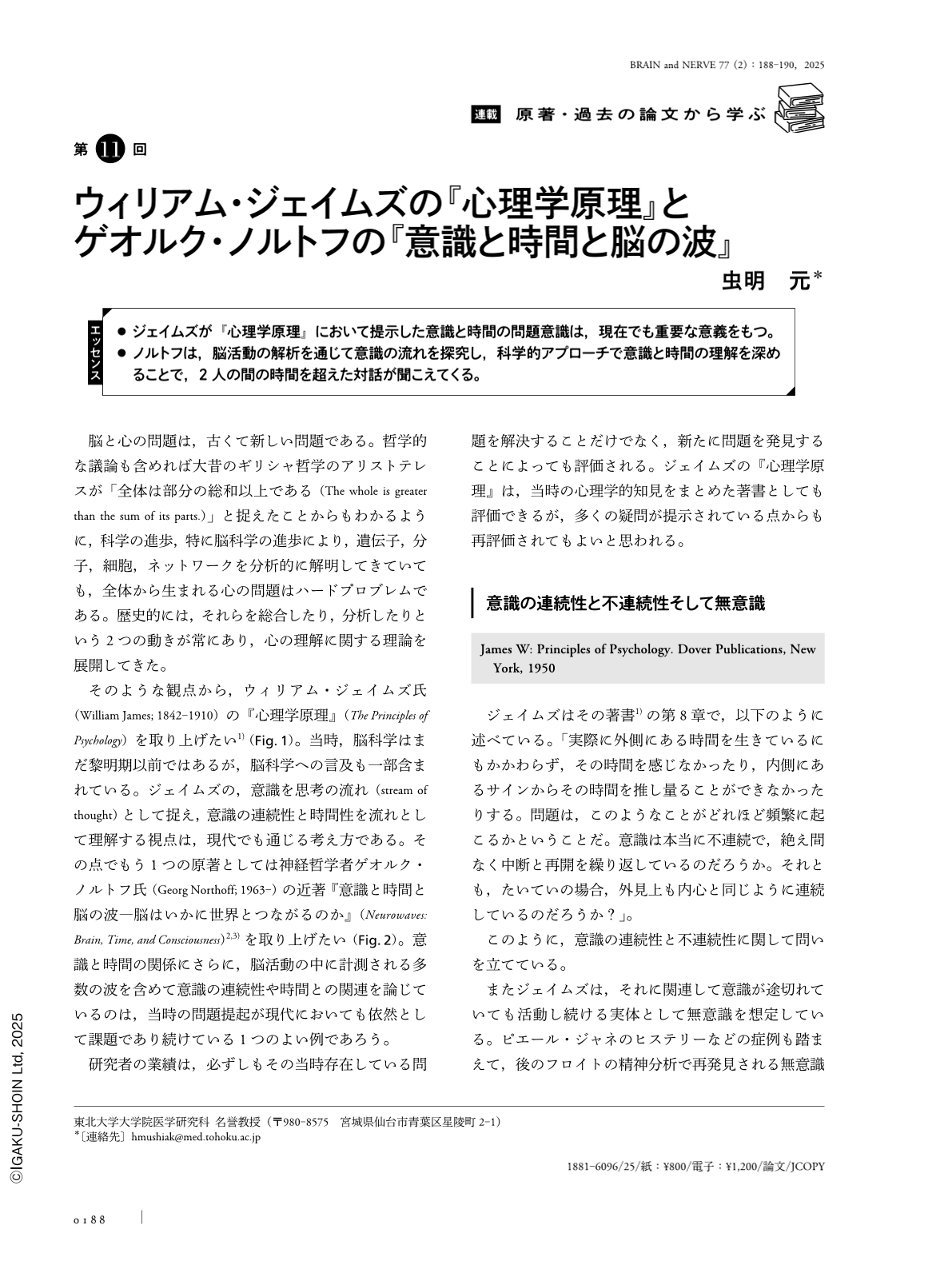
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.