- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
- サイト内被引用
はじめに
突然の受傷により遷延性意識障害となった患者は,これまでに習得した能力や生活,そして思い描いていた未来への希望を一気に失う。自らの感情表出や活動が困難となり,常に他人の援助を必要とする生活となる。一方,家族の毎日は,時に深い悲しみや絶望感,怒り,受け止められない現実を伴ったまま過ぎていく。このような患者や家族に対して,看護職は役に立ちたいと感じながらも,患者を前にすると生活援助や合併症予防の援助にとどまり,家族を前にすると家族からの期待にプレッシャーを感じ,踏み込んだ援助を実践できない状況にある。
筆者がこれまで病棟でかかわり,意識障害から脱却した患者は,「ボクハイッショウコノオリ(ベッド)ノナカデイキテイク」(筆談),「(意識がないと思われている時期の医療職者の声掛けに対し)大人として扱ってほしかった」(筆談)といった患者の耐えがたい悲しみや思いを表出していた。先行研究において,患者の思いを基盤に意識障害看護の特質を明らかにした報告はほとんどない。病棟看護師の立場からは,佐々木,佐々木(2014)が「意識障害看護を20年経験した看護師でさえ,患者に行う行為が,本当に患者が望んでいるのかと悩んだり,変化のない患者に対して虚しさを感じる」など,患者とのかかわりにおいて看護職が直面する困難な状況を指摘している。
一方,家族は筆者に,リハビリテーション(以下,リハビリ)に対する期待や,「病院で死なせてあげたほうが本人は楽だったのかな」「障害者手帳の申請にどうしても踏み切れない」など,意識障害が遷延する患者と向き合う苦しみや障害受容への葛藤について話していた。このような家族の苦悩に関し,石田(2008)は,家族が「子どもの状態に対し“受け入れの気持ち”と“否認”の気持ちの間で揺れていること」「子どもの体調や,周囲の環境によって容易に揺らぎやすい状態にあること」等を明らかにしている。
本稿で紹介する筆者の研究は,遷延性意識障害者の家族の“気がかり”にアプローチし,入院経験を通して今後の生活に家族が希望を見つけ,患者本人とともに,よりいきいきと生きていくために,入院期間註1に,看護としてどのような援助ができるのかを明らかにすることを目的に,3年間取り組んだものである。
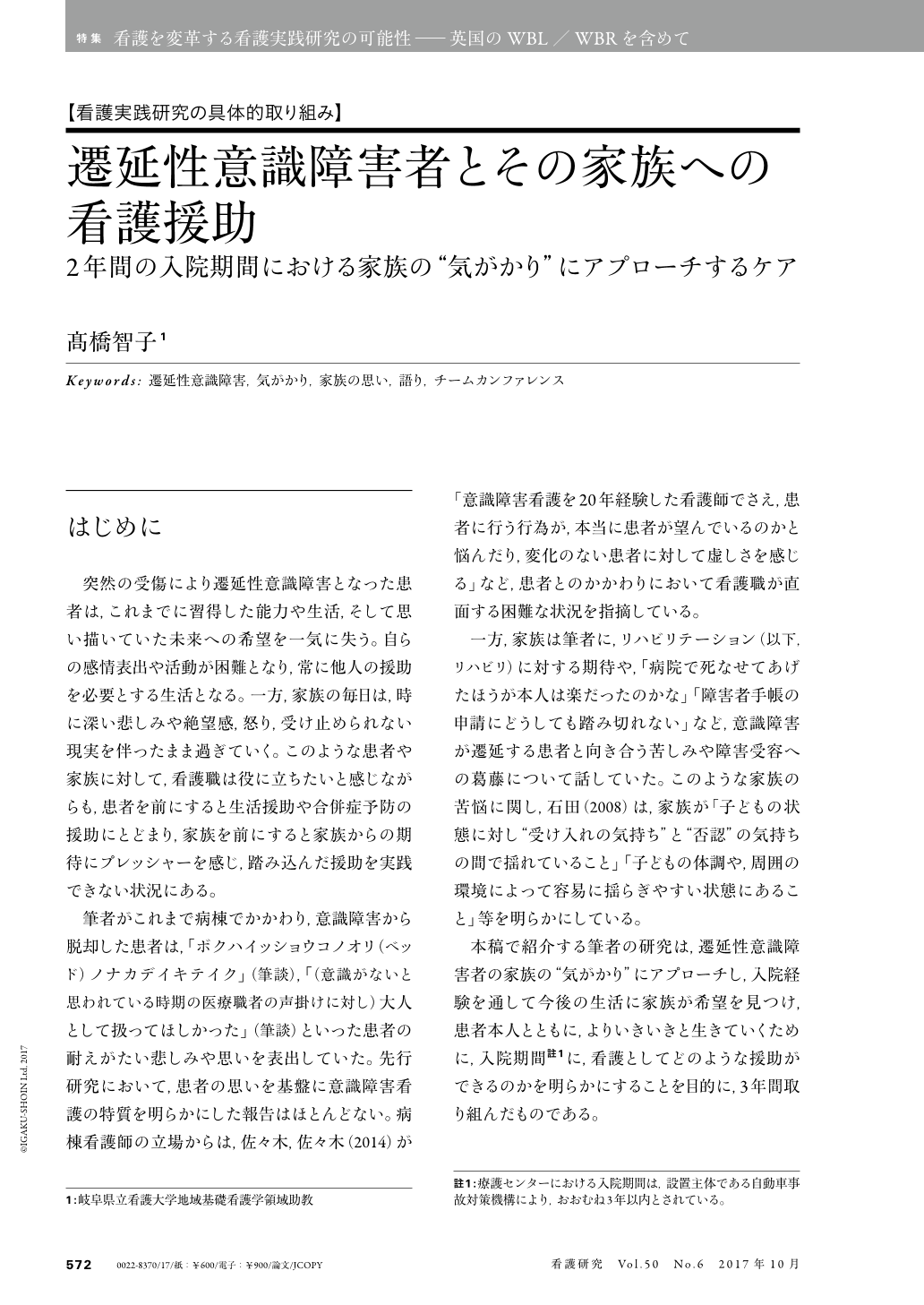
Copyright © 2017, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


