編集デスク・11
川端康成の目
長谷川 泉
pp.453
発行日 1961年9月1日
Published Date 1961/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663904077
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
川端康成に「末期の眼」というエッセイがある。およそ川端康成論が書かれる際に,誰でもとりあげざるを得ない凄絶な文である。川端自身は,自分が語られる際に,いつでも「末期の眼」が引き合いに出されるのはいやだと言っているが,論者にとっては,川端康成を論ずる場合に,川端の本質をとらえ,それを語るに,この文を逸することはできないから,川端が好もうが,嫌おうが,おかまいなしに,引用せざるを得ない文である。
孤児として人となった川端は芸術家の血は病み弱められており,消えゆく残燭が,いまわの際に燃え上がったのが芸術家の生命だと信ずることを述べている。これはすでに悲劇であり,芸術家は一代にしてできるものではないことを語っている。川端康成という,亜流を許さぬ芸術家も,そのようにして生み出されたものであろう。康成はもの心つく前に父母を失い,一人の姉をも早く失い,祖母を失い,祖父の手で育てられた。そのような天涯の孤児の感情が,川端文学の本質には流れている。それは,すでに亜流というものの存在を許さぬ環境である。
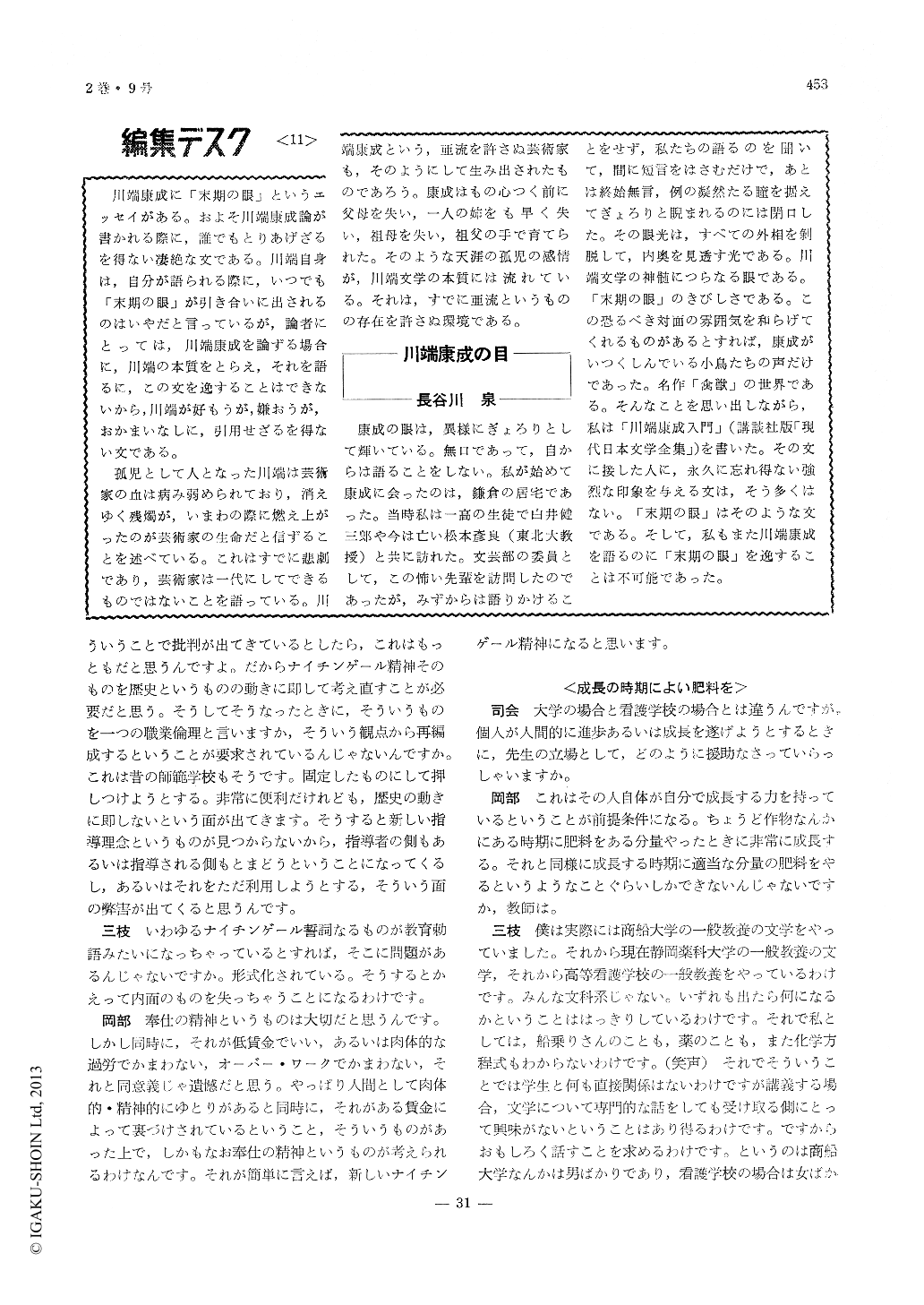
Copyright © 1961, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


