連載 ジェンダーの視点から地域・生活を考える・5
漁師町の民間信仰—シンボルとしての不浄と豊饒
中山 まき子
1
1鳴門教育大学
pp.410-413
発行日 1996年5月10日
Published Date 1996/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901363
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
「あそこの家は,嫁がソバエトル(妊娠している)さかい,よーけー漁があるー」「大漁でもよ,ワガ(自分)の力を過信したらいかん。きょうの大漁はワガに幸せがあった,そういうことよ」。漁師町で調査をしていると,人々の語りの中にこうした“人知を越えた力の存在に対する認識”がよく現われる。
かつて艪の船で漁をしていた時代,漁師という職業は,日毎に変わる天候,風向き,潮の流れなどの自然界を相手とし,「板子一枚下は地獄」と表現されるほど危険と背中あわせだった。そして船にハイテク機器が搭載され始めた今でも,操業中の事故や怪我,あるいは一命を亡くす出来事もなくならない。そのため彼らは,生活の中で実に多くの神がみを大切に守り,信心深く,また迷信や日常生活の中での決まりごとも多い。
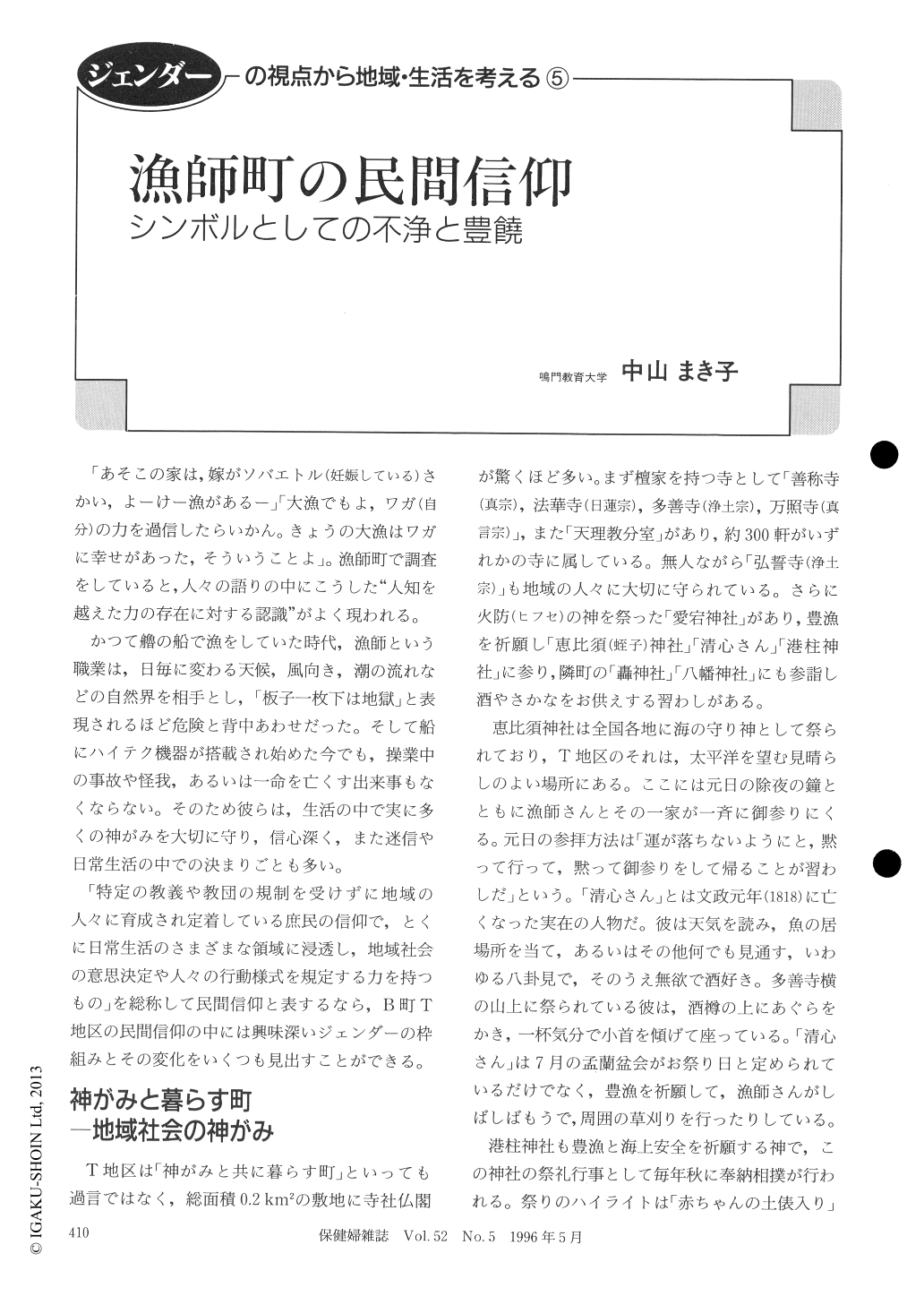
Copyright © 1996, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


