特集 家庭で死を迎える
患者の居場所は家庭であった
宮田 良子
1
,
牧 満子
1
1埼玉県立がんセンター
pp.609-613
発行日 1979年6月1日
Published Date 1979/6/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661918695
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
人間にとって,死はだれにでも確実にやってくる.そしてその臨終の時を,自分の思う人に囲まれ,生まれ育った温かい家で迎えられたら,それは最上の喜びであろうと思われる.当センターの内科病棟には,治ゆの望みのない,末期癌患者が多い.小康状態を保っている時に,一時的にも家庭での生活を勧めることが多いが,大抵の場合,患者はともかく家人は病院にいることを望む.そのような現実の中にあって,畳の上で家人に看取られて死を迎えたいという素朴な願いを持つ患者に出会うことがある.
時には涙を浮かべて,たとえ生命が短くなろうとも,自宅で配偶者や子供,孫に囲まれ,余生を送りたいと訴える老人もいる.家庭に帰ることが死期を早める結果になると自覚していても,あえてそれを希望する場合がある.患者にとって,病院でどんなに高度な医療や手厚い看護をうけても,家人の愛に囲まれて生活することにまさる幸せはないと思われる。核家族化が進み,女性の有職者が増加している現在,病人を家庭で世話することの難しさが問題になっている.患者のそうした希望は心情的に理解できても,それを実現化するのが困難な現状である.
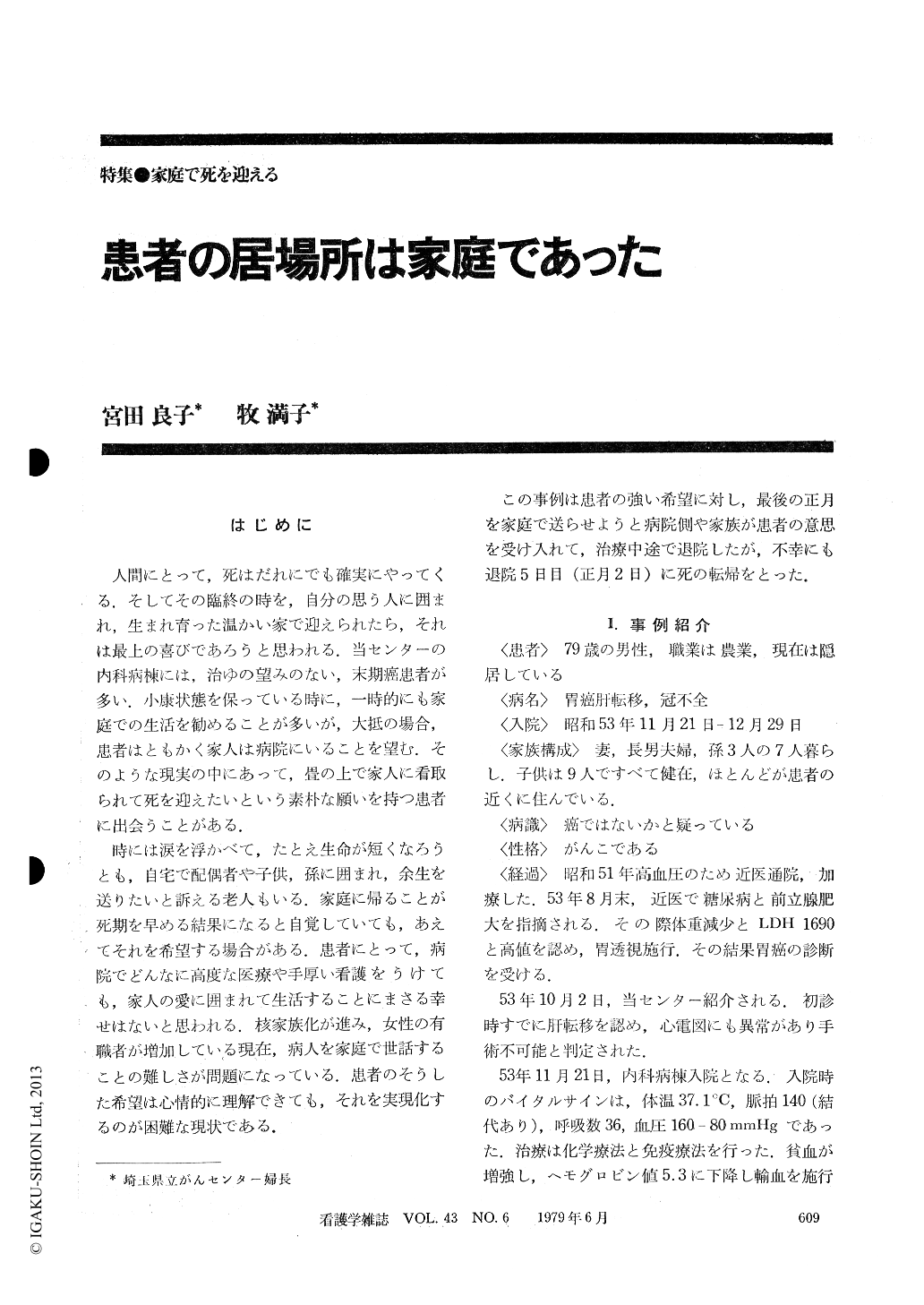
Copyright © 1979, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


