発行日 1949年8月15日
Published Date 1949/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906508
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
10年結核の床にあつた正岡子規は,世界にも稀らしい病床文學をいくつか殘している。子規の俳句も短歌も小説も,ひつきよう病床文學といえば言えないことも無いであろうが,私のいうのは病牀六尺,墨汁一滴,仰臥漫録など一連の病床隨筆を指すのである。その中でも病床六尺は,死の2日前まで,遂には目ら筆をとることも叶わず,口述筆記で辛うじて筆をついで新聞「日本」に發表して行つたものであり,然も彼自身,毎朝新聞を開いてみて,この稿の載つていない日は生きている氣がしないと言つたほど,その全精力を打込んだものであつて,餘りにも苦痛激しく口述に堪えない日は,たゞ,「人間の苦痛は餘程極度へまで想像せられるが,しかしそんなに極度に迄想像した樣な苦痛が自分の此身の上に來るとは一寸想像せられぬ事である」とのみ,2行を記すにとゞまった。それでも彼は筆を絶とうとはしなかつた。文學の鬼とは彼のことである。
その「病牀六尺」の中に,3日にわたつて看護のところを論じているところがある。子規の看護は故郷松山から出てこられた母堂と令妹がされたのであるが,子規はかなりわがまゝな病人のようであつた。もともと超人的の意力の持主であつたが,結核が全身にひろがり,脊椎カリエスを起し七つの瘻孔が腰に開き,ちよつと身動きしても激痛が全身をつゝぱしり,大の男が聲を上げて泣いたという有樣であつたから,無理も無いところがあつたのである。
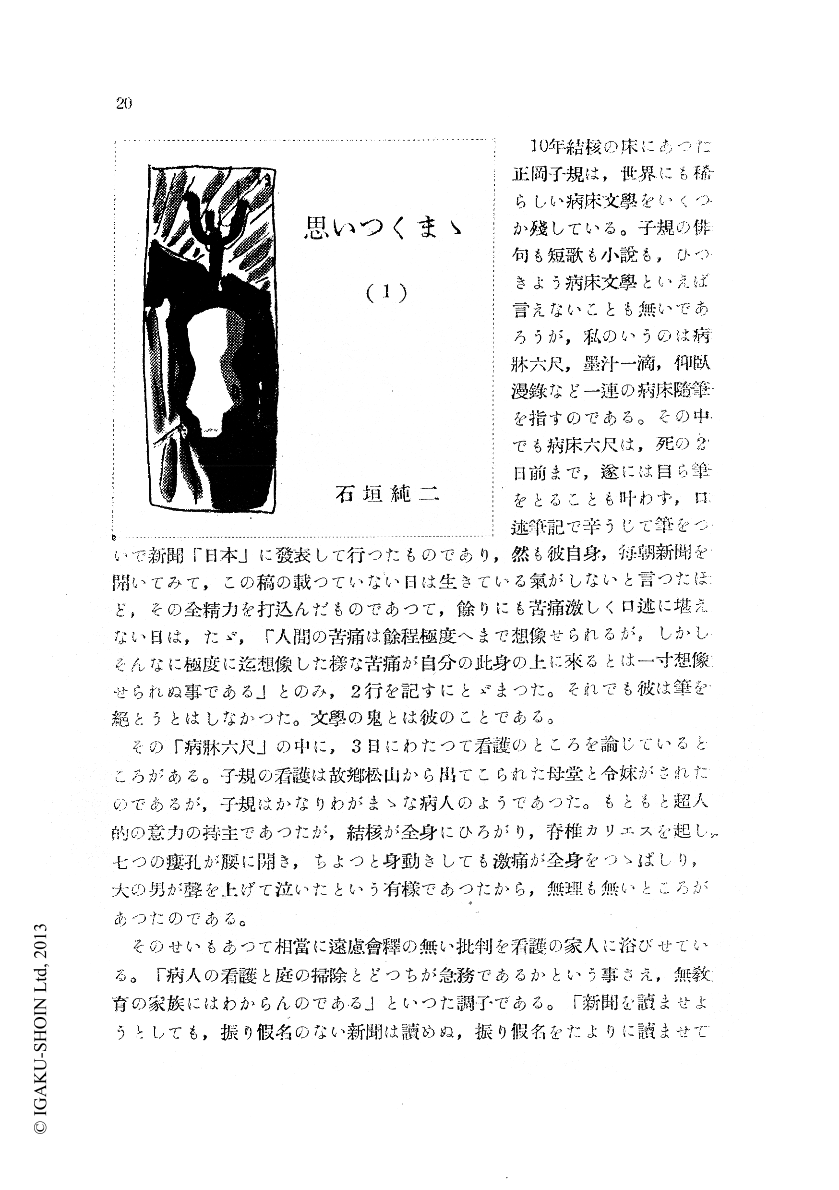
Copyright © 1949, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


