Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
パーキンソン病(PD)は,黒質などのモノアミン含有細胞に主座を置いた変性疾患で,その運動症状は振戦や筋固縮のような陽性徴候と無動や姿勢調節障害のような陰性徴候からなる.本症の治療は,ドーパ製剤などの薬物療法が基本ではあるが,難治性の振戦や固縮に対しては視床の腹外側核(VL)や腹中間核(VIM)などを標的とした定位視床手術が行われてきた.視床手術は確かにこれらの陽性徴候を劇的に軽減するが,患者の目常活動(ADL)にもっとも影響を与える無動症などの陰性徴候にはまったく効果がないばかりか,両側手術でかえって増悪する傾向がある.また,実際は固縮は薬物に反応するため視床手術は振戦を対象とすることが多いが,PDの振戦はしばしば随意運動でかえって軽減するため,視床手術は形成外科的意味合いが濃い.このようなことで神経内科医らがPDに対する視床手術を必ずしも前向きに受け入れてこなかった理由も納得できるものがある.
最近,振戦,固縮とともに無動などの陰性徴候に有効な定位脳手術がLaitinenら15,16)によって報告され注目をあびている.それは1950年代にLars LeksellがPD)を対象に開発した後腹側淡蒼球手術(posteroventral pal—lidotomy,PVP37)で,Laitinenらが復活させるまで40年近く一般に知られることなく埋もれていた定位脳手術法である.本手術は破壊的手法で陰性の冬神経徴候を改善させる点で,従来の機能的神経外科にはなかった特異性を有している.しかし,その牛理機構はまだ充分に説明されておらず,したがって適応範囲も明らかでない.われわれは無動を主徴とするpD患者を対象に,手術部位をMRIにより解剖学的に同定するとともに,微小電極法で大脳基底核のニューロン活動を記録し生理学的に確認したのち,Laitinenらよりさらに限局した凝固巣を後腹側淡蒼球に加え,彼らと一部異なった結果を得た28-30.近年,大脳基底核の生理機構は著しい進歩を遂げ,少なくともその構成要素を結ぶ神経回路網やその伝達物質と特性が明らかになってきた1,3,4,11,14,24).われわれが経験した臨床および生理学的知見をもとに,本手術の適応範囲や生理学的位置付けを考察する.
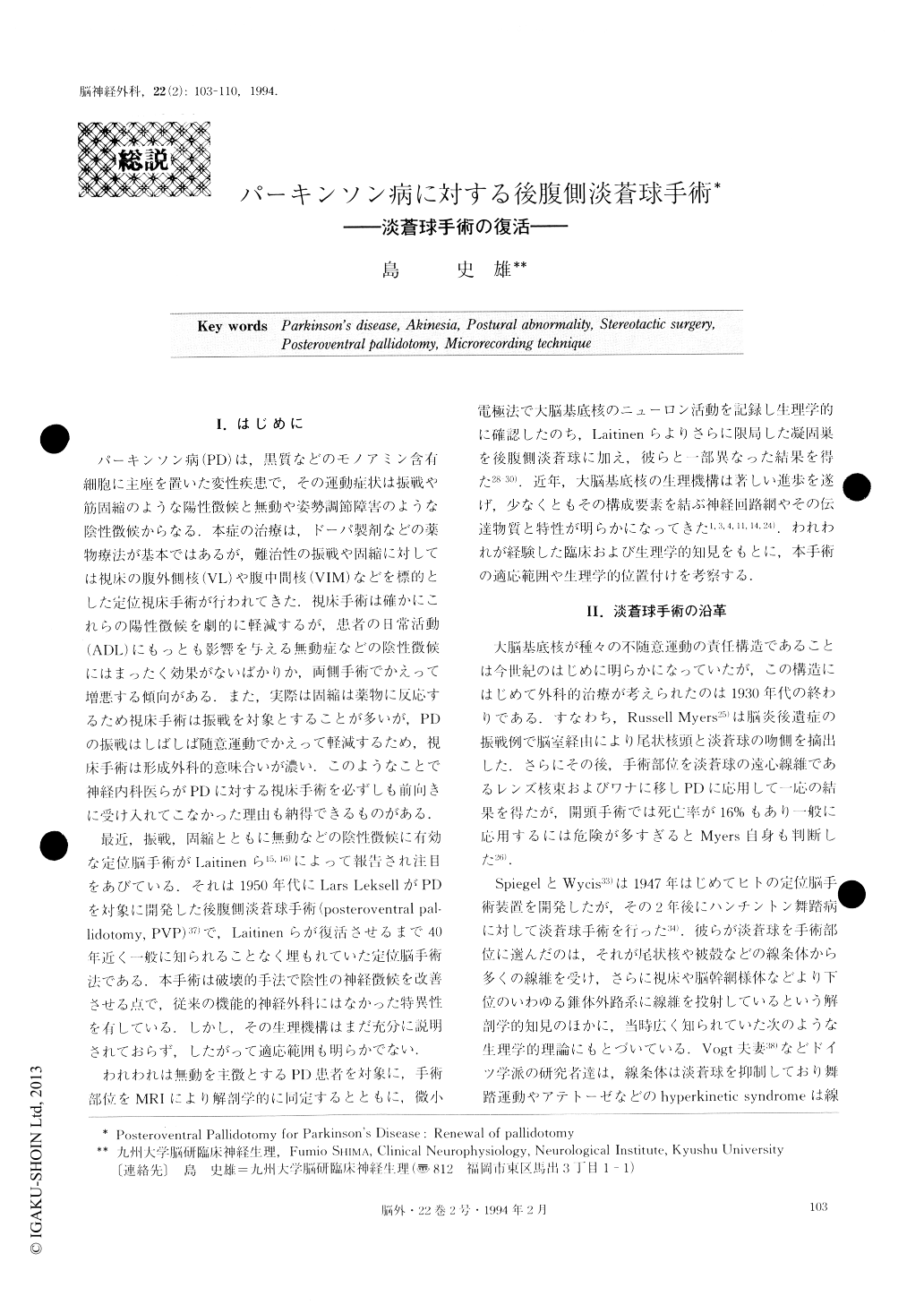
Copyright © 1994, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


