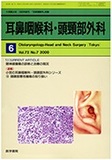- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
聴神経腫瘍の治療は,19世紀中ばのBalance(1834)に遡るといわれている。今世紀に入って間もなく,Cushingにより本格的に外科的治療への挑戦がなされた。しかし,検査機器や手術機器の不十分さに加え,抗生物質もない1910年代の手術死亡率は66.6〜70%と惨澹たるものであった。Cushingの業績は聴神経腫瘍のクロノロジーに集約される。彼の仕事は,彼の学生であったDandyに受け継がれた。彼は,当時患側決定が難しく,両側開頭をすることも少なからずあったものを,聴力障害のある側を患側としてより小さな開頭で済ませるようにした。また,1920年代になってX線撮影が軌道に乗ると,気脳写を導入して患側を確認することを可能とし,より小さな腫瘍をてがけることもできるようにしたのであるが,完全摘出しなければ2〜3年で再発することもわかった。このために,完全摘出のためには,顔面神経を犠牲にするのもよしとされていた。即ち,Dandyは“Loss of the facial nerve is a cheap price to pay for the total removal of an acoustic neuroma”とも断言していたのである1)。
1960年代に入って,House2)によって初めて顕微鏡手術が導入され,これによって顔面神経の同定と保存の成績が上がり,腫瘍の完全摘出も可能となって治療成績の大幅な向上をみた。さらに,その後の神経耳科学的診断法やX線学的診断法の進歩,特にCTの導入によって飛躍的に診断率が向上し,その後のMRIの登場によって内耳道内に限局する腫瘍も正確に診断できるようになってきた。こうして,機能障害のわずかな小さな聴神経腫瘍の診断が容易となって,今や顔面神経を保存することはもとより,聴力保存が大きな課題となっている。しかし,現在こうした小腫瘍の治療法をめぐっては議論のあるところである。外科的治療法のほか,ガンマ-ナイフのような保存的な比較的新しい治療法も含めて,機能保存に対する成績向上を目指し患者のQOLを上げていくことがこれからの課題である。聴神経腫瘍の診断と治療において,聴覚,平衡,顔面神経および側頭骨外科を取り扱う耳鼻咽喉科医がその目標達成に向けて果たす役割は大きいと思われる。
本稿では,聴神経腫瘍の診断と治療の現況について,筆者の経験を含めて概説する。

Copyright © 2000, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.