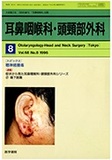鏡下咡語
医療と情緒の力
松永 喬
1
1奈良県立医科大学耳鼻咽喉科学教室
pp.692-693
発行日 1996年8月20日
Published Date 1996/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1411901410
- 有料閲覧
- 文献概要
「私は81歳の母を甲状腺のガンで亡くした身です。最後の数日は,母は一言も口をきかず,じっと壁を見つめたままでした。抗ガン剤で苦しみ点滴を辛がりながら,最後は家族と心のつながりまで断ったような,不信と怒りと孤独の日々であったように思います。私たちはお医者様に“どうせ助からないのなら抗ガン剤はやめて命を無意味に引きのばすことは要らないのですから,せめて苦しくないようにしてやって下さい”とお願いしましたが,“最後まで生命を保つように努めるのが医師の義務です”と叱られました。どうしてもっと,せめて心の安らぎなりを得させてあげられなかったのだろうかと後悔の思いにかられるのです」。
「私の兄は4年前,肝炎のため27歳で亡くなりました。1年4ヵ月の入院の末でした。その病院は医科大学なので,兄より少し若い年頃の医者のタマゴが,回診の時,ぞろぞろついてきて寝ている兄のまわりをズラリと取り囲み,兄を見下ろすのでした。決して姿勢を低くして患者と視線を同じにするという配慮などないのです。勉強のためとはいえ兄も私たちもどんなに悔しかったでしょう。兄は最後まで治ると信じ,それゆえに強い薬による副作用によって体が次々とむしばまれていくことに疑問を抱き,医師や看護婦の顔を見る度に,それらの疑問,治療法に対する疑問をぶつけていました。しかし医師も看護婦もそれらに誠意をもって答えることもせず,それどころかうるさがっている有様でした。重い患者は医師や看護婦をどんなに頼っているか,もう一度考えてほしいのです」。
Copyright © 1996, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.