ヒューマンバイオロジー--臨床への展開 子宮頸癌
子宮頸癌における化学療法と免疫療法の問題点
杉森 甫
1
Hajime Sugimori
1
1佐賀医科大学産婦人科教室
pp.309-313
発行日 1985年5月10日
Published Date 1985/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409207169
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
子宮頸癌の治療は長年にわたり,手術と放射線による治療が主体であり,化学療法は再発癌や末期癌に姑息的に使用される程度であった。しかし,これまでの手術や放射線の術式や機器の進歩改善によって,副作用や合併症の発生率はかなり減少させることができたものの,進行期別にみた治癒率はあまり向上していない点が反省されてきた。手術や放射線は本質的に局所療法であるので,癌が局所にとどまる限りは優れた治療成績をあげうるが,転移を示すようなすでに全身疾患のphaseに入ったものに対しては,その成績に限界があるのは当然であって,この場合には化学療法の力を借りねばならない。また,進行癌や再発癌は手術や放射線による治療が困難であることから,化学療法が積極的に使用されるようになってきている1,2)。
1982年度に日本産科婦人科学会子宮癌登録委員会に報告された5,528例の頸癌I-IV期の治療法をみると,手術64.2%,放射線35.4%で,化学・免疫療法単独はわずか0.4%に過ぎない。しかし,手術や放射線に併用して化学・免疫療法を施行したものは23.8%であり,合わせて24.2%に何らかの化学・免疫療法が行われている3)。
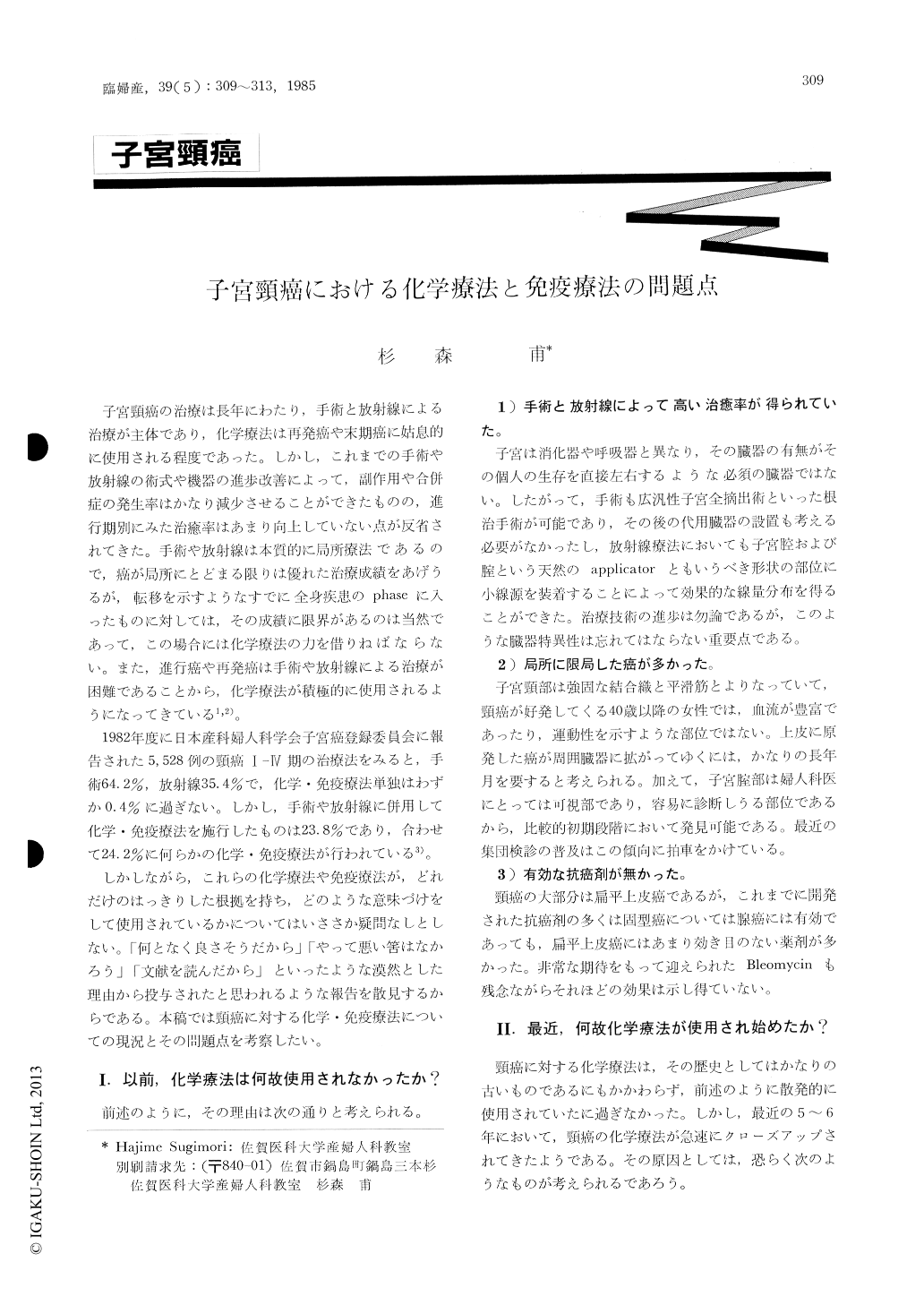
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


