明日への展開--ヒューマンバイオロジーの視点から 生殖免疫
Topics
妊婦の自己免疫疾患と新生児
松本 脩三
1
Shuzo Matsumoto
1
1北海道大学医学部小児科学教室
pp.661-663
発行日 1984年8月10日
Published Date 1984/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409207042
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
妊婦のもつある疾患が,生まれた新生児に一時的に発現する事実はかなり以前から知られていたが,そのような疾患の病因に免疫学的機構の関与していることは,10数年ほど前に初めて推測されたばかりである1)。その後間もなく,自己免疫機構に基づいて生ずることが明らかにされた疾患の殆んどで,母から子へ一時的に症状が伝達されることが確認されるようになった。妊娠中から周産期に至る間に母子相互間に起きる免疫学的影響の中で,ただひとつ明瞭にされていることは,母体のIgGクラスの抗体が主として出生前,周産期に経胎盤的に児へ大量に移行することである。これはヒトの胎盤がIgG分子のFc部分に対するレセプターをもっており,IgG抗体を母血中から胎児循環血中へ能動的に移行させるためである。したがって,もし母体にIgG抗体を介して生ずる疾患があるときには,その児がその抗体に相応する抗原をもつならば,母にみられる表現型が子にも表現されることは当然である。しかも経胎盤的に移行したIgGのターンオーバーは多くは2〜3カ月以内であることから,この表現型は乳児では決して永続的な障害に発展することはなく一時的な経過で消褪する特徴がある。
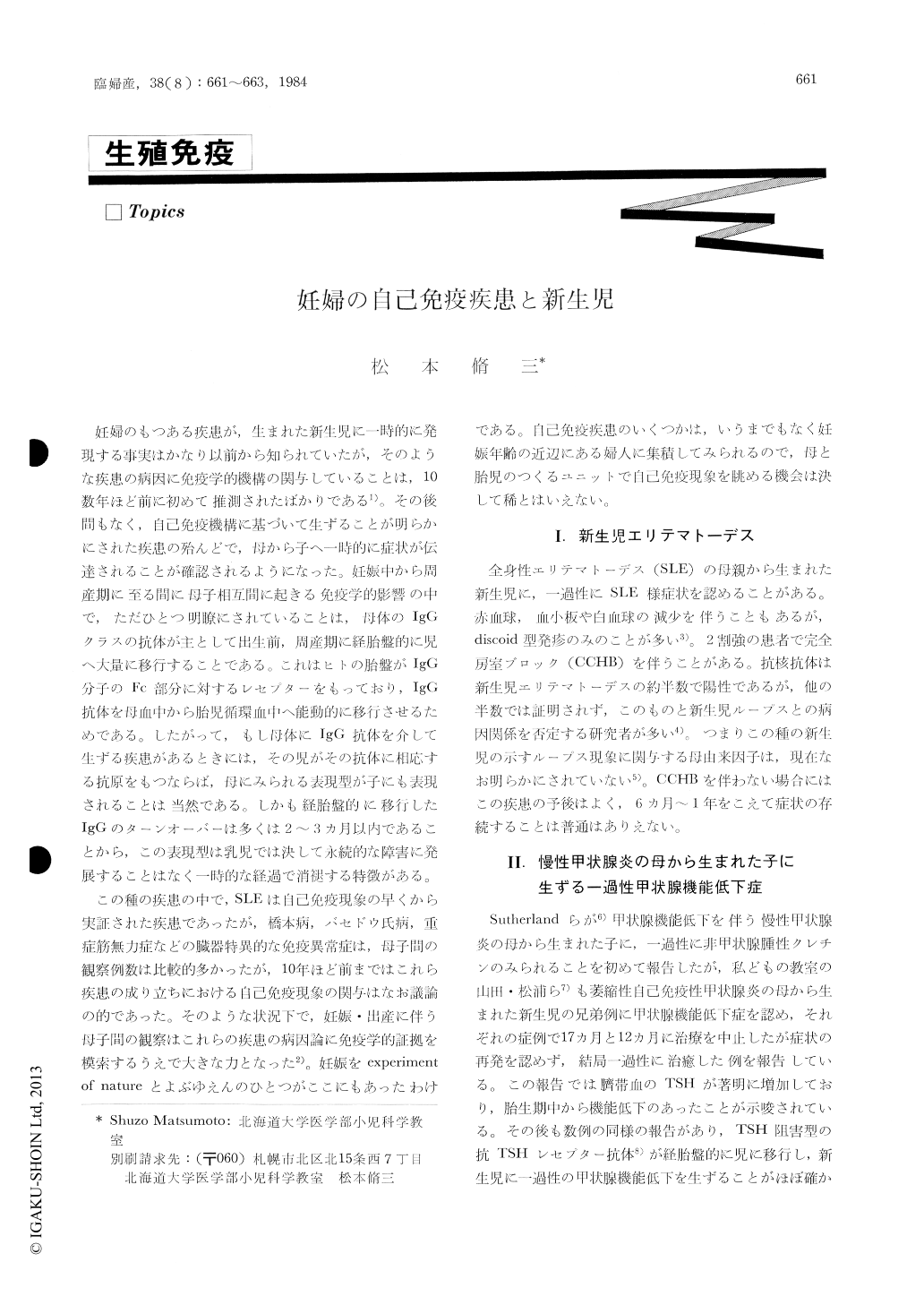
Copyright © 1984, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


