特集 産婦人科医に必要な臨床病理の知識その2
絨毛性腫瘍(1)—胞状奇胎および破壊性奇胎
竹内 正七
1
Shoshichi Takeuchi
1
1東京大学医学部産婦人科教室
pp.827-833
発行日 1966年10月10日
Published Date 1966/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409203575
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
胞状奇胎はそれ自身は良性疾患であるが,本症の5〜10%に絨毛上皮腫が続発し,一たび絨腫が発生すると,その予後はきわめて不良であるので,絨腫発生の予防という意味で,奇胎の取扱いが臨床上問題となる。ことに本症は妊娠性の疾患であるので,若い婦人に見られ,妊孕力の保持を計らねばならないことが多く,我々は本症の取扱いに悩まされることが少なくない。
従つて,胞状奇胎の臨床病理として問題になるのは予後診断が可能かということであるが,現在の段階では,病理所見と臨床経過との間にはしばしば大きなくい違いがあり,胞状奇胎の組織診による予後診断の価値には大きな疑問が持たれている。このように組織診の価値の乏しい理由は何であろうか? 第1は正常絨毛が病理学的に悪性性格とされている浸潤や転移を示すことである。肺に正常絨毛を認めることはまれであるが,絨毛細胞の栓塞が43.6%にも見られるという報告(Att—wood&Park 1961)もある。しかして,この正常絨毛と奇胎絨毛や絨腫絨毛との間における質的形態的差異は明瞭でなく,量的な差が認められるに過ぎないからてある。第2は宿主側の抵抗性因子(免疫的?)の関与が推定されるが,その形態表現が明確ではなく,組織診において十分な考慮が払われていないからであろう。第3に本症の発生病理がまだ不明であることである。
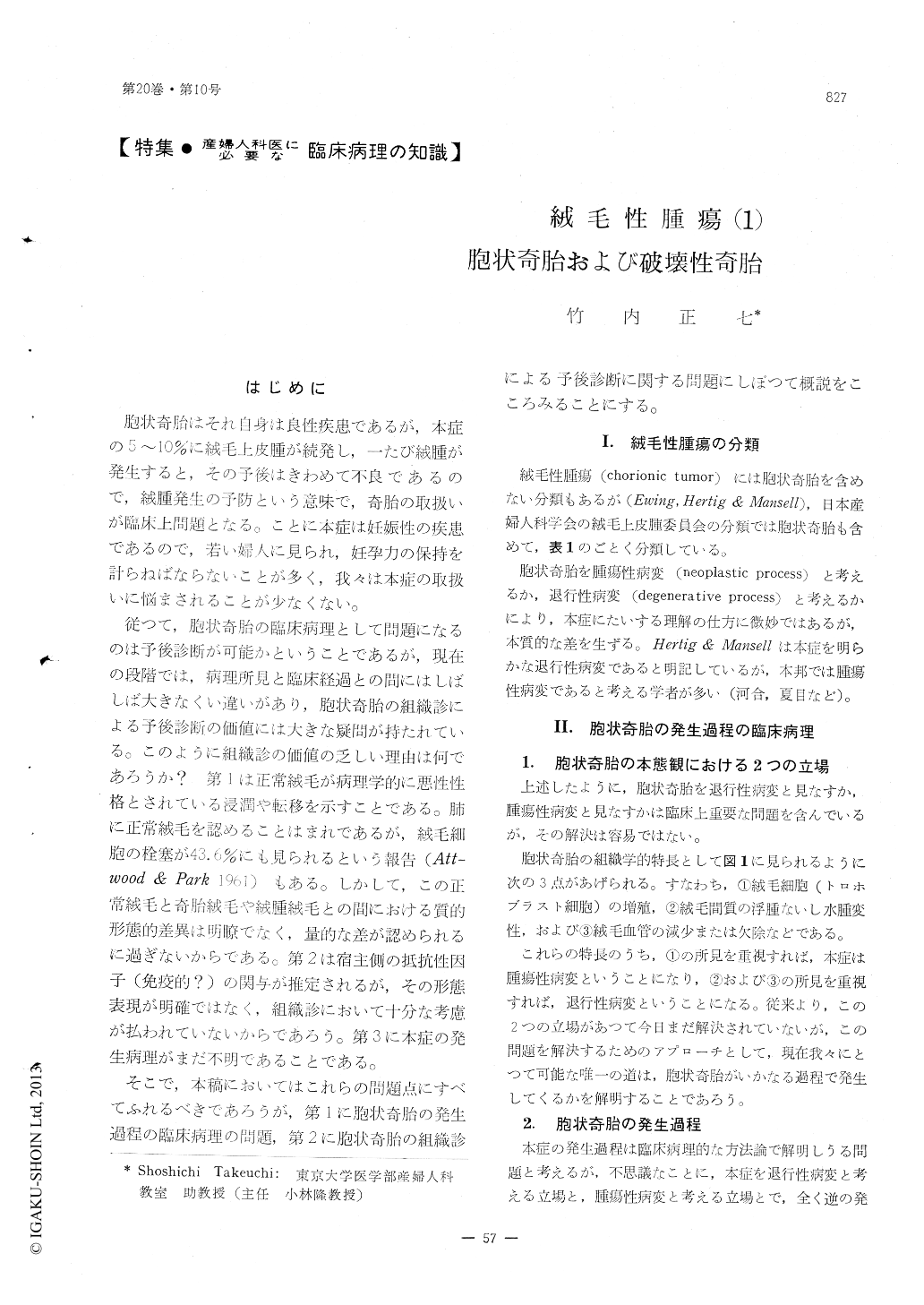
Copyright © 1966, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


