今月の臨床 婦人科がん治療の難題を解く―最新のエビデンスを考慮した解説
子宮体がん
3.子宮体がん腹腔細胞診はリスク因子か?
嵯峨 泰
1
,
今野 良
2
,
高野 貴弘
1
,
高橋 佳容子
1
,
大和田 倫孝
1
,
鈴木 光明
1
1自治医科大学産婦人科
2自治医科大学附属大宮医療センター婦人科
pp.1508-1512
発行日 2003年12月10日
Published Date 2003/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409101347
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
子宮体がんの多くは腫瘍が子宮体部に限局した早期例で,5年生存率は80%以上と比較的予後良好である1).しかしながら一部の症例では再発がみられ,再発例の死亡率は高いことから,30年前に比べて治療成績の改善はみられていない1).本疾患の再発ならびに予後を規定する因子を明らかにすることは重要である.1988年のInternational Federation of Gynecology and Obstetrics(FIGO)による子宮体がんの新しい術後進行期分類によれば,腹腔細胞診陽性は,付属器転移や漿膜浸潤と同様にIIIA期に分類される.しかしながら,腹腔細胞診が予後因子となるかどうかはいまだ結論が出ていない.
本稿では,われわれの施設における子宮体がん症例を中心に,腹腔細胞診がリスク因子となるか否かについて検討した.
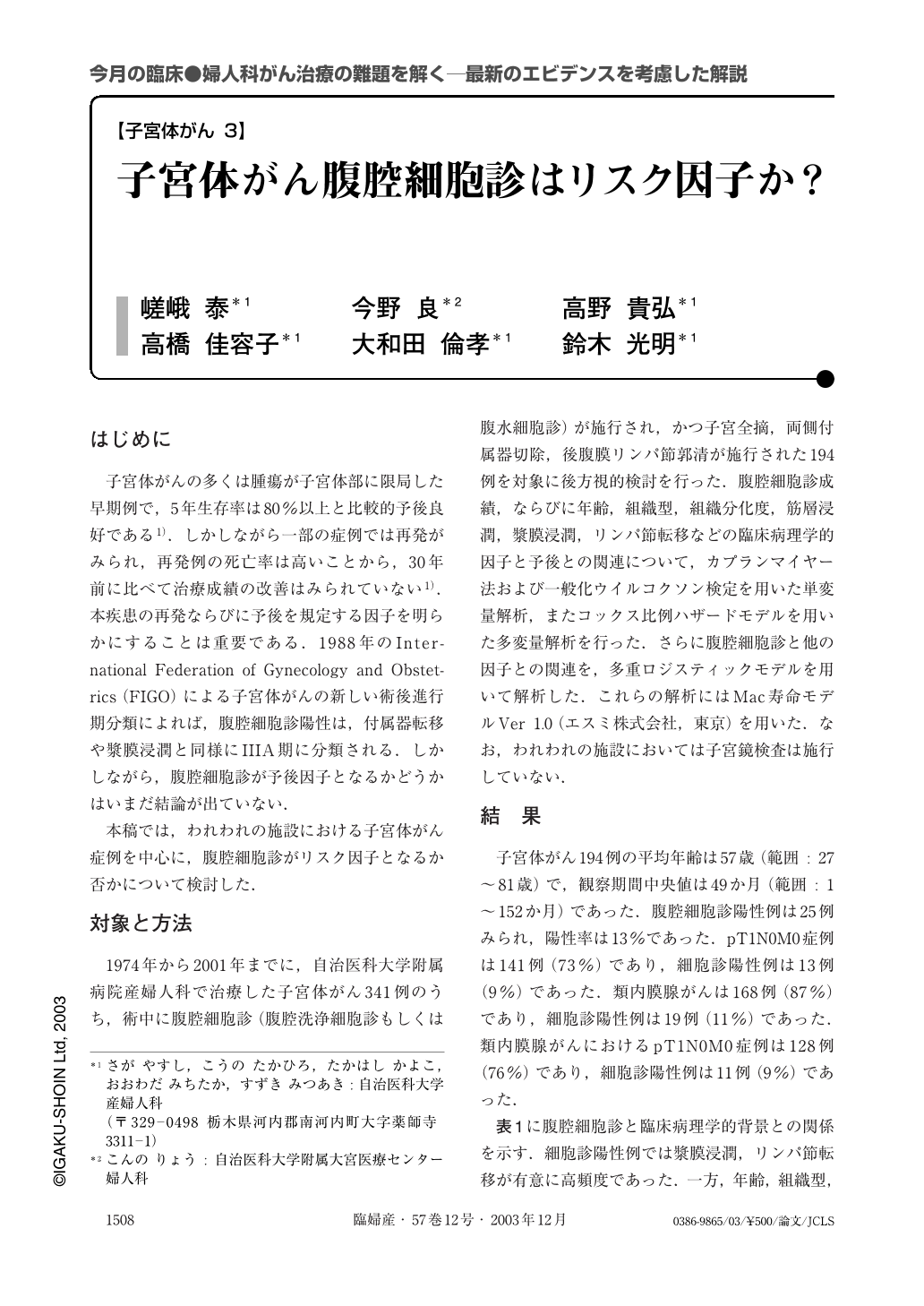
Copyright © 2003, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


