特集 保存的治療の適応と限界—外科から,内科から
急性胆嚢炎
内科から
千葉 俊也
1
,
松崎 靖司
1
,
田中 直見
1
,
大菅 俊明
1
1筑波大学臨床医学系消化器内科
pp.1500-1503
発行日 1990年10月30日
Published Date 1990/10/30
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407900256
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
近年,急性胆嚢炎の予後は著しく向上した.その要因として,診断技術および保存的治療の目覚ましい進歩があげられる.すなわち,診断技術面においては,直接胆道造影の経皮経肝胆道造影法(PTC)や内視鏡的膵胆管造影法(ERCP),超音波断層法(US),X線CTなどの新しい診断技術の導入・改善であり,治療面においては,超音波映像下経皮的胆嚢ドレナージ法(PTGBD)の普及および化学療法の発展である.
しかしながら,急性胆嚢炎症例の90%以上は胆石を保有しており,最終的には外科的治療が要求されることが多く,またときに穿孔性胆汁性腹膜炎や急性閉塞性化膿性胆管炎などを生じ重篤になることも少なくない.そこで,その手術適応および手術時期の判定が非常に重要な問題となる,急性胆嚢炎患者は最初に内科を受診することが多いのが現状である.したがって,われわれ内科医にとって急性胆嚢炎に対する保存的治療の適応とその限界,手術時期の判定はきわめて重要なことと考えられる.
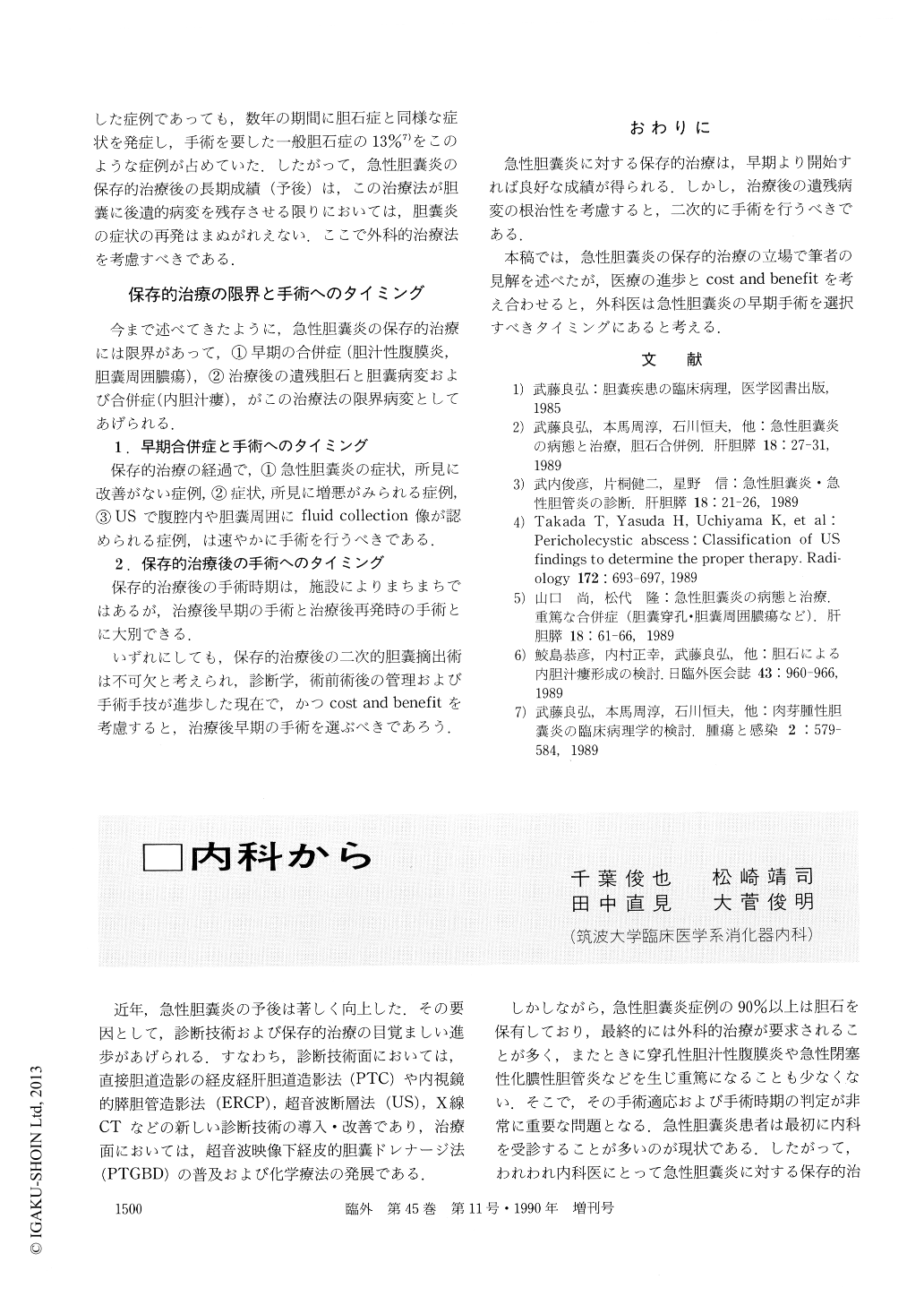
Copyright © 1990, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


