Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
かつてマニー(mania)は狂気の代表的な名称であった。それは古代ギリシアから綿々と受け継がれ,19世紀初頭のPinelの疾病分類においても主要な位置を占めていた。メランコリーがPinelによって部分狂気とされ,Esquirolが名称自体を解体した後も,マニーは依然として狂気の表象としてとどまり続けた。今なお,マニーという言葉はアルカイックな古層を呼び覚ます。それに対して,本稿のテーマであるヒポマニー(hypomania)は,いかにも現代的な様態である。
近年の気分障害は,非内因性事例が急激に増加する一方で,中核にある内因性事例においてはソフトな双極性障害,「双極スペクトラム」がクローズ・アップされてきた。双極Ⅱ型障害はその代表的なものであり,1970年代に北米においてDunnerら5)によって提唱されて以来,Akiskalらの精力的な臨床研究および啓発活動によって,臨床診断として一定の地歩を確立した。しかし未だに見逃される事例が後を絶たない。その多くが,うつ病やパーソナリティ障害などと誤診され,回復に難渋する。他方,些細な事象の過大視による過剰診断も少なからず目につく。いずれの場合も,足が速く変幻自在なヒポマニーの精神病理を捉え損なっているのである。
内因性の気分障害は,20世紀の中葉にその見取り図を大きく変貌させた。Kraepelin由来の一元論から,単極性/双極性の二元論へと転回したのである。この一種のパラダイム・シフトは,結果的に,気分障害の概念を単純化した。とりわけ「双極性」について,安易なイメージを作り上げてしまったのである。おそらく多くの臨床家が,その影響下にある。
その一つが「周期性」である。つまりは病相がサイクロイドのような弧を描き,一定期間のうちに収束するという経過モデルである。双極Ⅱ型の多くは,そのような緩やかなものではない。また,ともすればエピソードとして限局されることなく拡散し,普段の生き方に浸透してくることさえある。
今一つは「極性」というイメージである。つまりは「躁」と「うつ」がシンメトリーをなし,一つの軸の両端にあって,精神症状はその間を上下に振幅するというものである。そして経過はサインカーブで表象される。
しかしソフトな双極性障害の臨床像は,「躁」と「うつ」の関係が,自然界における極性の現象と異なることを示している。たとえば電気や磁性のように両極が相殺されることもなく,あるいは寒暖や明暗のように一元的な尺度で定量可能なものではない32)。ヒポマニーは神出鬼没に割り込んでくる。それは「うつ」を中和しないし,「うつ」によって中和されることもない。混合するのである。
ヒポマニーの精神病理を読み解くにあたって,一つのキーワードとなるのは「スペクトラム」という概念である。それはヒポマニーを従来のナイーブな病型や状態像のイメージから解放する。さらにsubclinicalな事象をはじめとする,さまざまな局面への着目を促すだろう。
気分障害をめぐるスペクトラムは単一のものではない。筆者のみるところ,少なくとも4つの軸がある。本稿では,それぞれのスペクトラムを順次取り上げながら,ヒポマニーの精神病理について論じていこうと思う。
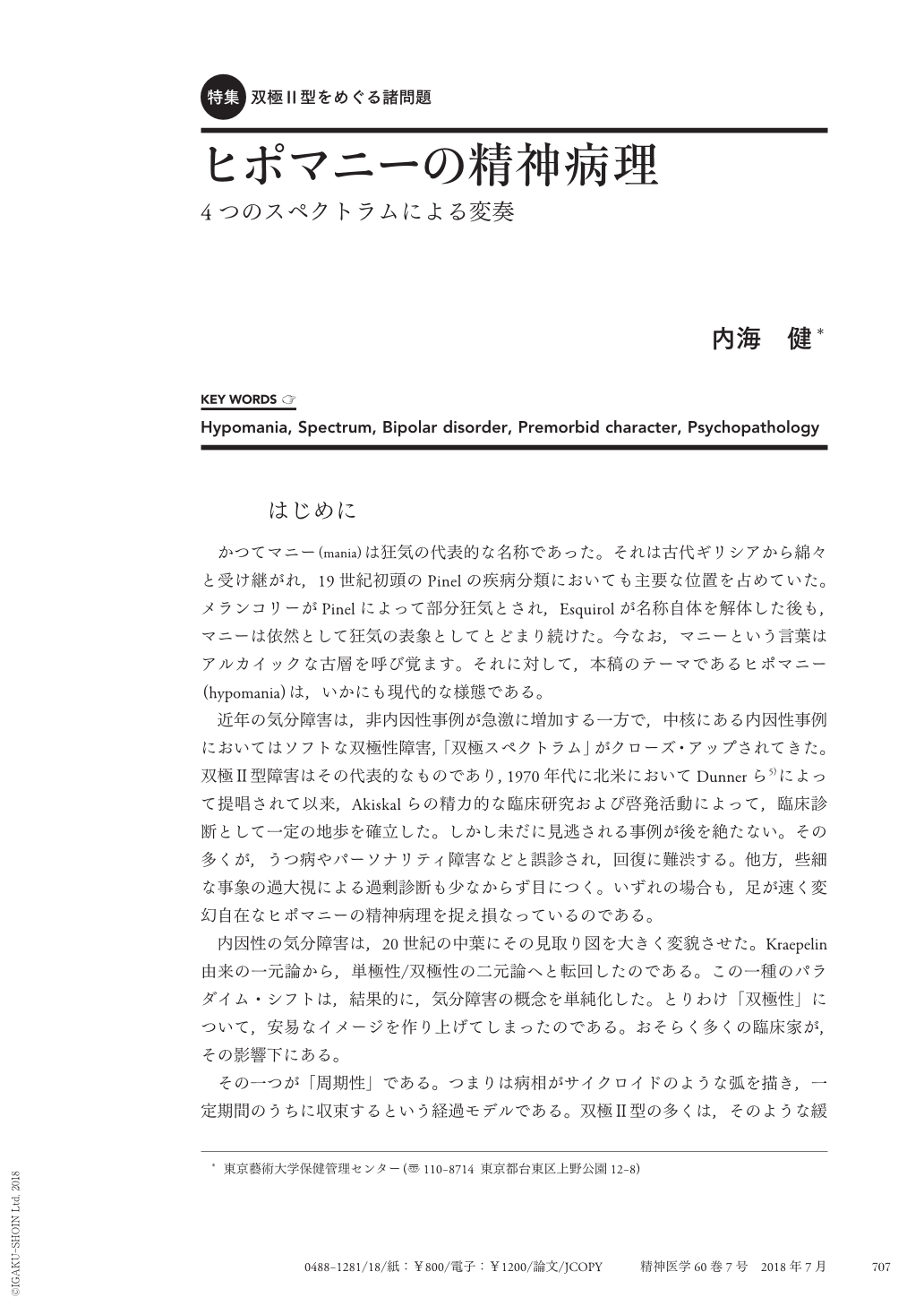
Copyright © 2018, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


