Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
I.はじめに
失語患者の発話に於ける「流暢性」fluencyという特徴を比較的明瞭な形で概念化して,失語学に導入したのはGoodglassら3)(1964),GoodglassとKaplan4)(1972),Bensonら2)(1967)の業績である。とはいっても,19世紀の偉大な観察眼が,この種の事実を見逃すはずもなかった。JacksonにせよWernickeにせよ,その著作を閲してみれば,今日の流暢性なる概念に相当する記述を見出すのに,さして時間を要しない。しかし今,歴史の森は,これを遠望するにとどめて,その小径に踏み入るつもりはない。
今日の失語学に於ける「流暢性」または「非流暢性」non-flunencyという概念を,我々は次のように考える。①流暢性とは,失語患者の発話に接した観察者の「全体的」な判断である。この意味で基本的には「直観的」・「印象的」判断である。②しかし当然のことであるが,この判断はいくつかの「個別的」な発話症状の評価に依拠している。その症状とは,例えば,構音障害,dysprosody,句の長さ(Goodglassら3),1964),休止,失文法または統辞論的障害,発話量(能登谷ら12),1982),発話量と情報量との相対的な割合,吃音(Koller10),1983),努力性発話,等々である。③これらの症状のうちのどれとどれに重さを置いて,流暢性を判断しているのかは,検者によって異なっているし,同一の検者でも常に同一の基準に従っているとは限らないかもしれない。④また例えば,聴覚的了解障害,反響言語,等のように,個別的な言語症状のなかには,その存否が流暢性の判断にほとんど影響を与えぬと思われるものがある。⑤流暢性には尺度としての性質もあり,例えば,「甲は己よりも流暢である」とか,軽度の非流暢性」とかの言い方も可能なはずである。文献的には,Benson2)(1967),Kertesz8)(1979),Knopmanら9)(1983)等の尺度がある。⑥この判定は,失語の分類に大きな影響力を有し,これのみにて流暢性・非流暢性失語の分類が行なわれている。
以上を背景として,ここで我々は,流暢性という特徴の数量化の可能性を探る。さらに流暢性を症候群として捉え,症候群のパターン認識という立場より(浅野1),1976),この概念の探索発見的exploratory方法として,因子分析の適用を試みる。
この小論は本来,前頭葉と言語の問題をテーマに企画された。この問題の検討のためには,準備として「流暢性」の再検討が不可欠であり,今回はここに焦点を当てて議論する。
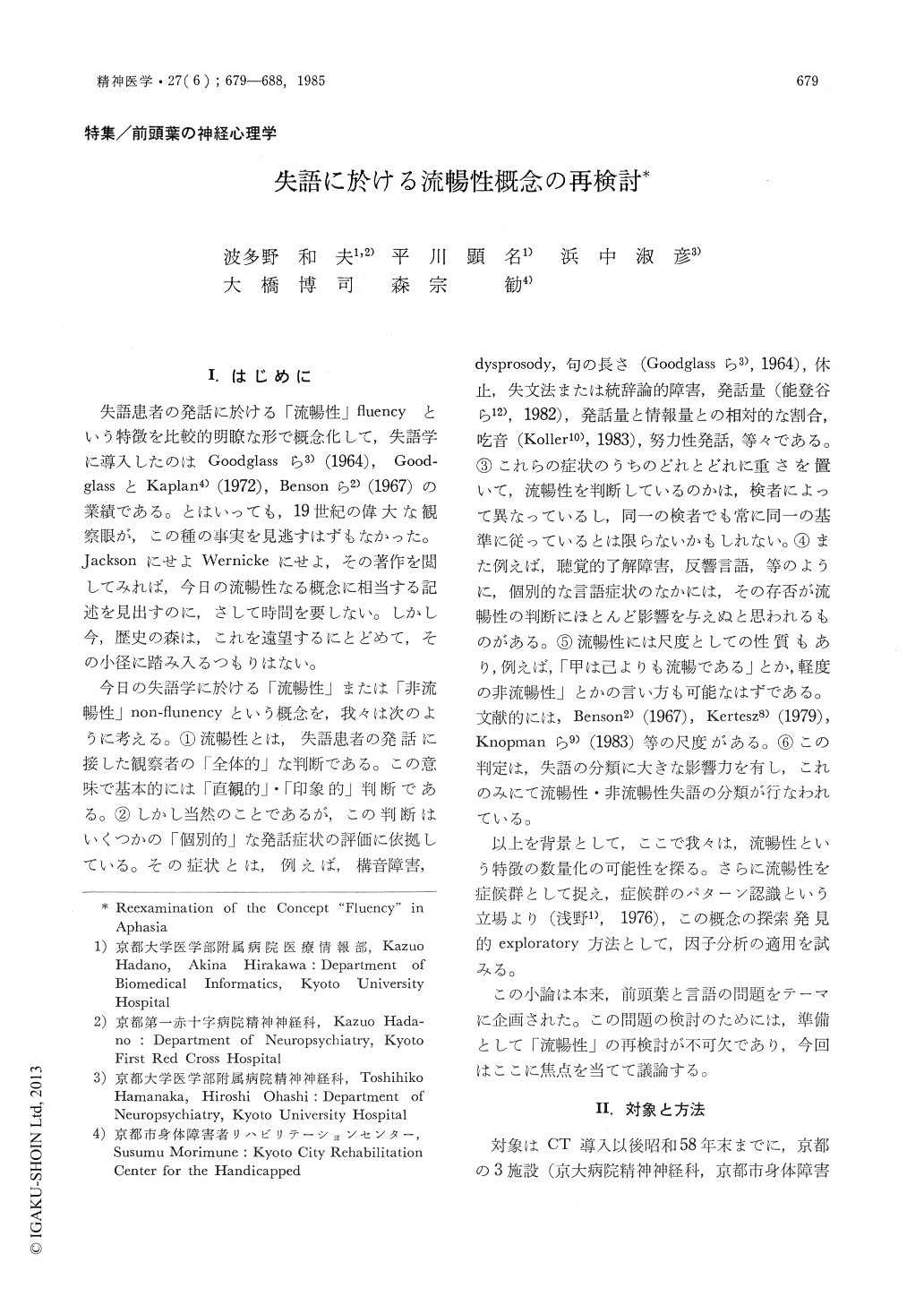
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


