Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
はじめに
一般に僧帽弁閉鎖不全症(Mitral regurgita—tion;MR)の手術適応を患者に説く時,明らかな心不全症状があって初めて外科治療の効果を,周術期に患者が受ける負担を上回る利益として説明できるものである.あるいは自覚症状がないかごく軽度の場合にも,左室機能の低下傾向を外科治療によって食い止める意義を納得させることができるものである.ところが,ほとんど症状がなくて左室機能の低下所見も見出せない場合は,例え高度の逆流が認められても,即手術適応とするには外科医といえども躊躇するのが普通である.手術そのものの危険性と術中術後に起こり得る様々な合併症を懸念するだけではない.術後遠隔期には,弁置換を行えば抗凝固療法によって患者の生活を少なからず制限することになり,それでも一定の頻度で人工弁の合併症を覚悟せざるを得ず,また弁形成術を行っても時には逆流の再発を来すこともあり,結果的に術前以上のQOLが保証されないとも限らないからである.よく似た事情は外科治療ならずとも,最近のカテーテル治療にも共通するところで,予防的あるいは先取りの侵襲的治療には慎重であり過ぎることはないといってよい.
しかしながら,MRに対する弁形成術の進歩・普及とともに,手術適応が徐々にではあるがより早期に考慮されるようになっていることも日常診療の場で経験される事実である.自らの患者が弁形成術を受けて理想的な状態で帰ってくるという,内科医の体験が積み重なって適応の早期化が加速される現象としてみることができる.確かに,これを支持するような弁形成術の優れた成績が数多く報告されているが,問題は,それぞれに異なる個々の症例に即した外科的治療方針をどのように考えるかである.自験例を紹介しながら,MRに対する弁形成術の早期適用について私見を述べる.
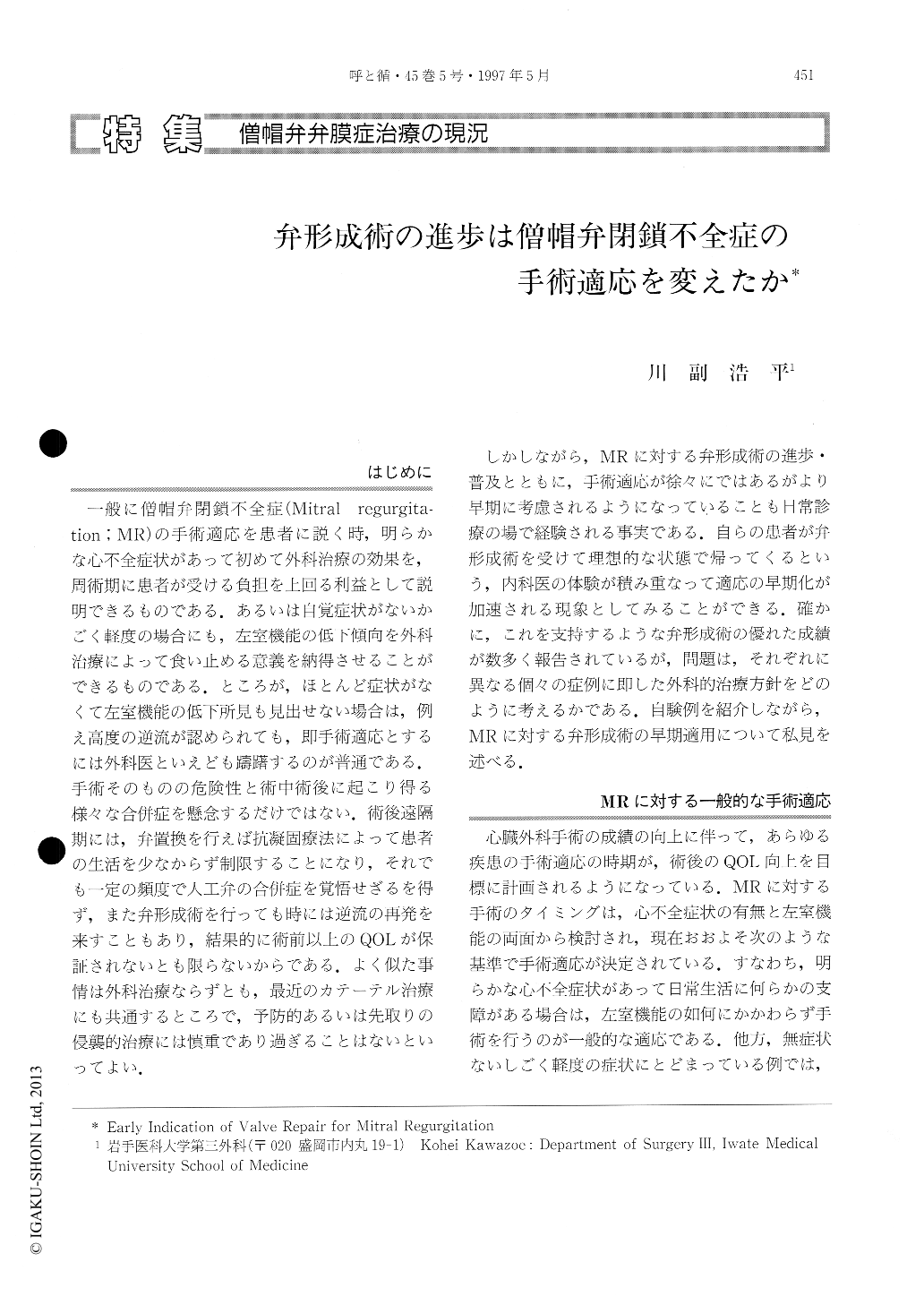
Copyright © 1997, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


