--------------------
編集後記
大谷 吉秀
pp.1222
発行日 2006年7月25日
Published Date 2006/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1403104328
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
1980年代から行われてきた早期胃癌に対する内視鏡治療は,ESDとして急速に普及した.低侵襲で,治療後の機能欠損がほとんどない点は他の外科的治療法の追随を許さない.しかしながら,内視鏡治療がスタートしてから20年以上経過した今日でも,ESDが根治的治療法として成立するためには,内視鏡下に完全切除が行え,切除標本が十分病理組織学的検討に耐え,かつ,その結果としてリンパ節転移の可能性が極めて低いと判断される,という条件を満たさねばならない.本号ではリンパ節転移が疑われるm癌の病理形態,X線・内視鏡所見の特徴のみならず,それらの症例に対する縮小手術の是非,適応やQOLを考えた手術術式について,網羅的に詳しく述べられている.さらに,市川らは,“早期胃癌手術症例の臨床病理学的解析による統計学的な見地から,内視鏡治療の適応病変を拡大することはもはや限界に近い"と断言し,cDNA Microarray解析を用いた遺伝子異常と臨床病理学的因子の研究の重要性を指摘している.
10人に1人のリンパ節転移陽性早期胃癌症例を判別するために,より精度の高い診断法をいかに発展させ,治療に応用するか,基礎と臨床の双方から,チャレンジが求められる.近い将来,分子生物学手法やsentinel nodeなどの全く新しい概念による転移診断が,早期胃癌内視鏡治療の適応拡大を飛躍的に推進し,再び本誌で主題が組まれることを楽しみにしたい.
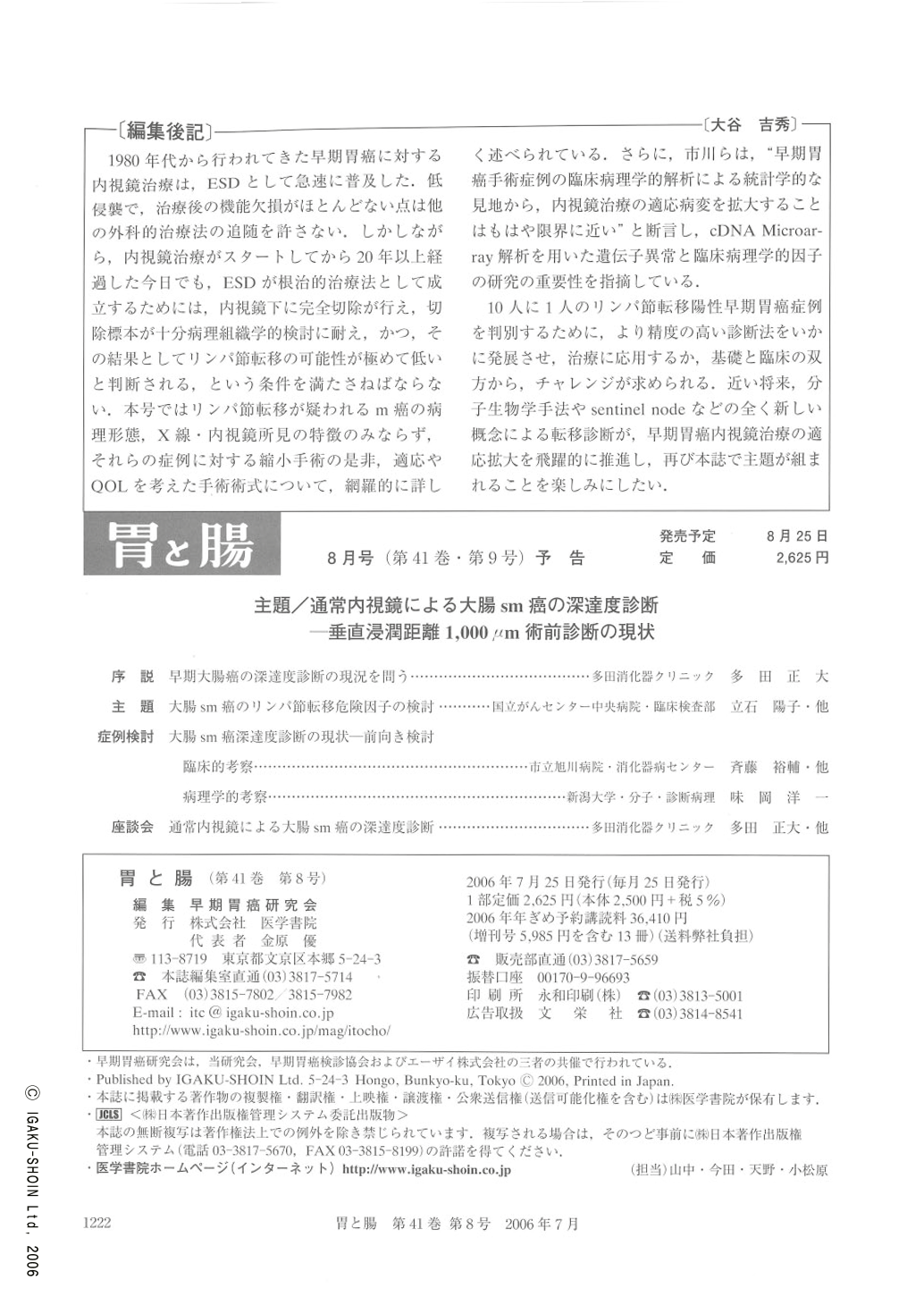
Copyright © 2006, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


