- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
1.当該疾患の発生動向
肺炎球菌感染症は、グラム陽性球菌である肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)によって起こる感染症である。気管支炎、中耳炎などの市中感染から、肺炎、敗血症、細菌性髄膜炎などの侵襲性肺炎球菌感染症(invasive pneumococcal disease: IPD)を引き起こす。IPDは重篤な後遺症や死亡のリスクが高い疾患である。小児肺炎球菌ワクチン導入以前のわが国において、小児細菌性髄膜炎の原因菌の第2位が肺炎球菌であった1)。全国多施設共同研究(1道9県)における調査2)によると、ワクチン導入前の2008〜2010年における5歳未満小児人口10万人当たりの肺炎球菌による髄膜炎罹患率は2.6〜3.1、非髄膜炎罹患率は21.2〜23.5であり、IPDは毎年1,200症例程度発生していたと推計された。IPDは2013年から感染症法5類感染症の届出対象疾患となっている。2014〜2021年の感染症発生動向調査3)によると、IPDの年間報告数は2014年以降2018年まで経年的に増加し、2020年以降に減少している。2020年の人口10万人当たりのIPDは、全年齢1.32、5歳未満6.0、65歳以上2.75と、小児患者が最も多い。5歳未満における年間報告数の推移も全体と同様に、2014〜2019年にかけて増加し、2020年以降に減少している。病型は、5歳未満では菌血症、菌血症を伴う肺炎、髄膜炎の順に多く、65歳以上では肺炎、菌血症、髄膜炎の順に多く見られている。後述するように、ワクチン導入後にワクチン含有血清型によるIPDは激減したが、ワクチン非含有血清型のIPDが増加している4)。本稿では、主に小児のIPDと小児肺炎球菌ワクチンについて解説する。
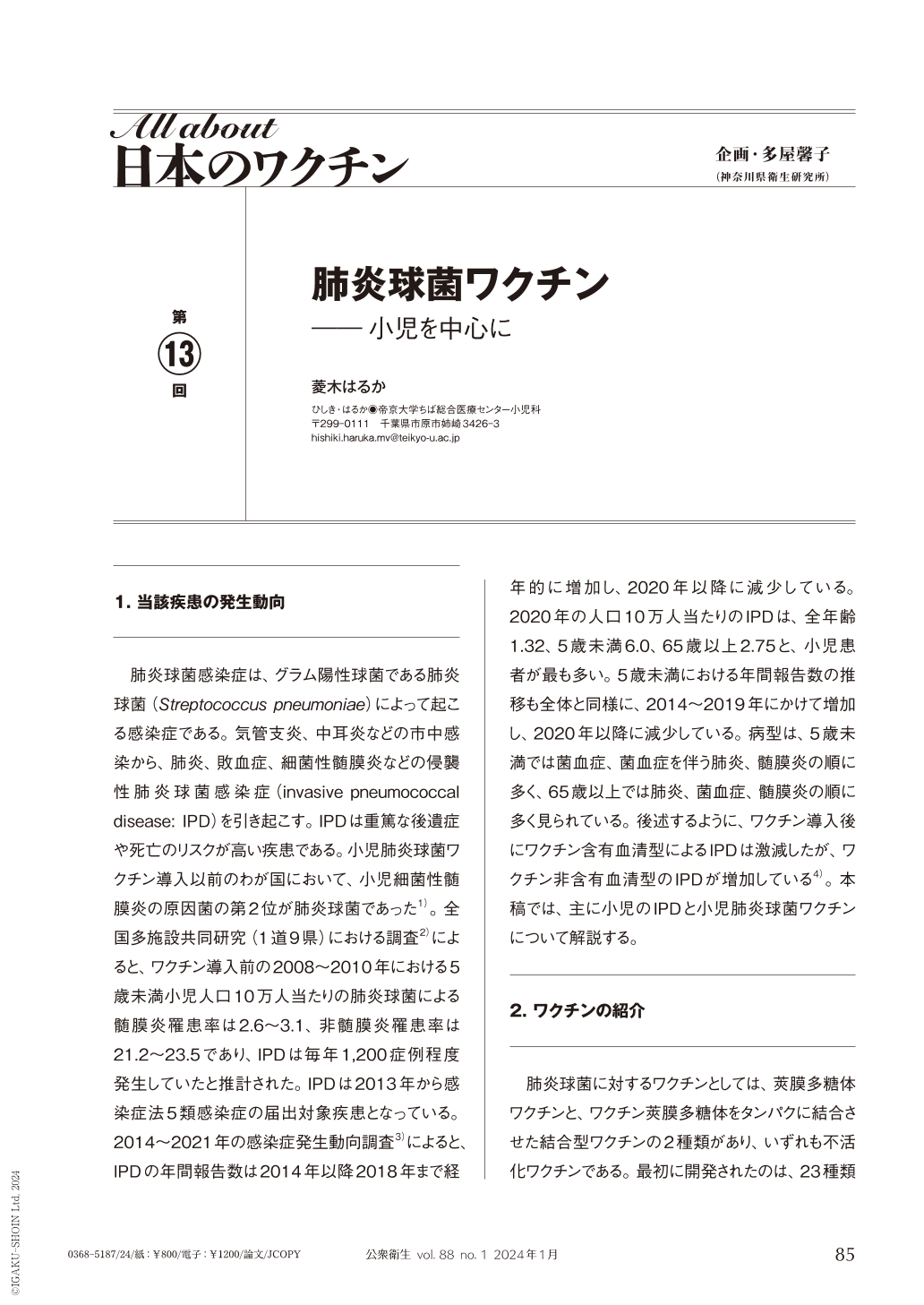
Copyright © 2024, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


