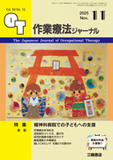- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
農福連携とは,障害者や高齢者が農業分野で活躍することを通じて,自信や生きがいをもって社会参加を実現していく取り組みである.現在,全国では農福連携が社会参加の合言葉のように広がりをみせているが,農福連携を始めてみると,単に農業と福祉が連携してどうなるのかと言われる方が中にはおられる.筆者は,農福連携とは,生きづらさを抱えた方たちの特性や背景が,農業という植物の成長を観察したり収穫や手入れをするといった作業とマッチングすることであると考えている.
筆者が農福連携に携わるようになったのは,高知県安芸福祉保健所で自殺予防のネットワーク会議を開催していた2014年(平成26年)に,10年ひきこもりの生活困窮者のA氏を支援したことがきっかけである.この農福連携は,実は自殺予防の副産物として始まった多職種,多機関の取り組みである.
当時の高知県安芸市の産業は,2015年(平成27年)の「国勢調査」によると,27%が一次産業であり,25%の人が農業従事者であった.主な農作物はナスやユズ,ピーマン,ミョウガ等があるが,中でも冬春ナスの生産は全国1位であった.
農福連携は,何の根拠もなく行われているわけではない.農作業は多岐にわたることから,生きづらさを抱えた人々が特性を活かして活躍できる可能性が十分にあるのである.安芸地域の農福連携では,雇用する農家側も,生きづらさを抱えた人が元気になっていく姿を見ることに喜びを感じ,人が変わっていく過程に遭遇できている.
他方,就労する側にとっても,農業は筆者の経験上,体調を整える効果があり,収入を得ることができ,目標設定により元気になる効果がある.元気になった後,以前の職業的目標が蘇り,転職していく方もこれまで支援した中で,約30人程度存在した.以下に筆者がかかわった5つの事例を提示し,農福連携の今後を考えたい.
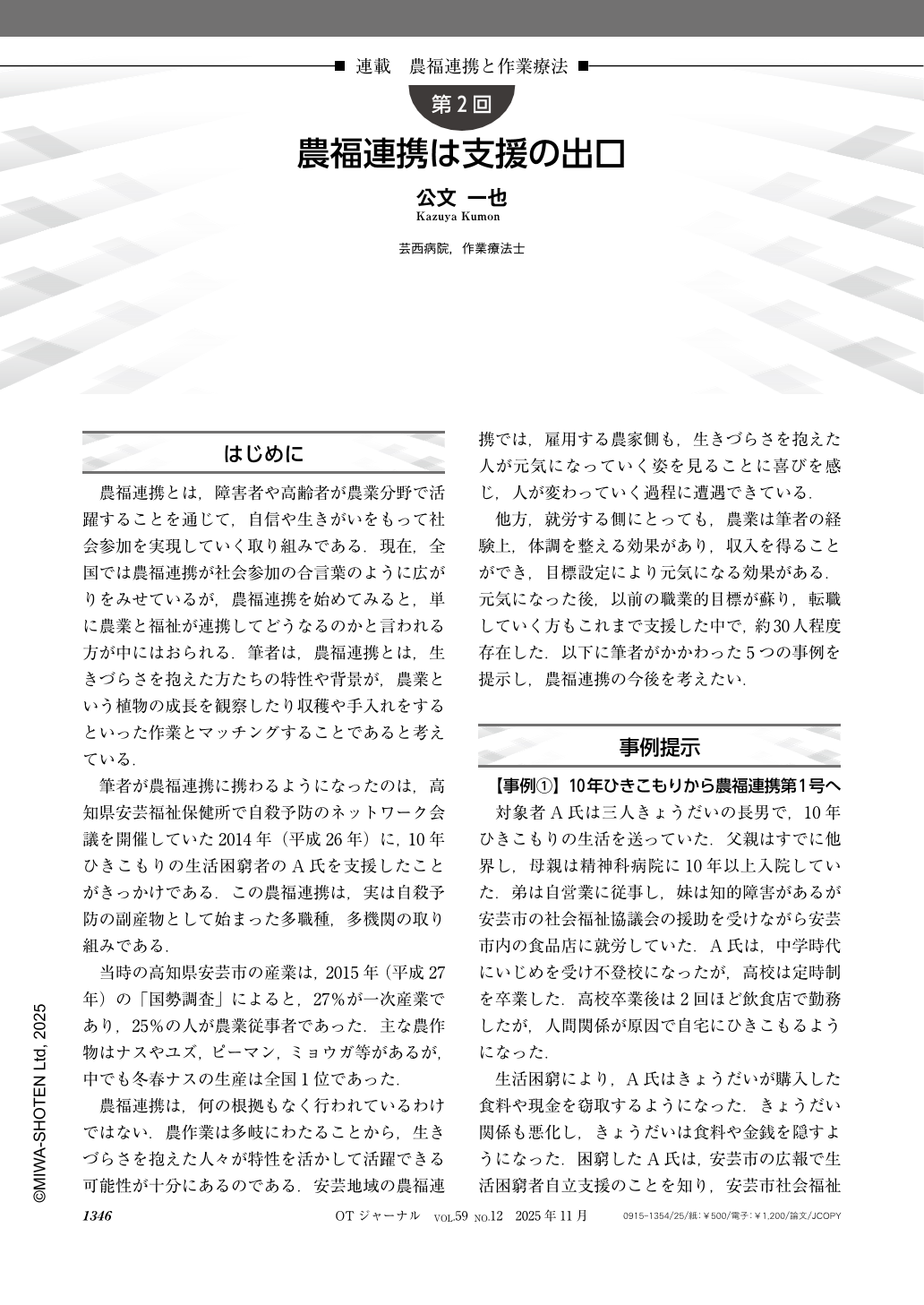
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.