Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
Key Questions
Q1:見守り支援機器とは?
Q2:見守り支援機器の制度における位置づけとは?
Q3:見守り支援機器の今後の課題とは?
はじめに
介護DXや介護の生産性向上が大きな話題となっている中,高齢者へのIT支援の代表格の一つとなっているのが見守り支援機器である.1万7,000件を超える福祉用具を収載している公益社団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(Technical Aids Information System:TAIS)には,883件(執筆時)の見守り関連の機器が収載されており,移動や外出関連の機器の数には及ばないものの,排泄や入浴関連の機器と並んで,多くの機器が登録されている1).国際福祉機器展2025の来場者アンケートの結果においても,「お探しの製品の種類」についての質問項目にて,「センサー・見守り機器」と回答した福祉関係者は12%との数字が得られており,22項目の福祉用具中8番目の多さとなっている2).これらの結果は,利用者のニーズの多さも表していると考えられる.
従来,認知症等による徘徊感知を目的とした機器と緊急通報システムが,主たる見守り支援機器とされてきた3).徘徊感知機器は,2000年(平成12年)の介護保険開始当時より,福祉用具貸与の種目に挙げられ,給付の対象となっており,在宅でも利用されている.施設では,床マットタイプの離床センサーは多く利用され,普及も進められてきた.しかしながら,2023年(令和5年)に報告された認知症に係る行方不明者数は1万9,039人であり,2014年(平成26年)から増加の一途をたどっている(図)4).緊急通報システムは,主に在宅で生活する高齢者の体調急変等に対応して,自宅に設置された緊急通報装置のボタンを押すことにより,支援センターや消防署,医療機関等に通報を送ることができるシステムである.高齢者の孤独死,孤立死が社会問題となる中,自治体が補助制度等により導入を促進するケース等もみられてきた.2025年(令和7年)4月には,警察庁が初めて自宅において死亡した一人暮らしの高齢者の統計値を公表し,5万8,000人に上ることが示された5).このように,見守り支援機器には,社会の要請も大きいことがわかる.
一方,技術開発の領域では,画像処理による人の動きの検出技術や,バイタルセンシング技術の進歩が目覚ましく,高度な見守りが可能となっている.特にAI技術の活用はここ数年で飛躍的な進歩を遂げており,利用者や社会の要請に応え得る支援機器が利用可能となっている.
本稿では,このような状況を踏まえ,見守り支援機器の最近の動向を概説するとともに,介護保険における見守り機器の状況とロボット介護機器関連の事業における見守り機器の位置づけ,そして2024年(令和6年)に新たに経済産業省と厚生労働省から示された介護テクノロジーに関する事業における見守り機器の展開について概説する.さらに,筆者らが実施している見守り機器の利用実態の調査結果を紹介しつつ,この領域の課題を示すこととする.
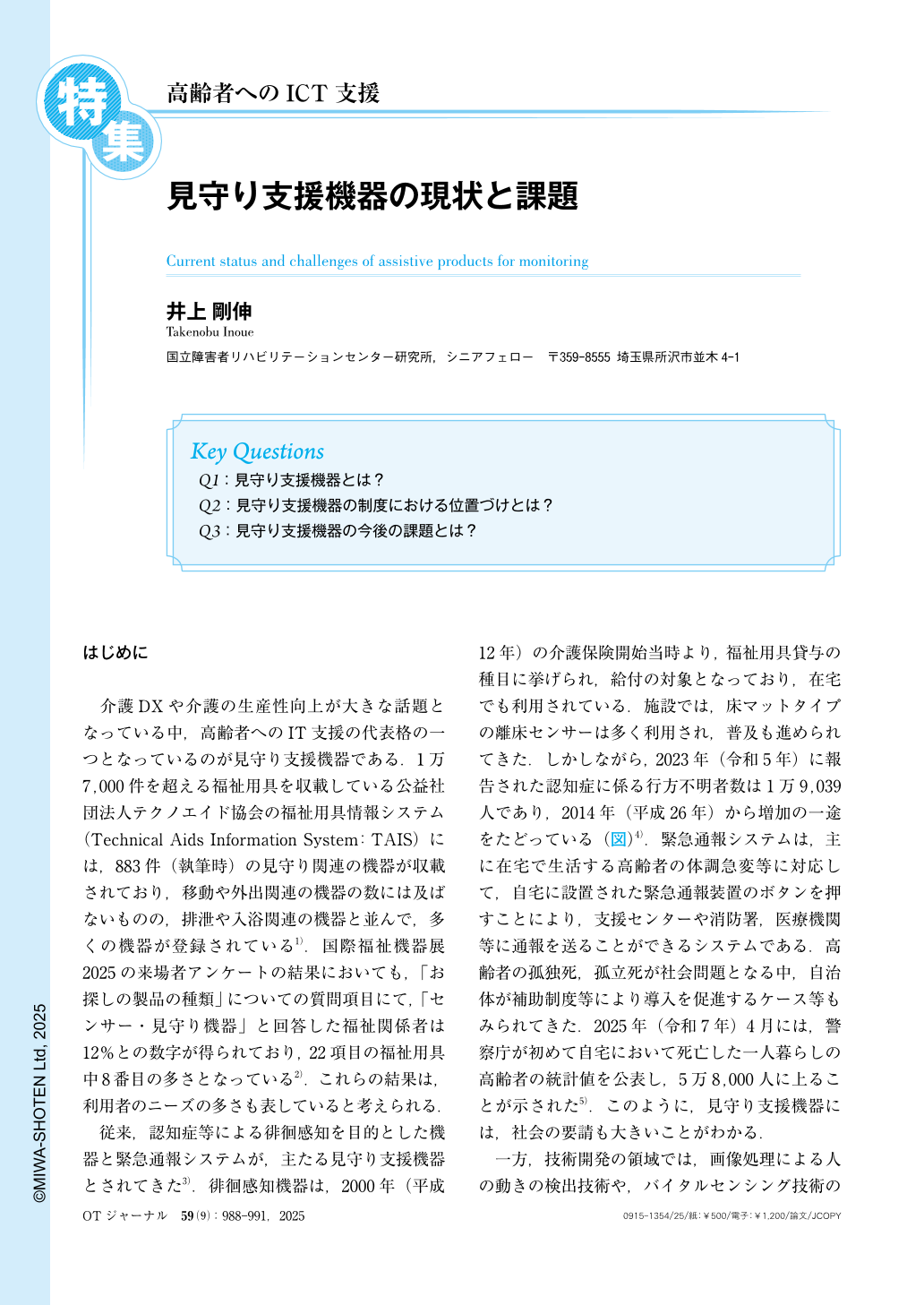
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


