- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
株式会社奏音は,長く養成校の教員をしていた私が2010年(平成22年)に設立した会社である.私の末子が発達障害であると診断されたにもかかわらず,当時は療育を受けたい子どもたちが多く,十分にその機会が与えられないでいた.このように「療育を受けたくても受けられない子どもがいて,保護者が困っている」ならば「専門職による療育を提供する場」をつくろう,という思いで,療育に特化した障害児福祉支援事業を展開するために設立した会社である.
前述した末子は,受診したリハビリテーションセンターでの作業療法や言語療法等,療育の予約が月1回しか取れなかった.しかもその機会を親の仕事の都合でキャンセルすると,3カ月,4カ月先まで療育を受けることができない.すると,注意欠如で授業中ボーッとする,忘れ物が多い,偏食のため給食が食べられない,漢字が書けない等,種々の特性に合わせた対応が後手にまわり,末子は自己評価をどんどん下げていった.そのような状況で級友からのいじめもあり,学校になじめなくなり,小学3年次後半には学校に行かなくなった.学校に行くのがあたり前と思っていたわが子が不登校になると,親は「出口のないトンネルに入ったような,明けない夜を過ごしているような感覚」をもち,担任教諭からの「今日はどうされていますか?」,「明日は登校できそうですか?」という電話に申しわけなさを感じていた.しかし,学校に行けない日々が続いてくると,末子を一人家に残して仕事に出ることがあたり前になり,不登校であることに本人も周囲も慣れてきてしまっていた.そのうち毎日かかっていた担任教諭からの電話も週1回から,月1回になり,最終的には学期はじめと終わりに電話がある程度になっていったころ,親が子どもを学校に行かす努力も減っていき,不登校が月単位ではなく年単位で続くことになった.
不登校児は学校に代わるどこか行き先があればそこに行くだろうと考えがちであるが,学校に行けないということは,外出もしないのである.「学校に行ってないのだから買い物に行ってクラスメートに会うのが嫌だ」と,家から出る機会そのものが極端に少なくなる現状や,医療にかかるときでさえ本人の受診がかなわず,保護者が代理で受診することもある.そうなると,本人への支援は,行き場所をつくって待っているだけでは,十分ではない.支援者は家庭に入り込まなければいけないのではないか? そしてそれは,機能にアプローチし,活動の幅を広げ,参加を促すことのできる作業療法士が医療の立場で担うべきではないか? また不登校児本人にとどまらず,家族への支援も必要なのではないかと考え,訪問看護ステーションを設立し,訪問作業療法で不登校児への支援を行っていくことにした.
本稿ではこれらについて,事例を通して,不登校児に対する訪問作業療法の実際を述べさせていただく.
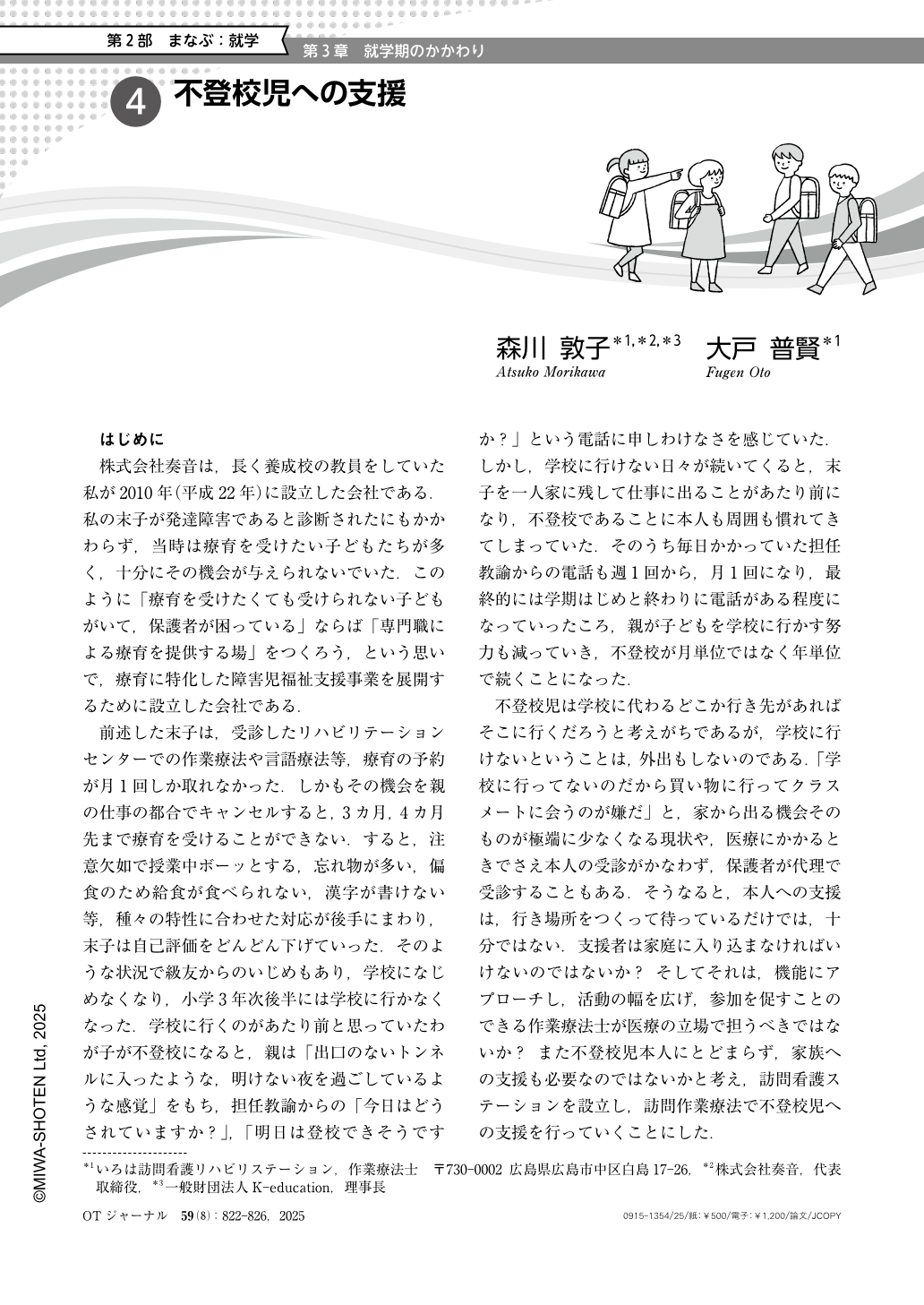
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


