- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに:作業療法士が学校(学び)にかかわる意義
近年,インクルーシブ教育の重要性が高まり,教育および学校にかかわる作業療法士の役割が注目されるようになっている.この背景には,2006年に国際連合の総会にて採択された「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」において,障害者に基づくあらゆる差別の禁止,障害者が社会に参加し包容されること等が規定され,締約国にその実現が求められたことがある1).さらに,日本では,2007年(平成19年)の「学校教育法」等の一部改正により,インクルーシブ教育の理念が組み込まれた2).また,合理的配慮は,この理念を実現するための重要な手段であり,障害のある幼児・児童・生徒が,他の幼児・児童・生徒と平等に教育を受ける権利を保障するために,個別の状況に応じた変更や調整を行うことが求められる.このように,インクルーシブ教育システムの構築が進められる中で,教育に対する考え方も,従来の「分離教育」から,多様な子どもたちが共に学ぶ「インクルーシブ教育」へと移行している.
一方で,医療・福祉制度に従事する作業療法士の立場からみると,「学校でのかかわり」は,これまで特別支援学校での肢体不自由児への支援等,限定的な場面にとどまることが多かった.また,特定の疾患や障害像の子どもを対象とする支援に焦点が当てられることが一般的であった.しかし,2023年度(令和5年度)文部科学省の調査3)では,全国の小・中学校における不登校児童生徒数は11年連続で増加し,約34万人を超えている.同調査3)では,教師が把握した不登校児童生徒からの相談内容として,「やる気が出ない」,「不安・抑うつ」等,メンタル面の課題が多い.発達特性や障害等の背景要因との関連があるとするならば,特別支援教育の枠を超えて合理的配慮が求められるケースが増えていることが示唆される.
このように,障害者に対する法整備の進展や社会的風潮の変化,また教育現場が抱える多様な課題に対し,環境因子も含めたアセスメントを基に,対象者の生活課題に寄り添った支援を行う作業療法士の役割は,今後さらに重要になると考える.
本増刊号の企画において「就学」および「学校でのかかわり」をテーマとするにあたり,特別支援学校や支援級といった支援の提供場所に限定せず,脳性麻痺,神経発達症,重度心身障害,医療的ケアが必要な児童等の疾患・障害像にとらわれることなく,包括的な視点で捉える必要性があると考えた.そのため,第2部ではライフステージ全体を見据えた作業療法のかかわりに焦点を当てる.第2,3章では,就学前および就学期の作業療法士の実践例を紹介し,第1章では,日本の制度の現状と課題,海外の実践例,そして学校における作業療法の歴史を概観することで,今後の方向性を考えるきっかけとしていただきたい.また,子どもの就学においては,子ども自身だけでなく,保護者や他職種の価値観・考え方も影響を与えるため,第4章では,就学に必要な環境調整として,保護者支援や多職種協働の視点から述べる.
さらに,教育現場とのつながり方や連携のあり方は地域によって異なり,本領域に従事する作業療法士はその違いを肌で感じているであろう.そこで,第5章では,地域全体を「学びの場」と捉え,地域とのつながりを築いてきた作業療法士の実践例を紹介する.
学校での学びは一過程であり,障害は一特性にすぎない.目の前の子どもを生涯発達の視点で捉え,5年後,10年後を見据えて支援することが求められる.本増刊号を通じて,「就労」そしてその先の生活につながる支援のあり方を考える機会になれば幸いである.
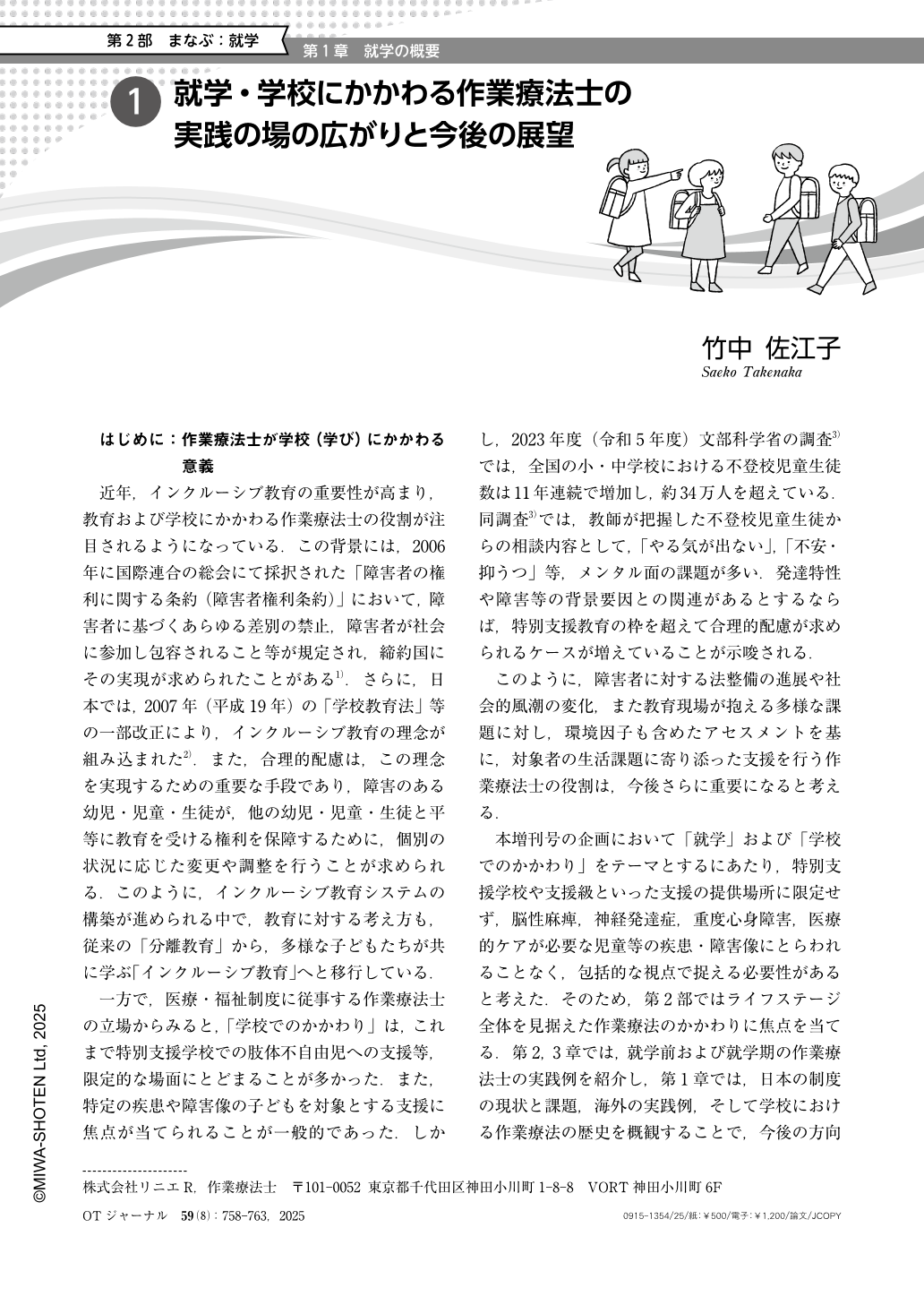
Copyright © 2025, MIWA-SHOTEN Ltd., All rights reserved.


