- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
はじめに
ロコモティブシンドローム(以下,ロコモ)とフレイルの違いを述べるには,まず両者の共通点を述べる必要があろう.まずロコモは2007年に日本整形外科学会によって提唱され,フレイルも2014年に日本老年病学会によって提唱された,いわゆるカタカナ英語である点である.ロコモは運動器機能不全や移動能力障害のような,「否定的な言葉を避け」ており,「蒸気機関車の力強さを連想させ,前向きな感じを与え」るように考案された1).フレイルも従来のfrailtyの訳語であった「生物学的に不可避な運命を暗示」する虚弱や老衰という言葉を言い換えている.これは,「高齢社会における健康長寿を支援する意識改革を意図する」とされている2).
否定的な表現を避けるという戦略は,認知症が痴呆症からの言い換えで,その認知に成功した点に倣ったという点で共通しているようである.これが推測の域を出ないにもかかわらず,確からしいと筆者が思っている根拠は,2012年頃に当時の千葉大学整形外科教室の高橋和久先生が主催された千葉市での講演会で,筆者が当時の国立長寿医療研究センターの鳥羽研二先生の前でうかつにも,「戦略的ロコモティブシンドローム考」と題して講演してしまったことによる.その後まもなくフレイルが提唱されたのは偶然ではないと密かに思っている.
それはさておき,両者とも世界で誰も経験したことがない長寿社会の問題を解決するために,「社会啓発・社会実装も視野に入れていることが共通である」3).また生活機能低下を捉え,その克服によって「健康寿命の延伸」を目指そうとしている点も共通している.両者とも加齢による身体機能の低下を非可逆的なものとは捉えず,何らかの介入により改善を期待できるものと考え,対策を提案している.ロコモでは,運動器疾患群,運動器疼痛,運動機能低下が,単独または複合して移動機能低下を生じる(図1)4)とし,フレイルでも生活機能低下やストレスに対する脆弱性が,身体的,精神・心理的,社会的な要素が単独または複合して生じるとしている点(図2)が共通している.介護を必要とする状態になることをエンドポイントとした場合,フレイルではそうでない人に比べリスクが4.6倍になり5),ロコモが進行したロコモ度3になるとロコモでない人に比べリスクが3.6倍になる4)ことが縦断研究でわかってきた点も共通している.
その他,両者ともステークホルダーが作成にかかわったガイドがある.ロコモには『ロコモティブシンドローム診療ガイド2010』とそれを大幅に改訂した『ロコモティブシンドローム診療ガイド2021』3)がある.フレイルには,『フレイル診療ガイド 2018年版』2)がある.
さらに両者とも公的な健診制度がある.主に65歳以上を対象としているフレイルでは2020年度から健診項目にフレイルに関する質問票が追加されている.これに対し,若年者をも対象とするロコモでは,学校健診への「四肢の状態」という項目の追加により,2016年度から全国小中学校で運動器検診が開始されている.
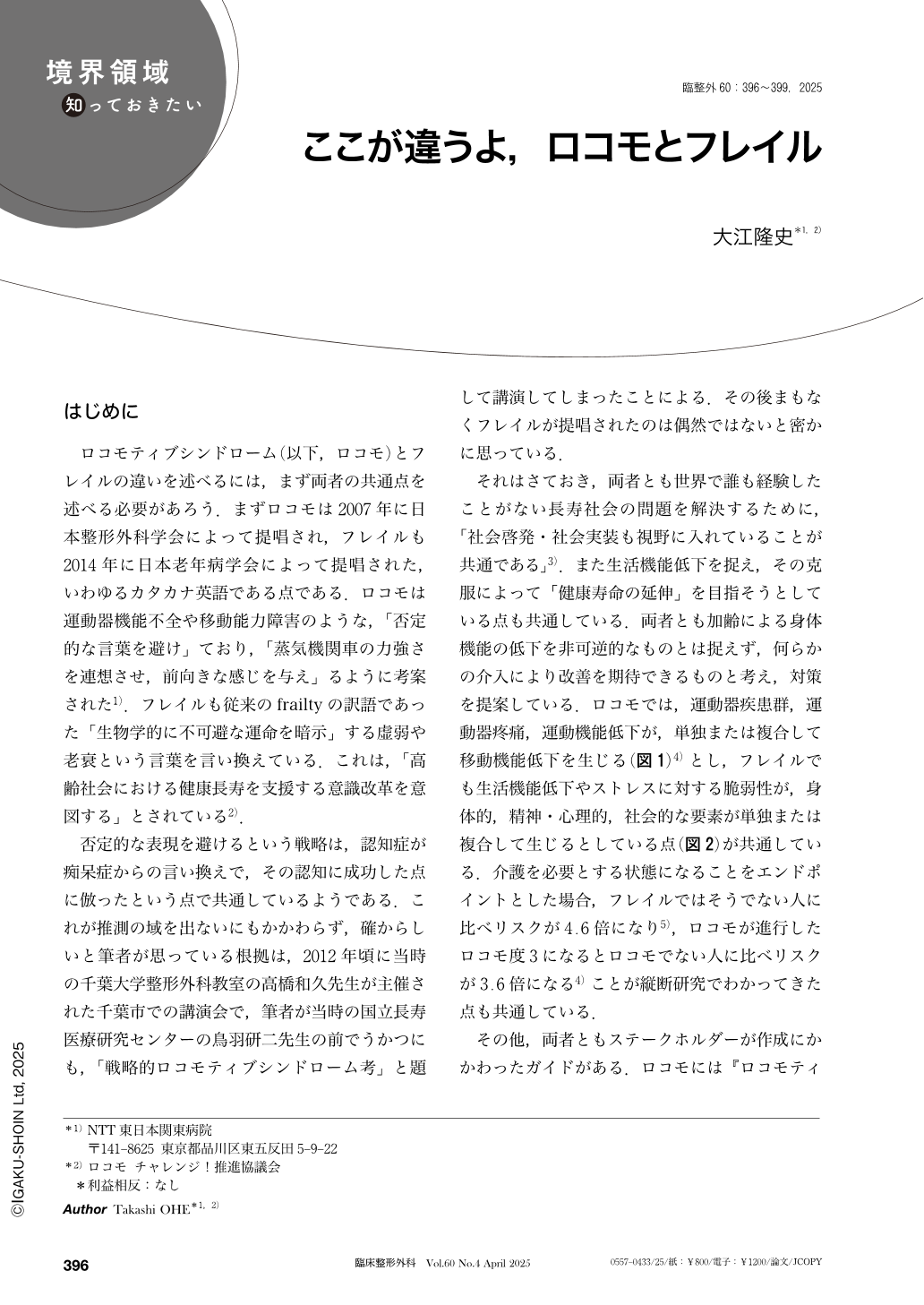
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


