- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
痛みは身体のみならず,脳やこころと密接に,しかもきわめて複雑に関連していることは精神保健の専門家にとっては今や自明の概念に近い。痛みや痛みに関連する症状を有した患者さんの診療に従事していて,頭を抱える経験をしたことがない精神保健の専門家はいないのではないだろうか。私自身の診療を振り返っても,緩和されない精神的なつらさをリストカットで和らげるしかすべのない患者さんにかける言葉やその対応に悩み,慢性的に続く痛みのために寝たきりのような生活を送っている患者さんに対して抱く無力感が思い浮かぶ。また,緩和ケアの領域では,モルヒネを使っても和らげることができない終末期の難治性のがん性疼痛に対して意識を落とすことしか方法がない患者さんにも遭遇する。先日は,がんの手術を受けた後に年余にわたる痛みが継続しているのに,主治医にその旨を伝えても「そんなに痛いはずがない」「命が助かっただけでもありがたいと思うべきだ」という言葉を浴びせられ,死んだほうがよかった,と涙ながらに話す患者さんにも出会った。私自身が一般の精神科診療に加え,サイコオンコロジーや緩和ケアに従事してきたこともあり,痛みに関しての疑問や課題が自身の頭から離れたことはない。
国際疼痛学会(IASP)による痛みの定義は「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する,あるいはそれに似た,感覚かつ情動の不快な体験」であり,痛みには,身体の感覚的な側面に加え感情的な要因が本来的に含まれている。一般的に痛みは,身体が障害やダメージを受けた際に警告信号として働き,外傷や病気の際には,身体の動きを制限し,自然治癒のプロセスを促すために役立つこともあるとされている。そういう意味では,痛みは人間の生存に不可欠なものでもある。
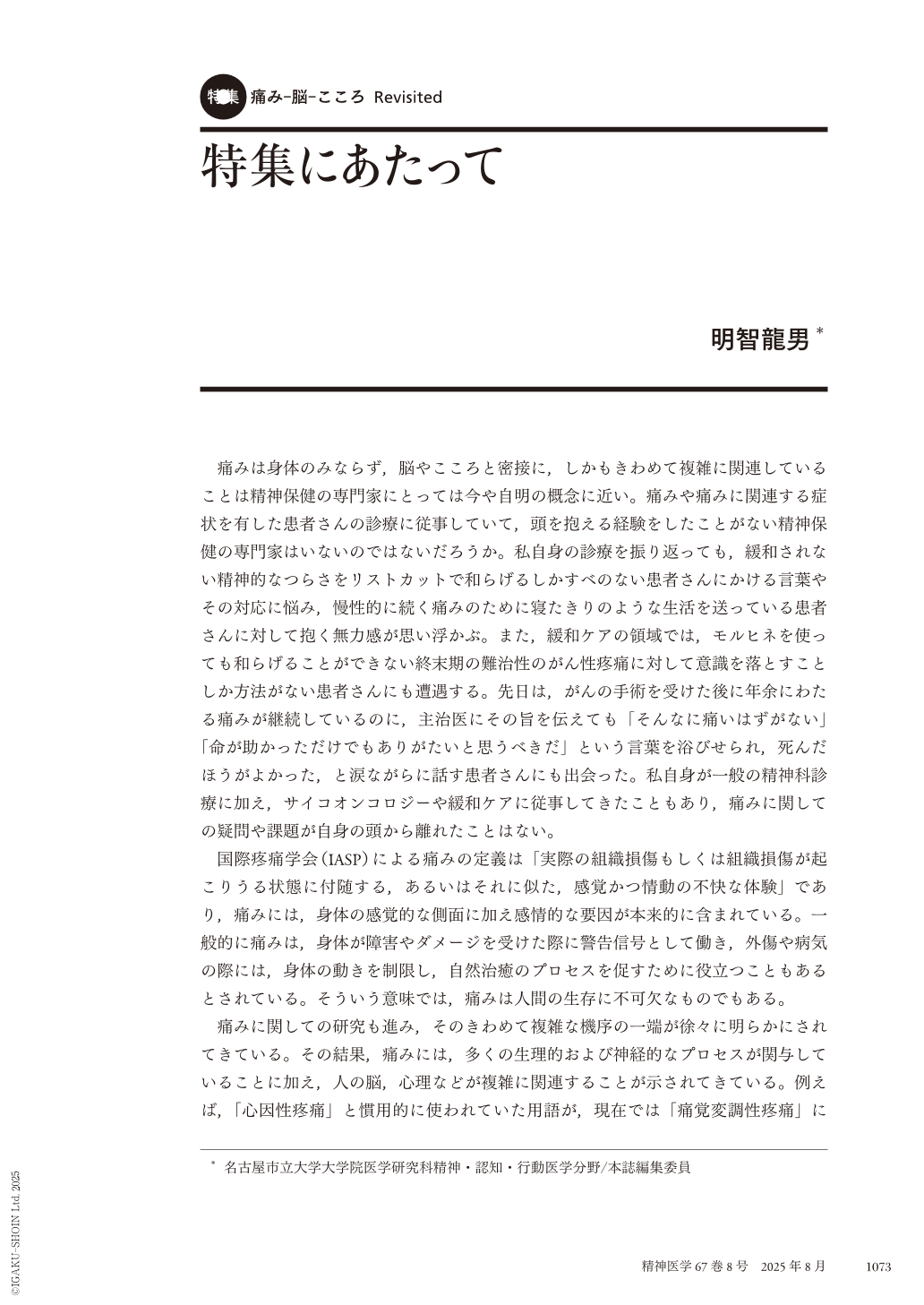
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


