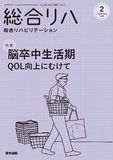Japanese
English
- 有料閲覧
- Abstract 文献概要
- 1ページ目 Look Inside
- 参考文献 Reference
はじめに
脳卒中患者にとって復職は社会復帰の一形態であり,自己肯定感や生きがいにもつながり,患者の生活の質(quality of life:QOL)向上のために重要な意義を有している.豊永1)は,就労していた障害者の最大のQOL向上は再就職することであると述べている.また,脳卒中後に復職できなかった者は,必要なニーズが満たされず心理・社会的転帰が悪化する2)との報告がある.65歳以下の発症時有職の脳卒中患者で復職できなかった46名すべてが,4年後のQOLの低下を認めている3).加えて,近年は家族構成,経済状況などから就労による収入を望む患者も増えてきており,脳卒中患者にとって復職へのニーズは高くなってきている.
少子高齢化が進む本邦では働き手の確保が必須であり,「働き方改革」でも,女性,高齢者,障害者をはじめとする多様な人材の労働参加が期待される.その政策の一つとして「治療と仕事の両立支援」を厚生労働省が推進し,2016年に「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を公表した.2018年には「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立し,国を挙げて脳卒中治療と仕事の両立支援を進めている.2020年の診療報酬改定で,これまでがん患者のみを対象としていた「療養・就労両立支援指導料」が,急性発症した脳血管疾患などの患者にも対象が拡大され,産業医がいない事業場も対象に含まれることとなった.加えて,初回のみであった算定も3か月を限度に月1回算定可能となり,医療機関-事業場間のより綿密な連携が可能となり症状に合った働き方を選びやすくなっている.2022年の診療報酬改定では,さらに対象疾患に脳卒中とも関連の深い心疾患,糖尿病などが加わり,情報通信機器を用いた場合(web会議など)にも算定が可能となり,治療と仕事の両立支援の充実が図られている.社会情勢からも脳卒中患者の復職は求められており,法律制定や診療報酬改正を重ねながら制度面は整いつつあるが,実際の医療現場での活用は十分とはいえず,現在は普及に向けた移行期に差し掛かっていると考えられ,さらなる治療と仕事の両立支援の促進には医療関係者の知識の向上が求められる.
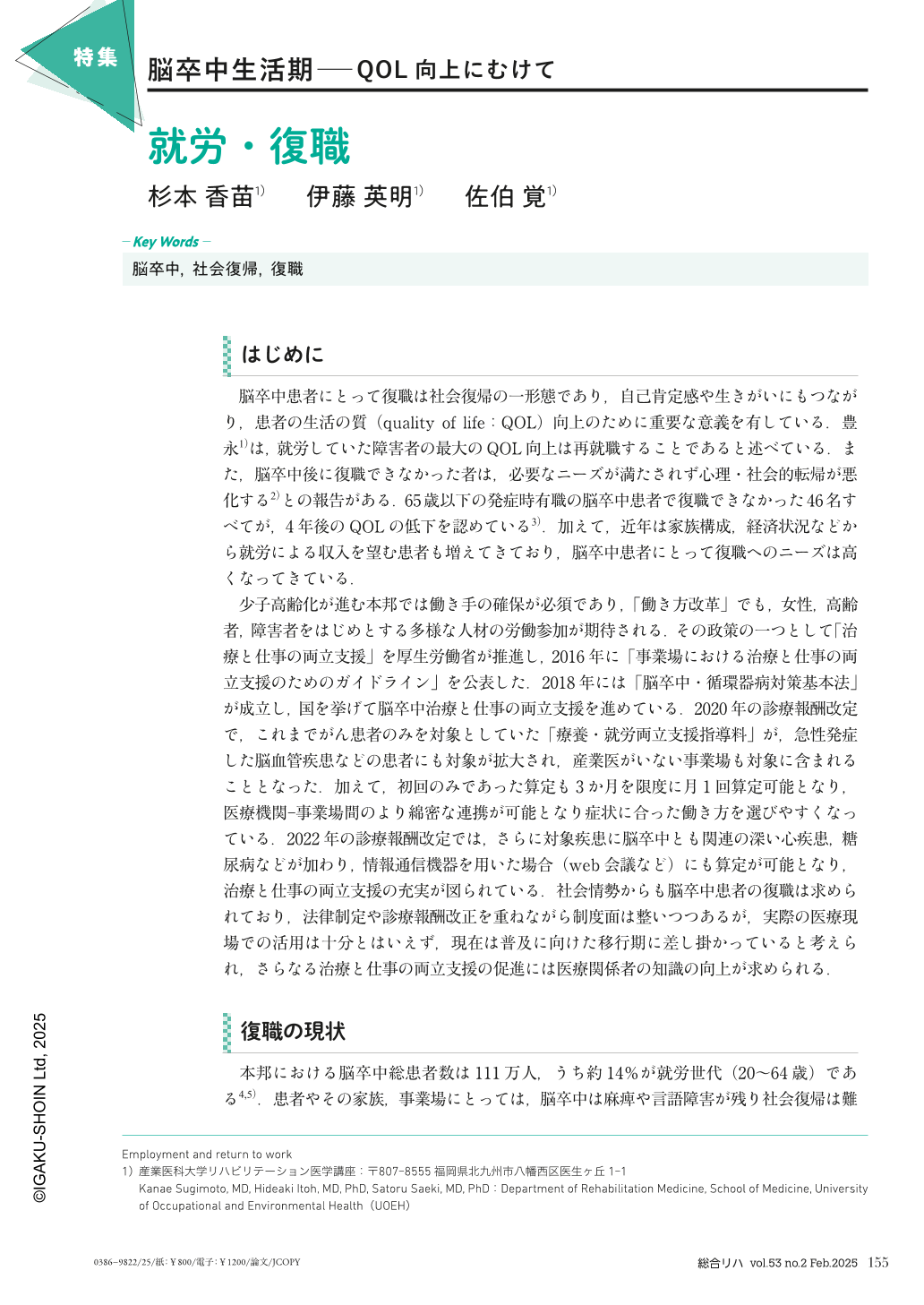
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.