特集 味と匂いの脳科学
特集「味と匂いの脳科学」によせて
吉原 良浩
1
1理化学研究所脳神経科学研究センター
pp.286
発行日 2025年8月15日
Published Date 2025/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.037095310760040286
- フリーアクセス
- 文献概要
- 1ページ目
1990年代,嗅覚研究は爆発的発展を遂げた。Lind BuckとRichard Axelによる嗅覚受容体遺伝子の発見に始まり,森憲作博士によって嗅球の“匂い地図”の概念が提唱され,その後の分子生物学,発生工学,神経活動イメージング研究によって糸球体ごとに嗅覚受容体がマップされていることが確認された。2000年代に入ると“1嗅細胞-1嗅覚受容体ルール”と“1糸球体-1嗅覚受容体ルール”を規定する分子,細胞,回路メカニズムの研究が,坂野仁博士らが中心となって展開された。
味覚研究については2000年代からブレイクスルーが相次いだ。Charles Zukerらによる味覚受容体の発見,基本五味のlabeled-line味覚神経経路の証明,味細胞の発生・分化を規定する転写因子群の同定,味細胞から味神経への情報伝達を担うATP放出チャネルシナプスの発見など,主に末梢における味覚受容・伝達についての研究が大きく進展した。
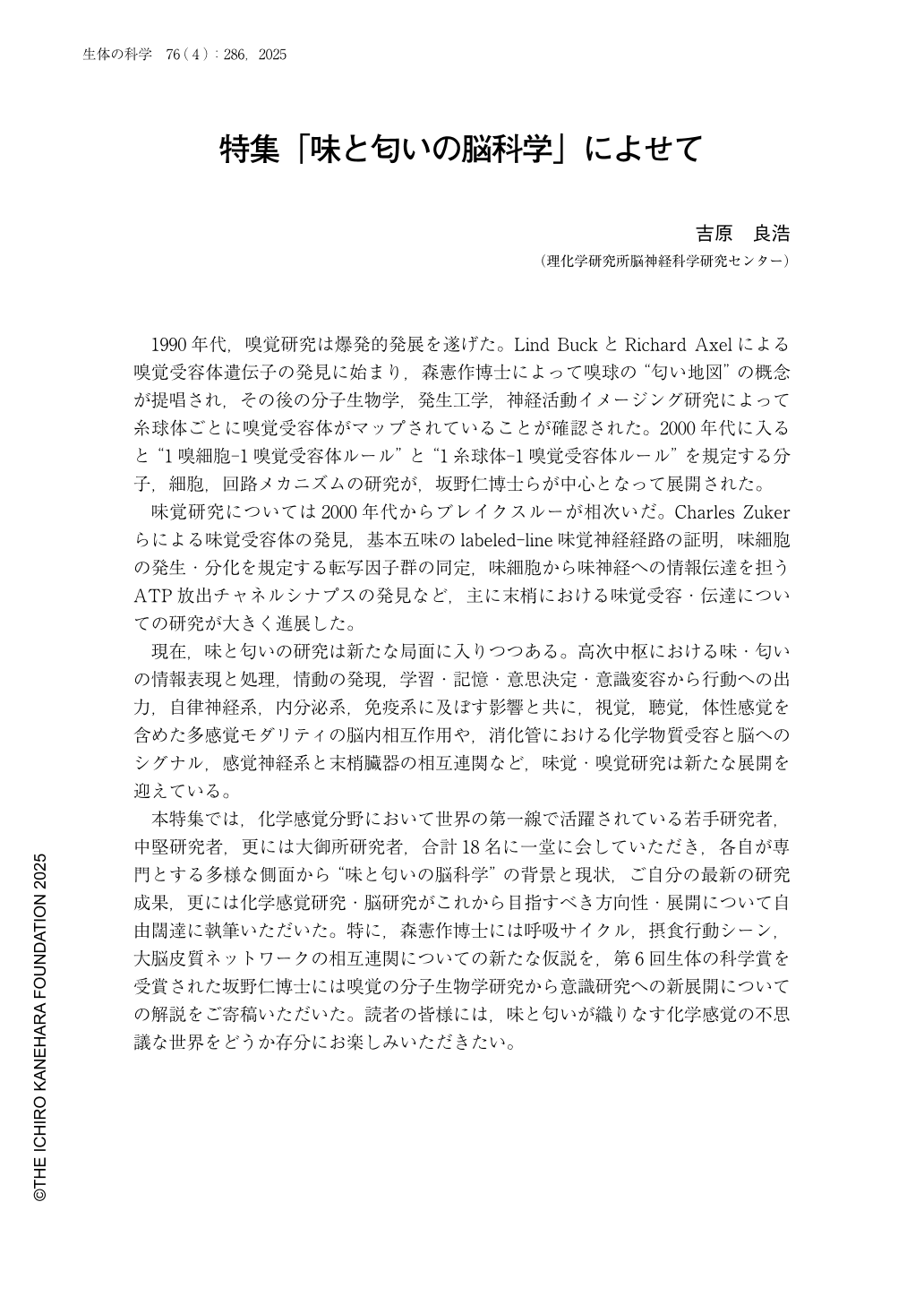
Copyright © 2025, THE ICHIRO KANEHARA FOUNDATION. All rights reserved.


