特集 「測りすぎ」評価からの脱却—看護の魅力に学生が気づける学びをどう支えるか
測りすぎの時代の学習評価論②—OSCE-Rにみる「学習としての評価」
松下 佳代
1
1京都大学大学院教育学研究科
pp.540-544
発行日 2025年10月25日
Published Date 2025/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.004718950660050540
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
パフォーマンス評価の中のルーブリック
前稿では、学習成果の評価のさまざまなタイプを把握するための枠組みを示した。ここからは、測りすぎの時代に求められる学習評価の形として、学習評価のタイプの1つであるパフォーマンス評価について論じていく。
日本では、パフォーマンス評価の研究は初等・中等教育のほうが先行してきた。とりわけ、いわゆる「思考力・判断力・表現力」の評価や探究の評価の方法としてパフォーマンス評価が注目されるようになったことにより、近年、学校現場にもかなりの広がりをみせている。一方、大学教育では、本来はパフォーマンス評価やポートフォリオ評価などにおける評価基準の一形式にすぎない「ルーブリック」のみが独り歩きしている観が否めない。「ルーブリック評価」という言葉の流布はその表れである。だが、パフォーマンス評価=ルーブリック評価ではない。
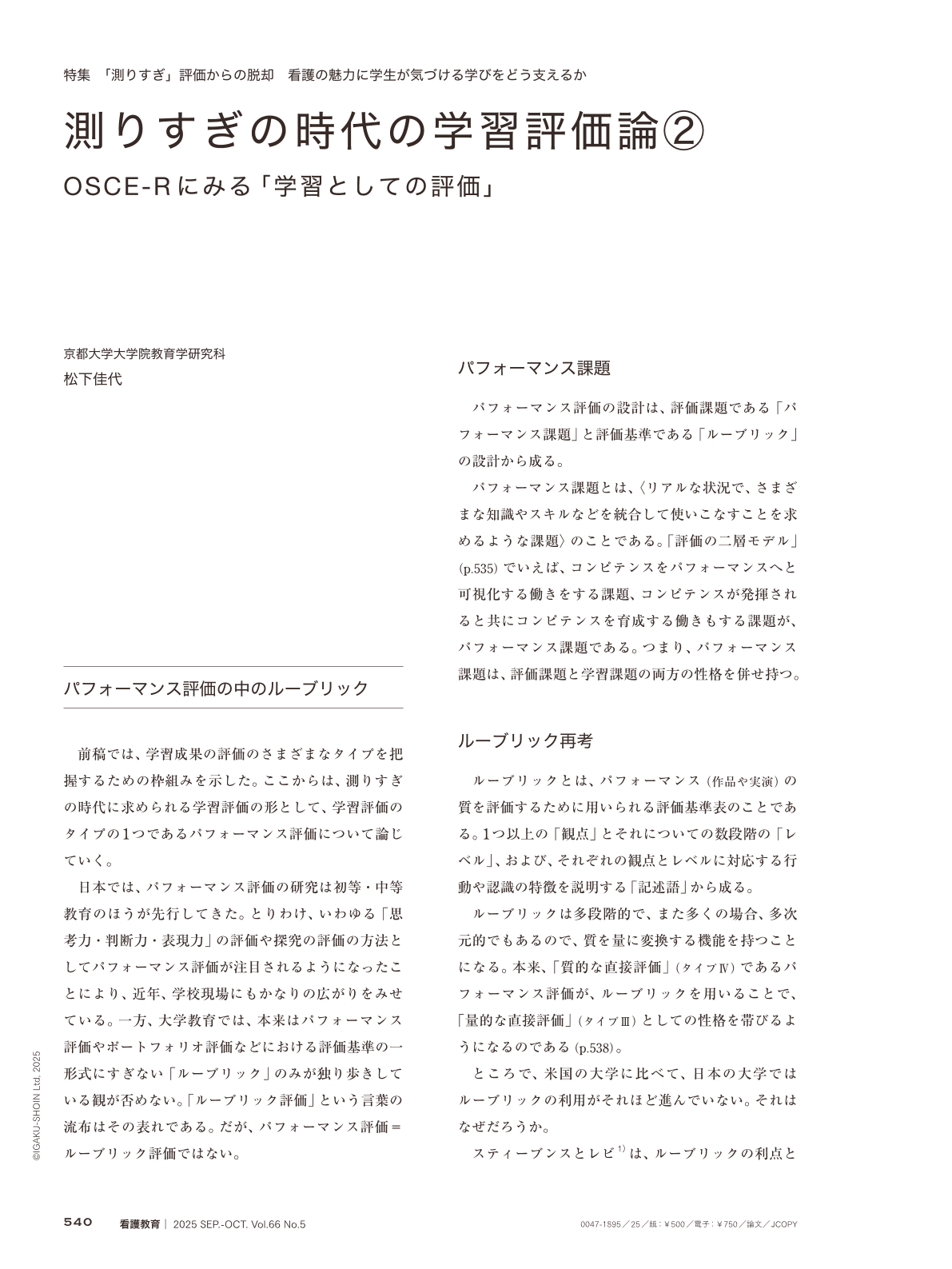
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


