特集 「測りすぎ」評価からの脱却—看護の魅力に学生が気づける学びをどう支えるか
測りすぎの時代の学習評価論①—評価の意味と構造
松下 佳代
1
1京都大学大学院教育学研究科
pp.534-538
発行日 2025年10月25日
Published Date 2025/10/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.004718950660050534
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
測りすぎの時代
現代は、「測りすぎ」の時代といわれる。歴史学者ジェリー・ミュラーの著作『測りすぎ』1)(みすず書房、2019)は、大学、学校、医療、警察、軍、ビジネスと金融、慈善事業と対外援助など、さまざまな領域での測りすぎ・測りまちがいを描き出して話題になった。この本の原題は『The Tyranny of Metrics』、直訳すれば「メトリクスの暴政」である。メトリクスとは、一定のルール・手続きに則って数値化するという行為、その際の測定法や測定基準、またはその結果としての数値や指標のことをいう。つまり、測定・測定法・測定基準・測定値といった意味を併せ持つ言葉である。「メトリクスの暴政」とは、このメトリクスが、社会のあらゆる領域に入りこんで、さまざまな悪影響をもたらしていることを指している。
ミュラーが大学を最初の検討対象として取り上げていることにも見て取れるように、教育の世界でも、特に2000年代に入ってから、「エビデンスに基づく政策・実践」や「説明責任」の名の下に、教育成果や学習成果の測定・評価が強く要請されるようになってきた。この時代において、評価を、教える側、学ぶ側の双方にとって意味あるものにすることは果たして可能なのだろうか。そのためには何が必要なのだろう。
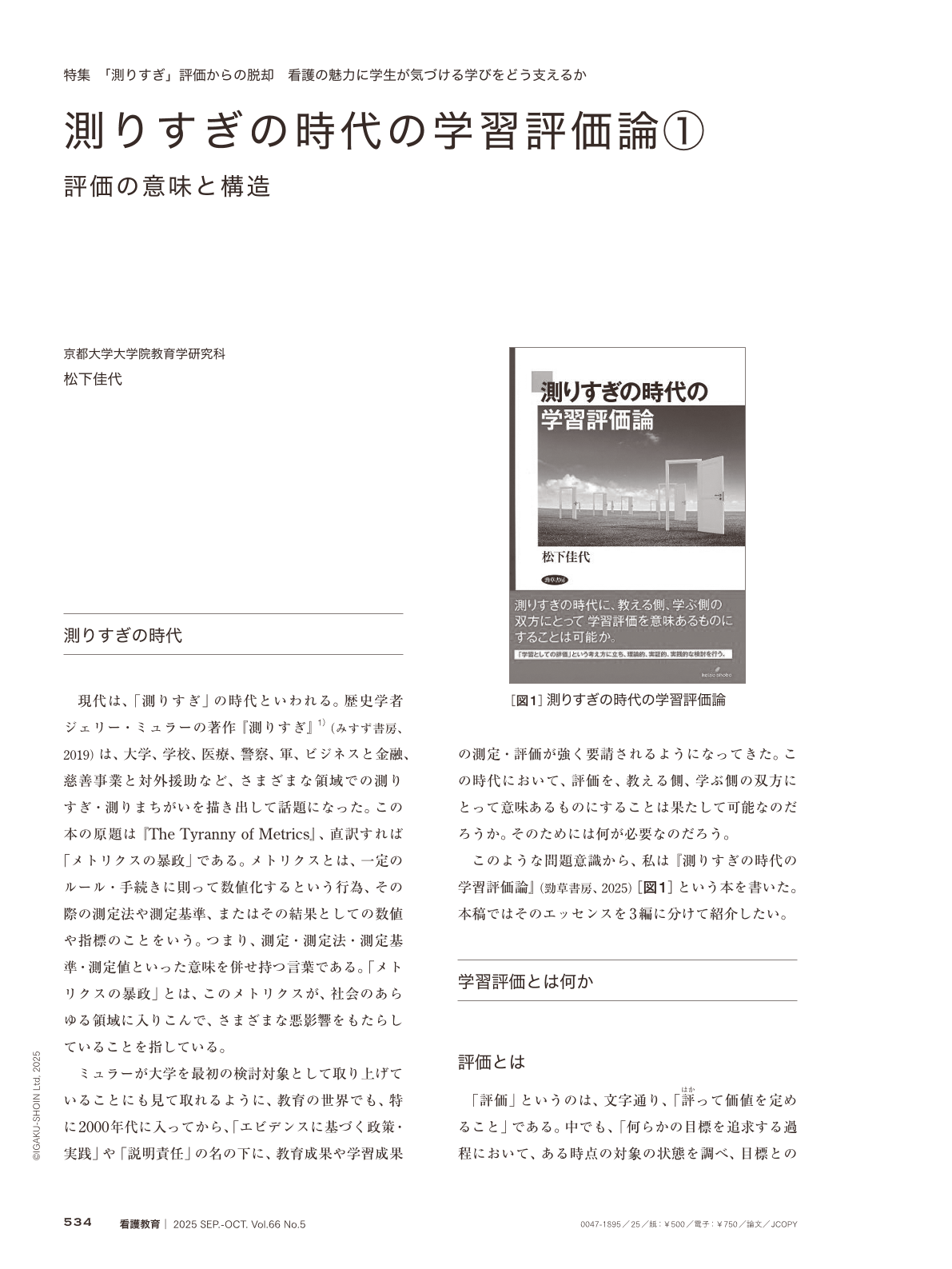
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


