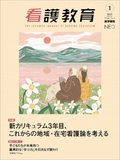特集 新カリキュラム3年目、これからの地域・在宅看護論を考える
地域に広がる精神科訪問看護―現場で気づけた看護の大切なもの
崔 明玉
1
1訪問看護ステーションみのり
pp.50-55
発行日 2025年2月25日
Published Date 2025/2/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.004718950660010050
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
はじめに
私が現在所属している訪問看護ステーションみのり(精神科特化)では、利用者さんに訪問看護の役割を説明する時、以下のように伝えています。
「(あなた自身が)症状と付き合いながら、生活を組み立てていく『お手伝い』をします」
あくまで訪問看護は「お手伝い」であり、主体は利用者さん自身なのだということを強調するためです。
なぜ「利用者主体」を強調しているのかというと、理由はいくつかあります。
精神疾患は慢性疾患であり、「自分自身が」うまく病気と付き合っていくという視点が大切になります。また、精神疾患の特徴として、治療に受け身になりやすいことも挙げられます。目に見える傷や骨折などとは違い、精神症状は目に見えないため、病気という認識を持ちにくかったり、社会的な偏見により病気として認めたくない気持ちを抱いたりもします。また、訪問看護と聞くと「何かをしてくれる」とか、「あれは駄目、これは駄目と管理される」というイメージを持つ方が多いので、その誤解を解くためでもあります。病状管理・治療に重きが置かれる入院環境とは異なり、地域では生活が中心になり、利用者さんの主体的な営みに重きが置かれることになります。
慢性疾患の増加、在院日数が縮小される医療制度など、当ステーションが大切にしている「利用者主体」という考え方は、地域医療のニーズに応えていくための重要なキーワードだと思っています。
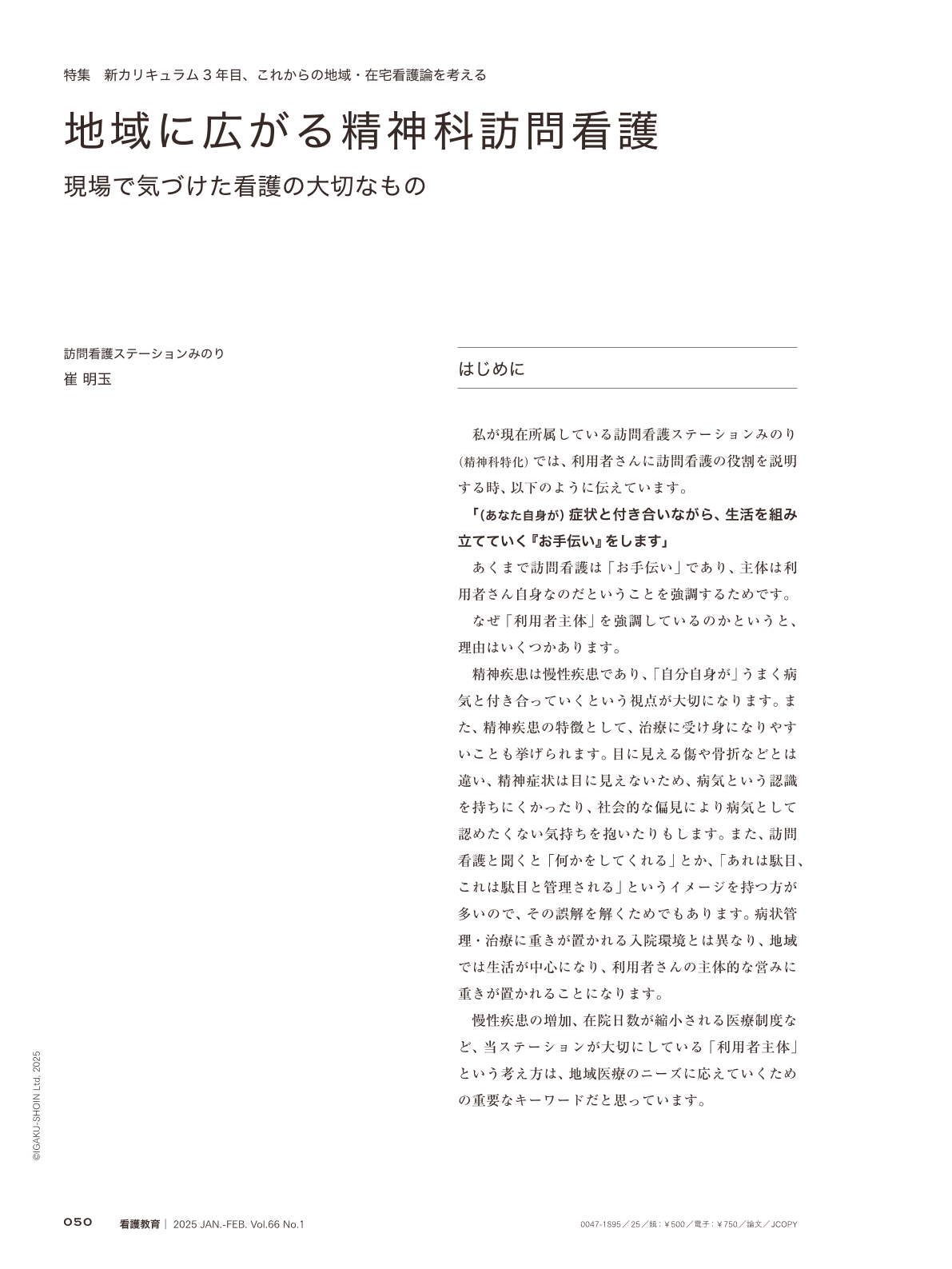
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.