- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
- 参考文献
本特集のねらい
長寿命社会を迎え,「健康」への関心が高まっている。心の健康としてメンタルヘルス,身体の健康として運動の機会や適切な食事,社会的な健康として社会的処方註1を,といった具合に,多方面からのアプローチがある。このような多面的な健康は,人々の暮らし方によって実現する一方,その舞台となるまちのあり方によっても支援ないし規定される。例えば,住民の運動機会を促進し高齢期など移動手段に制約がある場合でも社会的参加の機会を得やすくする「歩いて暮らせるまちづくり註2」は,その一例である。歩道を歩きやすく整え,自動車を制限して共存できるようにし,ベンチなどの休める設えを随所につくり,訪ね先となる公共施設や生活関連施設を歩ける範囲内に置く。こうした公園や公民館,図書館など「集まる場所」があることは,コミュニティを形成・醸成し,災害時等を含む相互扶助の土台となることが報告されている(Klinenberg, 2018/藤原訳,2021)。日本でもここ30年ほどの関心事として,公的な場所だけでなくさまざまな居場所がまちにあることの重要性についてさまざまな論説や実践が重ねられてきた。その発端は,ニュータウンのような「つくられたまち」では,公民館や図書館だけでは住民の主体的活動やコミュニティ形成が難しく,住民自らが居場所をつくる運動を始めたことにある。地域の居場所は,人とまちの健康を支える拠点である。
そのような地域の居場所はいま,日本だけでなく各国でつくられている。本特集は,ドイツの連邦プログラムとして実施されドイツ全土で運営されている「多世代の家」(Mehrgenerationenhaus:以下,MGH)でのさまざまな取り組みやその効果を,日本国内の事例と比較しつつ紹介する。MGHは地域の居場所であり,かつ「多世代」でその場所を利用することで多世代の交流を促すことが重視されている点が特徴的だ。MGHの多様な取り組みは,公的団体から民間団体まで多様な担い手によって実現されている。それを支えているのは,自分たちごと註3として社会問題を捉え,自らの心身・社会的な健康を市民自らつくろうとする市民社会である。看護・介護や建築の専門家がそれぞれの視点で捉え,その見解を交換することで得た論点を共有し,学際的なケア研究の展開につなげることが,本特集のねらいである。
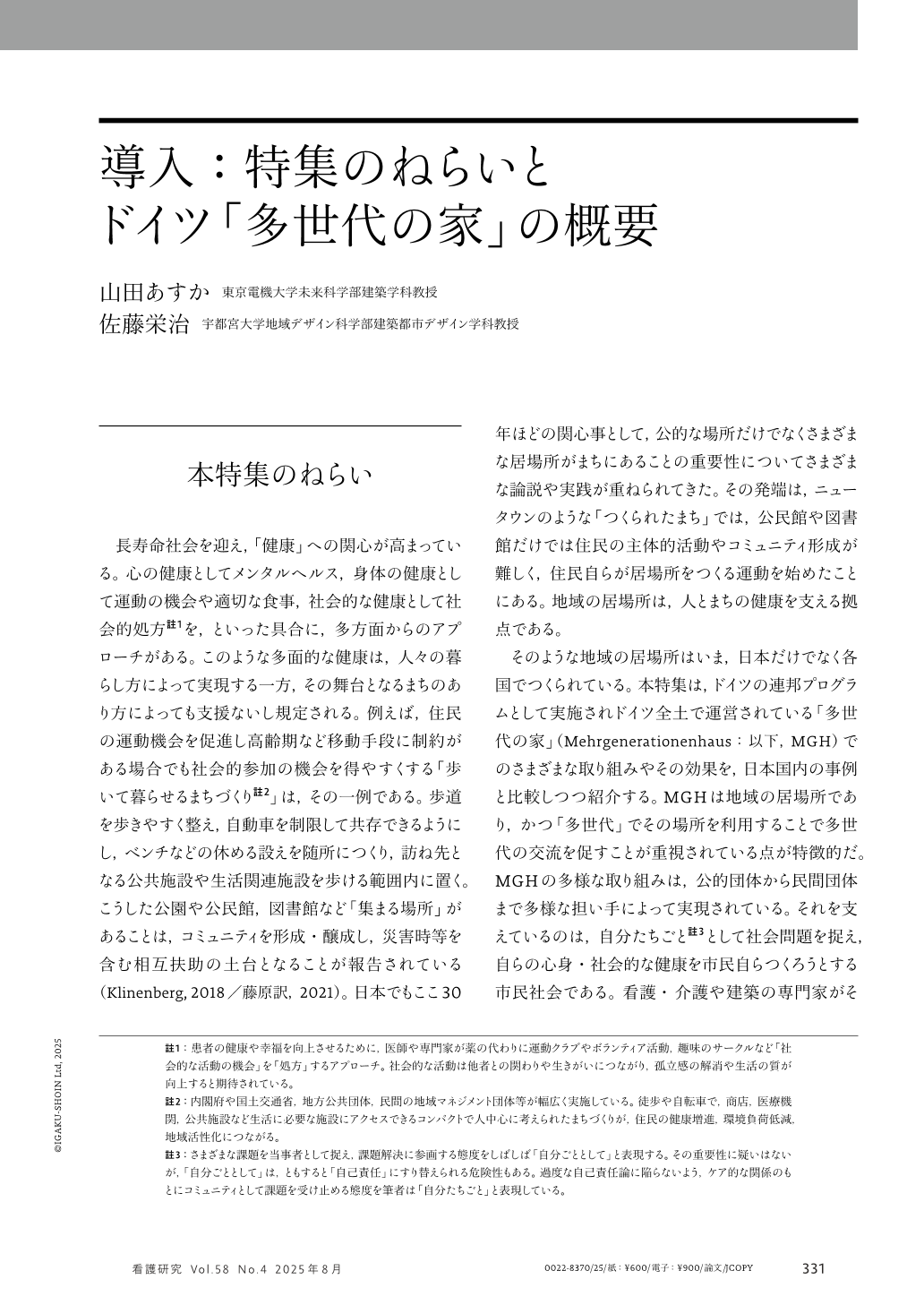
Copyright © 2025, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.


